この記事を読んでわかること
・嚥下障害とは?
・5つの過程
・嚥下リハビリテーションと口腔ケア
脳梗塞の患者の多くにあらわれる後遺症である嚥下障害。
嚥下障害になると食べ物が食べにくくなってしまうため、栄養不足や脱水を引き起こしやすい状態です。
また誤嚥して誤嚥性肺炎に発展してしまうと命にかかわる可能性があります。
この記事では、嚥下障害のメカニズムやリスク、リハビリなどについてご紹介します。
嚥下障害とは?原因と症状を詳しく解説

食べ物を口に入れてから飲み込むまでの過程が、正常に機能しなくなった状態を嚥下障害といいます。
嚥下障害になると食べ物が飲み込みにくい、飲み込めない、つかえる、むせる、咳き込むなどの症状があらわれます。
嚥下は5つの過程に分けられる
嚥下は以下の5つの過程に分けられます。
- 先行期:食べ物を視覚や嗅覚などで認識して口に運ぶ前の時期
- 準備期:口の中で食べ物を噛み砕き食塊にする時期
- 口腔期:食塊を舌を使って喉の奥に運ぶ時期
- 咽頭期:嚥下反射が起こり、食塊が食道へ運ばれる時期
- 食道期:食塊が食道から胃へと運ばれる時期
どの過程に問題があるかを突き止めることが大切です。
失われた機能によってリハビリ方法が変わってきます。
嚥下の過程と嚥下障害のメカニズム
食塊を喉の奥に運ぶためには、舌を上手に動かせなくてはいけません。
脳梗塞によって舌の動きに障害が残り舌が上手に動かせなくなってしまうと、喉の奥に食べ物を運びにくくなり口腔内に残りやすくなります。
食べ物を飲み込むとき、喉頭蓋が気道を閉鎖(嚥下反射)することで食べ物は気道には入らず食道に運ばれます。
しかし嚥下反射が上手く機能しないと、本来食べ物や唾液が運ばれる食道ではなく気道のほうに流入してしまうことが起こります(誤嚥)。
食道括約筋の働きが低下すると、食塊が逆流したり通過障害が起こる可能性があります。
嚥下障害が引き起こす誤嚥性肺炎や脱水等のリスク
嚥下障害を放っておくと、飲みものや食べ物を口から摂ることが難しいため、脱水や栄養状態の悪化を引き起こしてしまう可能性があります。
そうすると、栄養が不足してしまい飲み込むときに使う筋肉が低下し、さらに食べ物が食べにくくなるという悪循環に陥ってしまいます。
また誤嚥して口の中にいる細菌が食べ物や唾液と一緒に気道に入り込み、肺まで運ばれ炎症を起こしてしまうと、誤嚥性肺炎に発展してしまう可能性があります。
誤嚥は嚥下障害ではない人にも起こりますが、むせや咳き込むことで気道内から異物を出せます。
しかし、脳梗塞などで嚥下機能が低下している方は、誤嚥しても咳き込まないことがあるため肺炎に発展する可能性が高くなってしまうのです。
また嚥下障害で栄養状態が悪化して免疫力が低下している方は、誤嚥すると肺炎を引き起こしやすい状態になっているため、より一層注意する必要があります。
嚥下リハビリテーションと口腔ケア

嚥下障害のリハビリテーションは、飲み込む力を改善するために様々なトレーニングが行われます。
嚥下障害は、医師や歯科医師、言語聴覚士、管理栄養士などと連携しながら、嚥下障害の状況に応じて訓練や食事の工夫を行います。
嚥下訓練
- 嚥下訓練
- 食べ物を使わない間接訓練と実際に食べ物を使って行う直接訓練があります。
- 間接訓練
- 喉や舌、頬など嚥下するときに必要となる器官のマッサージやトレーニングを行うことで、嚥下力の改善を図ります。
- 直接訓練
- 咀嚼のいらない水分やゼリーなどから始め、徐々に通常の食事に近い物を食べる訓練をしていきます。
- 直接訓練
- 誤嚥のリスクがあるため専門家の指導のもと行う必要があります。
食品形態の工夫
咀嚼に問題がある場合は、食べ物を小さく刻んだり、柔らかく調理したりするなどの工夫をします。
飲み込みに問題がある場合は粘着性のある食べ物は避け、のどを通りやすいように食べ物にとろみをつけるなど工夫をすることが大切です。
口腔ケア
口腔ケアは、嚥下リハビリテーションにおいて欠かせない要素です。
。嚥下機能が低下すると、食べ物の残留物や細菌が口内に溜まりやすくなり、口の中に食べかすなどが残っていると細菌の増加を招きます。
口腔内を清潔に保つことで口の中の細菌を減らし、誤嚥性肺炎のリスクを低下させることができます。
口腔ケアを行うのは食後だけではありません。
寝ている間は口の中が乾燥し最も細菌が増殖しています。
そのため、起床後と就寝前にも口腔ケアをすることをおすすめします。
口腔ケアと嚥下リハビリを併用して
日常的な口腔ケアとリハビリを併用することで、口腔内の衛生を保ちつつ、飲み込みの力を回復させることが可能です。
特に、口腔ケアをしっかり行うことで、リハビリの効果を最大限に引き出し、誤嚥や感染症のリスクを減少させます。
当院で行っている脳卒中や脊髄損傷を専門とした再生医療リハビリ
脳卒中や脊髄損傷などによる後遺症は、リハビリをしただけで完全に回復することはほとんどありません。
しかし、再生医療で損傷を受けた脳細胞や神経を再生し易い下地作りをしてあげることができれば、リハビリにより大きな機能改善が期待できるようになります。
当院では、脳卒中や脊髄損傷の後遺症改善を専門とした再生医療とリハビリを組み合わせた新しい複合治療法「ニューロテックⓇ」を行っています。
リハビリを行うとそれに対応した脳の部位の血流が増加し、再生医療による血管新生作用と神経再生作用がさらに高まります。
嚥下障害やリハビリについてのまとめ
嚥下障害やリハビリについてご紹介しました。
脳梗塞の後遺症のリハビリは、早い時期に始めれば始めるほど効果があらわれやすいことがわかっています。
しかしリハビリ中の誤嚥により深刻な状況を招く可能性があるため、専門家の指導のもと適切なリハビリを行いましょう。
関連記事
気になる記事:嚥下障害の看護と自宅で必要なケア
外部サイトの関連記事:嚥下障害の患者にご家族ができること




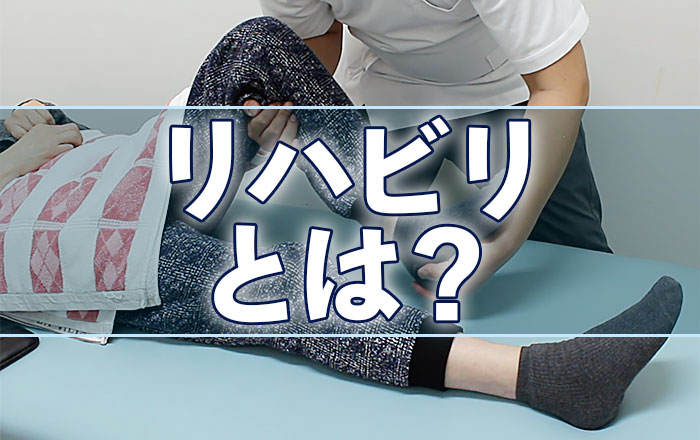










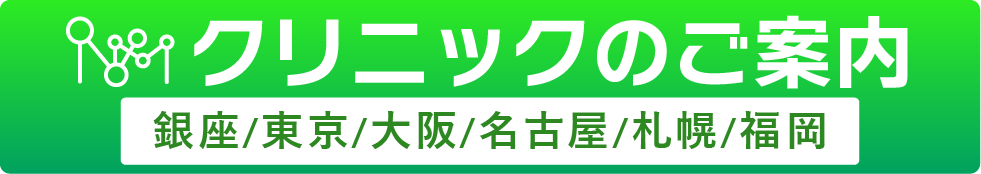
コメント