この記事を読んでわかること
・中心性頸髄損傷について
・中心性頸髄損傷の特徴は
・中心性頚髄損傷の症状
中心性頸髄損傷とは、主に交通外傷やスポーツによる頸部の過伸展が原因で生じる頸髄の病気です。
主に頸髄の中心部のみが損傷するため、逆に中心部から離れた外惻の神経は損傷を免れます。
症状は下肢よりも上肢に優位で、主に上肢のしびれや麻痺などの症状が強く出現します。
今回は中心性頸髄損傷の病態や予後について解説していきます。
中心性頸髄損傷について
中心性頸髄損傷とは、その名の通り頸髄の中心部のみが損傷した状態を指します。
主に交通外傷やスポーツ外傷により頸部に過剰な伸展がかかると、頸髄は中心部に負荷がかかり損傷をきたす可能性があるのです。
では頸髄の広範な損傷と中心部のみの損傷では具体的にどんな違いがあるのでしょうか?
中心性頸髄損傷の特徴は?
そもそも頸髄とは頸部の脊髄という意味です。
頸髄の下には胸髄、腰髄、仙髄と続いて全部合わせて脊髄と言います。
脊髄には、脳からの指令を上肢や下肢に伝えて運動を支配したり、逆に体が得た熱さや寒さ、痛さなどの感覚を集めて脳に送る橋渡し的な機能があります。
本来の脊髄損傷の意味するところは、損傷したレベルの脊髄が全体的に障害されるため、脳からの指令が損傷レベル以下の脊髄には一切届かず、逆に損傷レベル以下の脊髄からの情報も脳には一切届かなくなることで麻痺やしびれが出現するという病気です。
しかし、損傷したレベルの脊髄が部分的に障害されるとしたらどうなるでしょうか?
その場合、患者に発現する症状も部分的になってしまうのです。
脊髄を断面で見たときにどの部分を損傷したかで出現する症状が千差万別ということになります。
脊髄の中を通る感覚を伝える神経や、運動を伝える神経は、それぞれ中心部から頸髄、胸髄、腰髄、仙髄の順に走行しています。
つまり中心部ほど上肢や体幹の感覚や運動を支配していて、中心から離れるほど下肢や膀胱、直腸などの感覚や運動を支配しているわけです。
中心性脊髄損傷は、脊髄を断面で見たときに主に中心部が損傷する疾患ですので、上肢の機能が下肢の機能よりも不釣り合いに優位に損傷した場合、中心性頸髄損傷が疑われます。
中心性頸髄損傷の主な症状
主に上肢のしびれや感覚障害、麻痺などが出現します。
さらに、箸を使ったり洋服のボタンを留めるような繊細な巧緻運動障害も障害されます。
下肢にも軽度の症状が出現する可能性がありますが、比較的軽症もしくは改善することがほとんどです。
脊髄の中で最も外側を走行する仙髄の機能である排尿や排泄は、下肢の症状の次に改善していくという特徴があります。
そのほかに、上肢の深部腱反射が亢進し、ホフマン反射、トレムナー反射などの病的反射が出現します。
また一定期間麻痺症状が継続すると、使用することができない筋肉は萎縮してしまいます。
特に高齢者の筋線維数は80歳までに約40%減少し、上肢よりも下肢で低下率が大きいため、症状改善後に筋萎縮のせいで歩行できなくなる高齢者も珍しくありません。
中心性頸髄損傷では下肢筋の廃用性筋委縮を予防することが重要になります。
中心性頚髄損傷は治る?
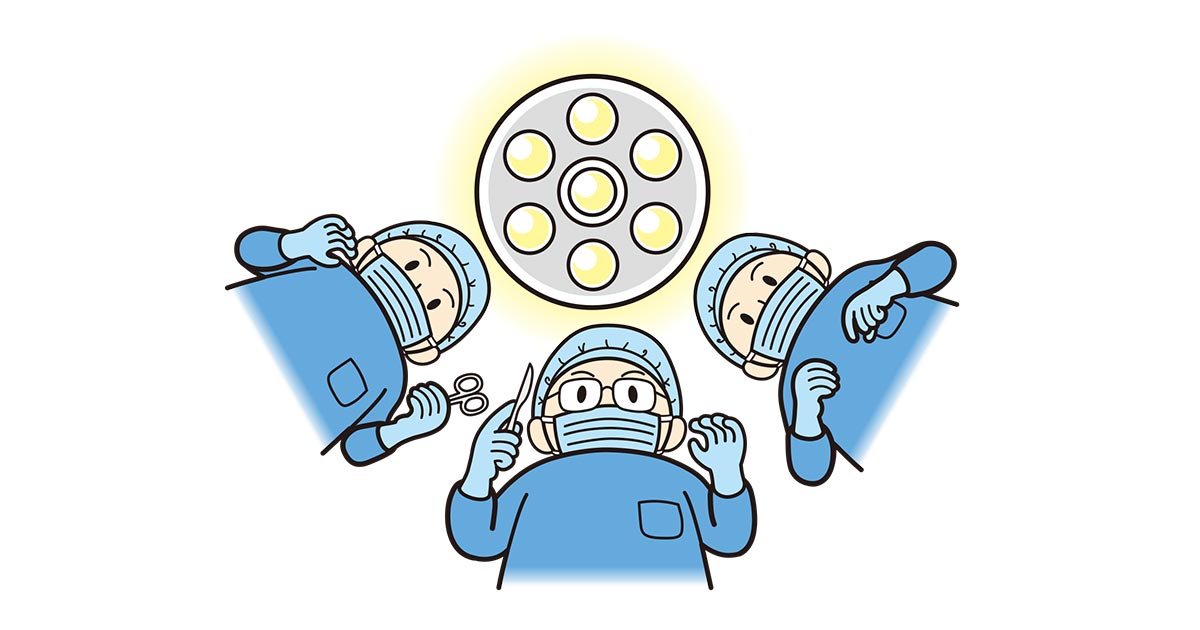
中心性脊髄損傷は比較的予後良好な疾患であり、約70%の患者は自然経過で神経所見が改善していくと言われています。
特に、40歳以下の広い脊柱管の人は予後が良好であると報告されています。
逆に、高齢者で脊柱管狭窄症などの脊椎の病気を持っている方は重症化しやすいので注意が必要です。
実際に中心性頸髄損傷に罹患した人の個人ブログなどでは、時間経過とともに下肢の症状がほとんどなくなったと書かれていることも多いです。
しかし実臨床では、中には下肢症状が強く残存する患者も散見されます。
仮に後遺症が強く残る場合は、後遺障害等級の認定を受けて適切な介護や介助を受けることをお薦めします。
中心性頸髄損傷の場合、後遺障害等級の認定を受けるにはMRIでの脊髄損傷の画像所見が非常に重要になりますので、必ず医療機関で評価を行ってもらうようにしてください。
症状が重症化した場合には、手術療法や薬剤療法などの選択肢があります。
超急性期の受傷直後の手術であれば脊髄損傷の予後が改善する可能性はありますが、実臨床では8時間以内の手術がゴールデンタイムとされています。
それ以降の手術療法に関してはその効果に対する評価は一定ではありません。
また薬剤療法にはステロイド投与などが挙げられますが、これも神経学的予後を大きく改善させるような効果は見込まれていません。
中心性頸髄損傷の治療法と予後と再生医療の可能性
中心性頸髄損傷では、保存療法と手術療法の2つが主に選択されます。
軽度の場合は安静や装具使用で症状の改善を目指しますが、重度の場合は手術が必要です。
リハビリテーションは、筋力回復と機能改善を目的に行われ、早期のリハビリ開始が重要です。
また、幹細胞治療などの再生医療は、神経機能の回復に期待される新しい治療法として注目されています。
中心性頸髄損傷についてのまとめ
神経細胞は一度損傷すると機能の回復は困難です。
中心性頸髄損傷では上肢に神経症状が残存しやすく、日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
しかし、近年では再生医療の発達が目覚ましいです。
骨髄から採取した幹細胞を点滴から投与すれば、幹細胞が神経に定着して死んだ神経細胞の代わりとなり再び機能が甦る可能性があるのです。
再生医療を併用すれば、リハビリによる機能回復にさらなる期待が持てます。
現在、多くの治療結果を積み重ねており、その成果が期待されています。
よくあるご質問
- 中心性頸髄損傷の主な症状は?
- 主に上肢のしびれや感覚障害、麻痺などが出現します。
さらに繊細な巧緻運動障害も障害されます。
下肢にも軽度の症状が出現する可能性がありますが、比較的軽症もしくは改善することがほとんどです。 - 中心性頚髄損傷は治る?
- 中心性脊髄損傷は比較的予後良好な疾患であり、約70%の患者は自然経過で神経所見が改善していくと言われています。
あわせて読みたい記事:非骨傷性頸髄損傷の病態や症状と治療について
外部サイトの関連記事:再生医療による頸椎・頚髄損傷治療について



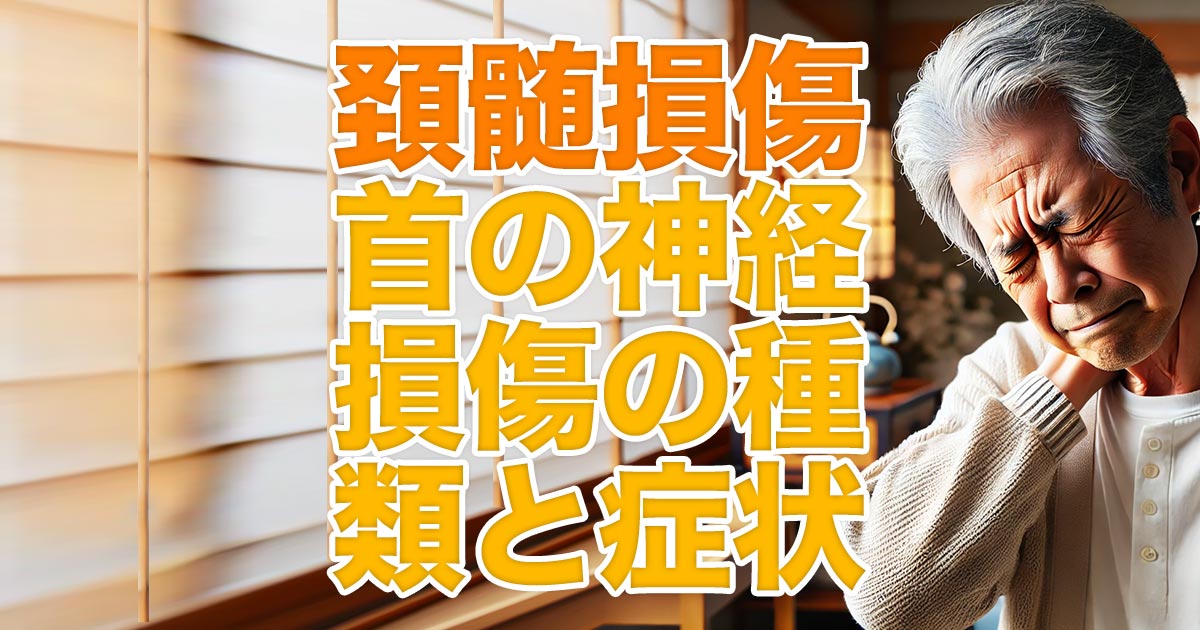
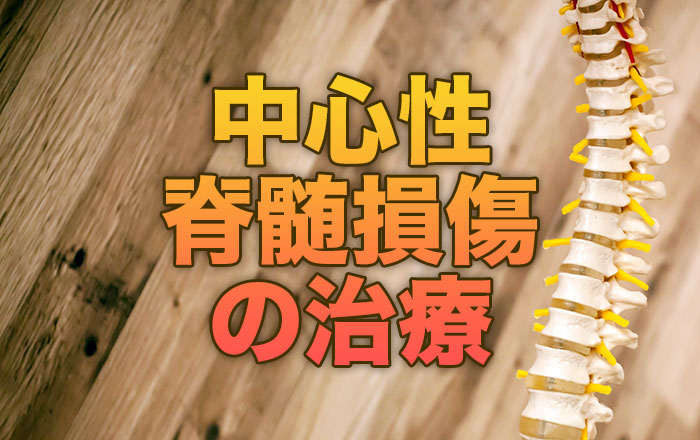













コメント