この記事を読んでわかること
高血圧と生活習慣病
高血圧の素因となるリスクファクター
心の健康が血圧に及ぼす影響
高血圧は生活習慣病の1つであり、3人に1人が罹患すると言われるまさに国民病です。
長期的な高血圧は、心臓や大動脈、腎臓、脳血管などさまざまな重要臓器に悪影響を及ぼすため、事前にしっかりリスクを把握し、予防することが重要です。
そこでこの記事では、高血圧の原因となるリスクファクターについて解説します。
生活習慣と高血圧

日本人はこれまで世界的にみても血圧の高い民族であり、その原因について「島国だから海産物の摂取が多い」「漬物文化によって塩分摂取が多い」「味噌汁の塩分が影響している」などさまざまな説が唱えられてきました。
しかし、1960年代以降、国民の生活環境の変化や、高血圧に対する薬物治療の進歩・普及、国全体での生活習慣病に対する予防対策推進などによって、国民の平均血圧は大きく低下しました。
一方で、深刻な高齢化や食文化の欧米化によって、将来的に平均血圧が上昇に転じる懸念も示唆されています。
高血圧の素因となるリスクファクター

高血圧は何よりも予防が大切であり、そのためには高血圧のリスクを把握しておく必要があります。
中でも乱れた生活習慣はリスクとなり、具体的には下記のような生活習慣が挙げられます。
- 乱れた食生活
- 過剰な飲酒
- 喫煙
- 運動不足
- 肥満
乱れた食生活については後述しますが、喫煙や運動不足・肥満なども高血圧のリスクとなります。
タバコに含まれるニコチンは末梢血管を収縮させ、心拍数を増加させる薬理作用を伴うため、血圧が上昇します。
さらに、血管内皮細胞を損傷することでコレステロールが血管壁に沈着しやすくなり、動脈硬化を招きます。
また、運動による発汗は体内に蓄積したナトリウム(塩分)を体外に排出し、血圧を低下させます。
さらに、運動によるリラックス効果によって自律神経のバランスが整い、血圧を安定化させる効果も期待できます。
そのため、運動不足は高血圧の原因となります。
また、肥満(BMI25kg/m2以上)の方も高血圧のリスクが高いです。
脂肪細胞からさまざまな物質が分泌され、自律神経のバランスが乱れたり、腎臓におけるナトリウムの再吸収が促進してしまうことで血圧が上昇します。
乱れた生活習慣を整え、なるべく若年から高血圧を予防しましょう。
食生活:高血圧引き起こすリスクファクター

高血圧最大の原因は、食生活の乱れ、中でも塩分の過剰摂取です。
ナトリウムには水分を引き込む力があり、血液中のナトリウムが増加すると血液内の水分量が増加して血圧が上昇します。
そのため、高血圧を予防するためには、日頃から塩分摂取量に気を使う必要があります。
2017年に実施された「国民健康・栄養調査」によると、1日あたりの食塩摂取量は男性で10.8g、女性で9.1gでしたが、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、今後5年間での目標値を男性7.5g/日未満、女性6.5g/日未満と設定しています。
実生活に置き換えると、これがどれだけ難しいかわかります。
例えば、袋タイプの焼きそばの塩分は約3.5g、牛丼は約5.3g、ラーメンに至っては5.5〜8.0gとされており、1食で1日の上限を超えてしまう可能性もあります。
最近ではどの食事にも塩分含有量が記載されているため、これを機にぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
また、野菜に含まれるカリウムはナトリウムを体外に排出する作用があるため、野菜の摂取不足も体内にナトリウムが貯留し、高血圧の原因となります。
高血圧を予防するために、野菜や果物の摂取も意識しましょう。
遺伝:遺伝的なリスクファクターの役割
これまで高血圧は、生活習慣などの環境要因と、親や祖父母からの遺伝要因の両方が関与していると考えられていましたが、具体的な研究結果には乏しいのが実情でした。
しかし、近年ではゲノム解析の技術が飛躍的な向上を遂げ、高血圧の発症には環境要因のみならず、遺伝的要因が3〜4割程度関与していることが知られています。
実際に、原因となる遺伝子も複数特定されており、遺伝的要因の関与も明らかとなりました。
ちなみに、両親の両方が高血圧の場合は約50%、片方が高血圧の場合は約30%が高血圧を罹患すると考えられています。
年齢:年齢がリスクファクターとしてどう作用するか
加齢とともに血管の弾力性は失われていくため、血管壁にかかる圧も高まり高血圧に罹患しやすくなります。
また、体動の低下や自律神経のバランス低下などの要因も、加齢によって高血圧となる原因です。
実際に、令和元年に実施された「国民健康・栄養調査」では、血圧の異常を指摘される年代としては50代がもっとも多く、降圧薬を内服している年齢層は50〜70代で多いと報告されています。
ストレス:心の健康が血圧に及ぼす影響
身体的・精神的ストレスも、血圧上昇につながるため注意が必要です。
ストレスによって交感神経が刺激されると、ノルアドレナリンなどのカテコラミン が分泌され、血管収縮や心拍数の増加を引き起こし、長期的に高血圧の原因となります。
また、ストレスは副腎皮質を刺激し、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌も促します。
コルチゾールには血糖値の上昇や、腎臓におけるナトリウムの再吸収などの作用があるため、高血圧の原因となります。
このように、ストレスは医学的にも身体に悪影響を与えることが知られており、日常生活から緩和していくことが重要です。
まとめ
今回の記事では、高血圧の原因となるリスクファクターについて解説しました。
高血圧の30〜40%は遺伝的要因が関与し、残りの多くは環境要因が影響します。
環境要因としては、塩分の過剰摂取や野菜不足、運動不足やストレスの蓄積などが挙げられます。
自分自身で高血圧を予防するためにも、高血圧のリスクを把握しておくことが重要です。
一方で、高血圧に対して予防・対策を怠ると、心臓や脳などの重要臓器に重篤な影響を与える可能性があります。
特に、脳梗塞や脳出血などを発症すると、麻痺やしびれなどの不可逆的な神経障害を引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。
現状、脳梗塞や脳出血による神経障害を根治する治療法はないからこそ予防医療が重要視されていますが、近年では再生医療の発達が目覚ましいです。
再生医療によって破壊された神経細胞が再生すれば、麻痺やしびれなどの神経症状が改善する可能性もあり、現在その知見が待たれるところです。
よくあるご質問
どんな生活習慣が高血圧のリスクを高める可能性がありますか?
高血圧のリスクを高める生活習慣としては、運動不足・乱れた食生活・喫煙・身体的、もしくは精神的ストレスの蓄積などが挙げられます。
特に食生活は重要で、過剰な塩分摂取や野菜の摂取不足・過剰なアルコール摂取は高血圧の原因となるため控えるべきです。
年齢と高血圧のリスクはどのように関連していますか?
加齢に伴って血管壁の弾性力が低下し、自律神経のバランスも乱れるため、血管が硬くなり、収縮してしまい高血圧の原因となります。
また、加齢による体動の減少も体内のナトリウム貯留につながるため、高血圧の原因となります。
<参照元>
・厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf
・日本医師会:https://jams.med.or.jp/event/doc/118013.pdf
あわせて読みたい記事:サイレントキラー動脈硬化とは
外部サイトの関連記事:アテローム血栓性脳梗塞とは何か



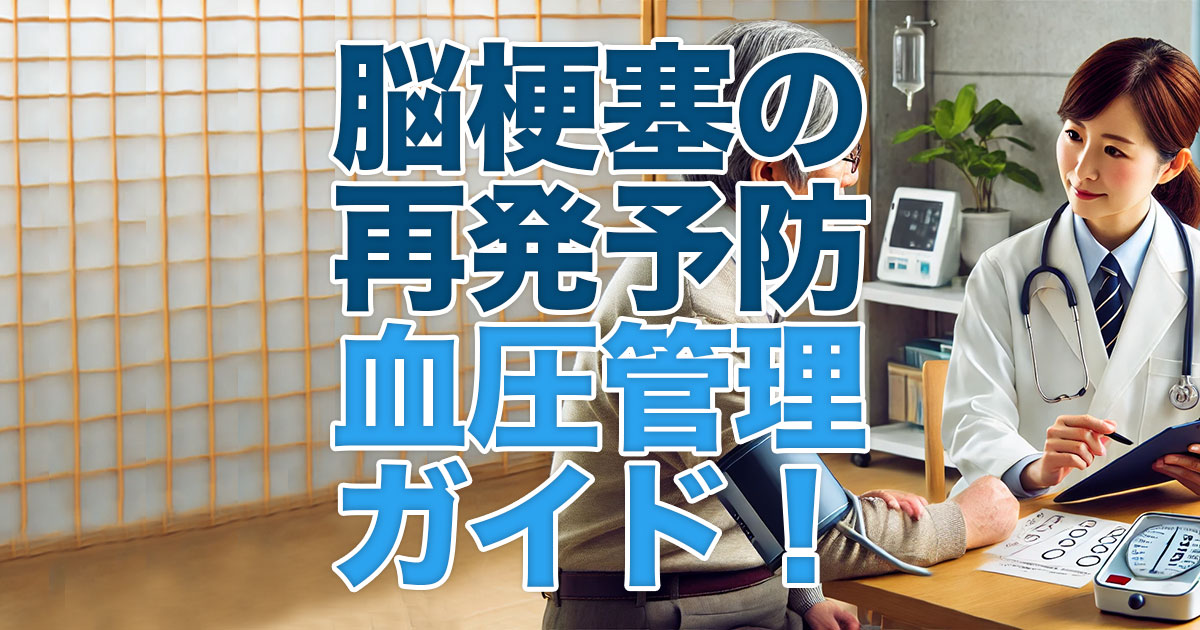
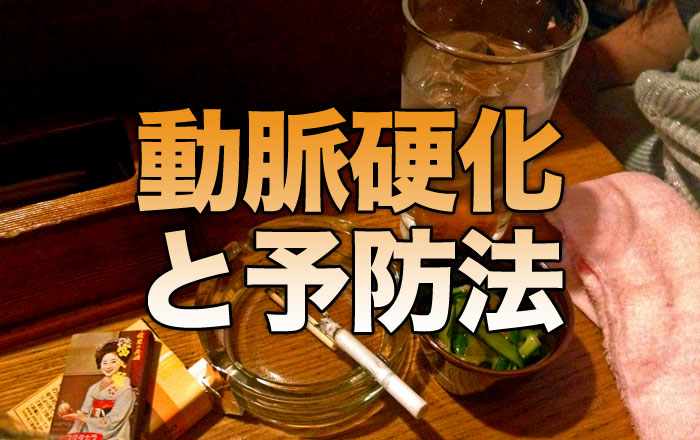












コメント