この記事を読んでわかること
・脳梗塞の後のこの疲れやすさの正体は?
・脳卒中後疲労感の発症率
・脳卒中後疲労感の発症のパターン
脳梗塞の治療のあとなんだか疲れやすい身体になってしまったような気がする。
この記事では、脳梗塞後に疲労感を感じやすくなってしまう症状、脳卒中後疲労感についてその理由や症状についてわかりやすくまとめていきます。
脳梗塞の後のこの疲れやすさの正体は?

特になんとも言えないけれども、脳梗塞の治療の後からどうしても疲れやすさを感じてしまう。
このような症状は英語でPost Stroke Fatigue(PSF)と呼ばれ、日本語に訳すと脳卒中後疲労感となります。
初期の治療がその後の生活や命に関わる脳卒中において、あまり知られてはいない概念かもしれません。
しかしながら、当事者や周りの人たちの生活に大きく関わり、私たちがしっかりと向き合わなくてはいけない問題なのです。
脳卒中後疲労感の発症率
脳卒中後疲労感はどれくらいの人に起こりうるものなのでしょうか?
脳卒中後疲労感の発症率には研究によって大きなバラつきが見られます。
しかしながら、多くの研究で脳卒中後の患者さんの数10%の発症率を報告しているのが現状です。
研究によると30%から70%程がPSFを発症するのではないかとも考えられています。
脳卒中後疲労感の発症機序
脳卒中後疲労感がどのようにして発症するのかのエビデンスも実は十分ではありません。
しかしながら、1つの説として脳卒中の炎症反応が起因しているのではないかと考えられています。
脳卒中により、脳細胞に十分な血液が脳細胞に供給されなくなってしまうと、炎症を誘発するようなサイトカインやケモカインと呼ばれる物質が多量に分泌され、脳内にて炎症が起こり様々な症状が出るのではないかという機序です。
2016年に発表された研究によると脳卒中発症1年後にサイトカインなどが上昇していることなどもこれらのメカニズムを支持するエビデンスではないかと考えられています。
脳卒中後疲労感の発症のパターンは3つ
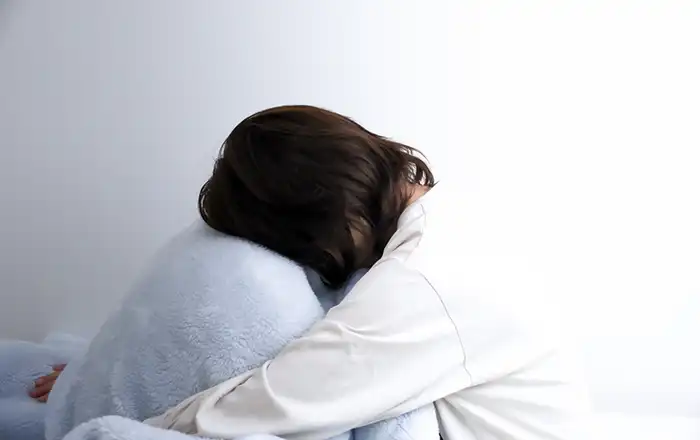
脳卒中後疲労感の発症のパターンは3つに大きく分けられます。
「早期発症タイプ」「発症から持続するタイプ」「晩期発症タイプ」のように発症するタイミングと持続形式によって区分されています。
早期発症タイプ
脳卒中後疲労感の1/3は脳卒中から3ヶ月以内に発症すると考えられてます。
このタイプの特徴としては、脳卒中による脳へダメージを与える生物学的要因が原因とされています。
発症から持続するタイプ
発症早期から晩期に至るまで症状が持続するタイプでは、どのような原因によって疲労感が現れるのかが未だ明確になっていいません。
晩期発症タイプ
脳梗塞から1年程経った後に発症するタイプの疲労感は、うつ病や睡眠障害などの心理的な要因の他にも、社会的な要因などが原因となって引き起こされると考えられています。
脳卒中後疲労感の発症要因は?

それでは脳卒中後疲労感はどのような要因で起きてしまうのでしょうか?
ここでは身体的な要因、心理的な要因、社会的な要因の3つに分けてご紹介します。
身体的な要因
脳卒中の後遺症には麻痺などの運動障害が残ることもあります。
これらの身体運動機能と脳卒中後疲労感の関係性についてもさまざまな報告があり、具体的な見解は示されていません。
例えば、とある研究では、身体的な要因の尺度として、どのくらいの距離を歩くことができるのかを測定した検査結果と脳卒中後疲労感には関係性が見られなかったと結論づけています。
一方で、同じ検査において、身体的尺度と脳卒中後疲労感の関連性を認めるとする報告も存在します。
心理的な要因
脳卒中後疲労感と心理的な要因については未だ明らかな見解は得られていません。
ただ、うつ病や睡眠障害などの精神科疾患などは脳卒中後疲労感に影響を与える可能性があるのではないかとも考えられています。
社会的な背景
脳卒中後疲労感の発症要因には心理的や社会的な背景要因が大きく関わっています。
例えば、高齢者や、独身者や非就業者、失業した人や脳卒中により職場での配置を変更があった人などが研究の報告として挙げられています。
まとめ
この記事では脳卒中後疲労感が脳梗塞の治療のあとなんだか疲れやすい。
その理由や症状についてこの記事ではまとめました。
脳卒中後疲労感の疲労感については最新の文献でもエビデンスは確立しておらず、明確なことは断定することはできません。
しかしながら、身体的、精神的、社会的、それぞれの要因が複雑に絡まりあって生じる症状であるからこそ、周囲の人のサポートが症状緩和の鍵を握る存在なのではないでしょうか?
よくあるご質問
- 脳卒中後疲労感の発症要因は?
- 脳卒中後の疲労感は身体的な要因、心理的な要因、社会的な要因の3つの要因があります。
例えば社会的な要因は、高齢者や、独身者や非就業者、失業した人や脳卒中により職場での配置を変更があった人などが疲労感を感じやすいと言われています。
あわせて読みたい記事:脳出血の治療薬と予防薬の種類
外部サイトの関連記事:脳梗塞後の様々な障害にどう対応できるか



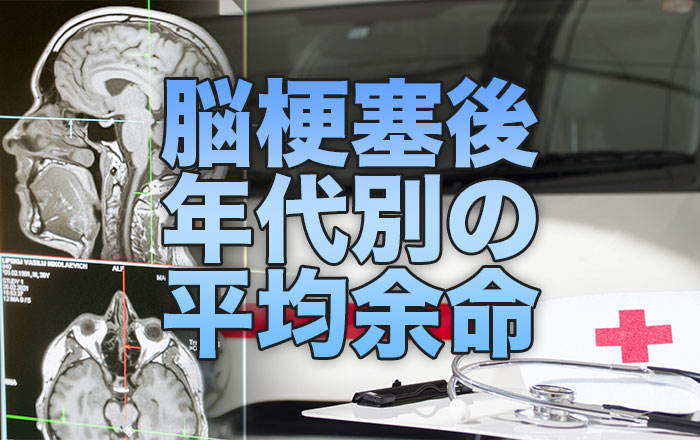

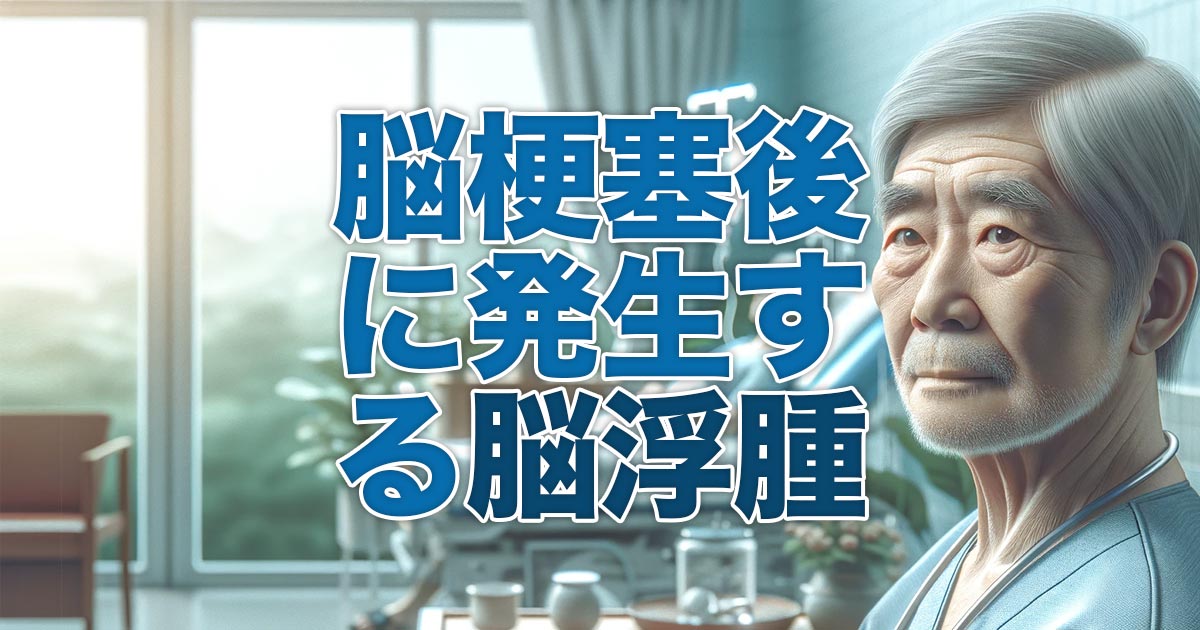












コメント