この記事を読んでわかること
・認知症予防のためのトレーニングとは?
・トレーニングの種類
ここまで医療が発達したにも関わらず、認知症を劇的に改善する特効薬は開発できておらず、現状ではどう治すかよりも、どう予防するかの方が重要です。
近年では様々な認知症の予防策が開発されており、進行する前に早期から適切な対策を行なっておく必要があります。
そこで今回は、認知症予防のためのトレーニング方法に関して詳しく解説していきます。
認知症予防のためのトレーニングとは?
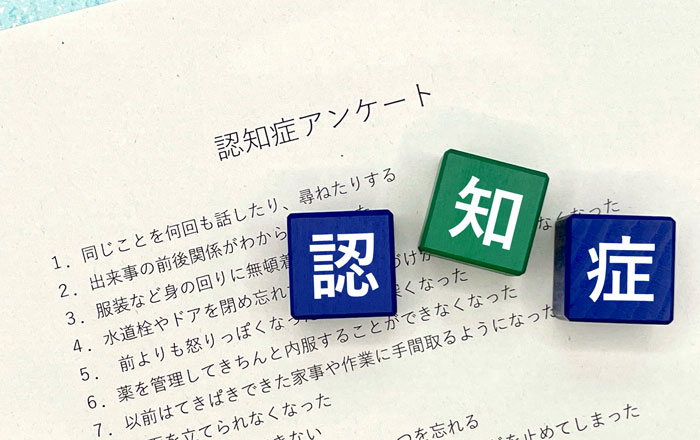
アルツハイマー型をはじめとする認知症は、高齢化社会の進む日本で年々増加傾向にあります。
認知症の基本的な病態は、記憶に関与する神経細胞の変性や萎縮による神経機能の障害です。
これまで認知症に対する多くの治療法が開発されてきましたが、既存の治療薬はこれ以上の進行を食い止めるための薬であり、一度失われた神経機能を回復させるようなものではありません。
つまり、認知症は発症する前にどれほど予防できるかが重要なのです。
そこで、認知症を予防する上では、どういったことがリスクになるかを知っておく必要があります。
過去の多くの研究から、高血圧や糖尿病や高脂血症などの生活習慣病、喫煙、うつ病、肥満、社会交流の乏しさ、知的刺激の乏しさ、活動性の低さなどがリスク因子になることが知られています。
逆に言えば、早期からこれらのリスク因子を避けて、しっかりと対策して生活しておくことで認知症の発症を予防できるわけです。
また最近では、より多くの人がこういった対策に取り組みやすくするために、予防のためのアプリやゲームなども豊富に開発されています。
そこで、発症予防に有効なトレーニング方法をいくつかご紹介します。
運動トレーニング
原始的ですが、運動は認知症予防に非常に有効な手段です。
特に、ウォーキングやジョギング、サイクリング、ヨガ、水泳などの有酸素運動は予防効果が高いと言われています。
有酸素運動を行うことで、社会交流や活動性が向上し、生活習慣病や肥満の予防にもつながるため、多くの側面で予防効果が期待できます。
また、筋力トレーニングや短距離走などの無酸素運動も予防効果があると報告されているため、ご自身の身体レベルに見合った運動に取り組むことをオススメします。
脳トレゲーム
脳トレゲームとは脳の運動をゲーム感覚で行えるもので、計算問題や謎解きやパズル、間違い探しなど様々な種類があります。
書店で脳トレ本を購入できますが、最近ではスマートフォンでのアプリで気軽に楽しむこともできます。
是非ご自身の興味の持てるものを探してみてください。
知的運動
知的運動とは、読書やコンピューター作業、趣味や家事、社会活動への参加などを指しています。
上記で記したような脳トレやゲームもこの中に含まれています。
中でも、手指を緻密によく動かすような知的活動は脳に多くの刺激を与えることができるため、予防法として非常に効果的と言われています。
筆者のオススメの知的運動は、一人負けジャンケンです。
右手でグーチョキパーを順番に出していき、左手は常に右手に負けるようにグーチョキパーを出していき、繰り返す手遊びです。
ある程度慣れたら左右を反転させ、今度は右手が左手に負けるようにします。
コグニサイズ
コグニサイズとは、英語のcognition (認知) とexercise (運動) を組み合わせたcogniciseという造語から来ています。
具体的には、運動によって体の健康を促進させるとともに、脳の活動を活性化させる機会を増やして、認知症の発症を予防する認知症発症予防プログラムのことです。
コグニサイズでは様々な運動方法が推奨されていますが、例えばコグニサイズの1つであるコグニステップでは、両足で立った状態から、
- 1で右足を右横に出し
- 2で右足を元に戻す
- 3で左足を左横に出し
- 4で左足を元に戻す
というステップを1セットとして繰り返します。
これだけではただの運動ですので、それに加えて3の倍数のステップの時に拍手をするという知的運動も行います。
これらの運動により、体と脳の両方を同時に刺激することができるため、非常に有効な予防策として期待されています。
まとめ
今回は認知症予防のためのトレーニング方法について解説しました。
認知機能の低下は現代の高度な医療を持ってしても不可逆的であり、基本的には治療よりも予防が重要になっています。
そこで最近では、より取り組みやすい、ユニークで多種多様なトレーニング方法が開発されています。
認知症に不安な方は、本書で紹介したようなトレーニング方法を早期から是非実践してみてください。
また、近年では再生医療の発達も目覚ましいです。
再生医療によって損傷した神経細胞が再生すれば、今までは難しかった認知症の治療的側面にも明るい効果が期待できるかもしれません。
よくあるご質問
- 認知症にはどう対策すればいい?
- 認知症はどう治すかよりも、どう予防するかの方が重要です。
認知症を予防する上では、どういったことがリスクになるかを知っておく必要があります。
近年では様々な認知症の予防策が開発されており、進行する前に早期から適切な対策を行なっておく必要があります。 - 認知症予防に有効なトレーニングとは?
- 運動トレーニングは認知症予防に非常に有効な手段です。
また、脳トレゲーム、読書やコンピューター作業、趣味や家事、社会活動への参加も予防法として効果的です。
あわせて読みたい記事:認知機能低下の原因である脳梗塞と血管性認知症の関係
外部サイトの関連記事:感覚障害のリハビリ徹底解説



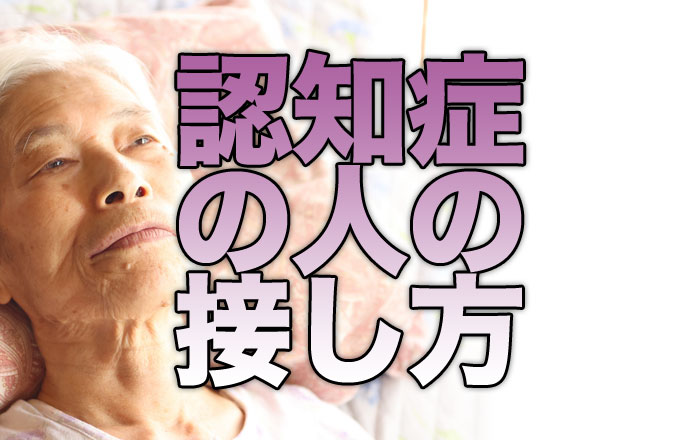












コメント