この記事を読んでわかること
障害年金の制度の基本がわかる。
等級の判断基準がわかる。
障害年金の1級・2級・3級の違いと具体例がわかる。
脳卒中の後遺症で半身麻痺が残った場合、「障害年金を受け取れるのか?」「何級に該当するのか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、障害年金制度の基本から、等級の認定基準、半身麻痺のケース別の等級例、申請時の注意点までを医療的視点からわかりやすく解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
障害年金とは?制度の基本をわかりやすく解説

脳卒中の後遺症が残ると、それまでの生活が送れなくなるのではと不安に思われる方もいるのではないでしょうか。
実際に、脳卒中患者(18-65歳)の予後を調べた調査データがあります。
この調査では、脳卒中を発症してから3ヶ月後のmodified Ranking Scale(mRS)を調べています。
なお、mRSは、脳出血や脳梗塞などの脳卒中(脳血管障害)、パーキンソン病などの神経疾患といった神経運動機能に影響を与える疾患の重症度を評価するためのスケールです。
mRSは0〜6の7段階に分けられます。
調査によると、1(症状はあるが、日常の勤めや活動は行える)が最も多く、0(全く症候がない)が次点となっています。
その次に2(軽度の障害:発症以前から行っていた仕事や活動に制限はあるが、日常生活は自立している状態)が続きます。
しかし、その次には4(中等度や重度の障害:通常の歩行や食事、身だしなみの維持、トイレなどには介助が必要となるが、持続的な介護は不要)の状態が多いという結果でした。
軽度の障害程度は約7割ですが、残りの約3割は何らかの介助が必要な状態になってしまうということになります。
障害年金は、脳卒中を含めた何らかの怪我や病気で、仕事や生活が制限を受けてしまう状態になった場合に、生活を支えるために支給されるものです。
障害年金の対象となる病気としては、以下のようなものがあります。
- 聴覚障害、網膜色素変性症
- がん、脳梗塞、心筋梗塞、糖尿病、慢性腎不全、人工透析など
- 人工肛門、手足切断、リウマチ、事故によるけがなど
- うつ病、統合失調症など
障害年金を受ける条件としては、公的年金への加入・保険料納付済期間などを有する、また、障害の状態が一定の程度になっていることなどがあります。
障害年金は、加入している医療保険によって受給するものが変わります。
自営業者など、国民年金の被保険者には「障害基礎年金」、会社員など厚生年金の被保険者には「障害厚生年金」が支給されます。
厚生年金の被保険者は国民年金にも原則加入していることになるので、後述する障害の程度が障害等級1、2級の場合には障害基礎年金も支給されます。
半身麻痺は何級に該当するのか?等級の判断基準
障害年金が支給される際に重要になってくるのが「障害の程度」です。
この障害の程度は、2つの法律によって定められています。
「国民年金法施行令」と「厚生年金保険法施行令」です。
障害等級は1から3級に分けられ、数字が小さいほど障害の程度が高くなります。
身体の障害の程度がどの程度なのか、具体的には日常生活や仕事にどの程度の影響を与えるのかによって区分されています。
障害年金の1級・2級・3級の違いと具体例

1級・2級は国民年金法によって定められ、国民年金加入者にも厚生年金加入者にも支払われます。
3級は厚生年金保険法によって定められ、原則厚生年金保険加入者のみに支払われます。
この等級は、以下のようになっています。
1級
常に介助が必要な状態です。
例えば、言葉を発することも困難で、食事や排泄など全介助が必要な状態となります。
2級
日常生活に著しい制限がある状態です。
例えば、歩行はできるが、入浴や着替えなどに毎日介助が必要です。
3級
労働に著しい制限がある状態です。
例えば、片手や片脚の麻痺で力仕事が難しく、軽作業に制限が出る状態です。
それでは、実際に半身麻痺の症状がある場合、障害年金の等級としてどのように認定されるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
片側の上下肢に麻痺があり、歩行や衣服の着脱に介助が必要な場合は「2級」に該当する可能性があります。
片側の上肢の麻痺により、細かい手作業や日常生活の一部に制限がある場合は「3級」の対象となることがあります。
一方で、麻痺の程度が軽く、日常生活や仕事にほとんど支障がない場合には、等級に該当しないこともあります。
このように、同じ「半身麻痺」でも、障害の程度や日常生活への影響によって、認定される等級が異なります。
まとめ
今回の記事では、障害年金がどのような制度なのかについて、例を挙げながら解説しました。
障害年金の申請について不安がある方は、社会保険労務士や年金事務所などの専門窓口に相談することをおすすめします。
脳卒中後には、多くの方が何らかの後遺症を抱えることになってしまいます。
後遺症の治療には、リハビリテーションを併用することが重要です。
ニューロテックや脳梗塞脊髄損傷クリニックなどでは、脳卒中・脊髄損傷を専門として、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。
リニューロ®では、同時刺激×神経再生医療®、骨髄由来間葉系幹細胞を用いて狙った脳や脊髄の治る力を高めた上で、神経再生リハビリ®を行うことで神経障害の軽減を目指しています。
ご興味がある方は、ぜひ一度当院までご相談くださいね。
よくあるご質問
- 半身不随は障害何級に認定されますか?
- 半身不随(半身麻痺)の程度によって異なりますが、日常生活に常時介助が必要な場合は1級、歩行や着替えなどに介助が必要な場合は2級、仕事に制限がある程度の場合は3級に認定される可能性があります。
- 障害年金の支給の基準は?
- 障害年金は、公的年金制度に一定期間加入していること、保険料を納付していること、そして障害が等級に該当する重さであることが主な支給基準となります。
認定は診断書や日常生活の状況に基づいて判断されます。
<参照元>
(1):図表1-2-6 脳卒中患者(18-65歳)の予後|厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/18/backdata/01-01-02-06.html
(2):障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病など内部疾患のかたも対象です | 政府広報オンライン:https://www.gov-online.go.jp/article/201201/entry-7663.html
(3):障害等級表|日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html
あわせて読みたい記事:高次脳機能障害者が受けられる社会支援と取得できる手帳
外部サイトの関連記事:脳梗塞後の様々な障害にどう対応できるか



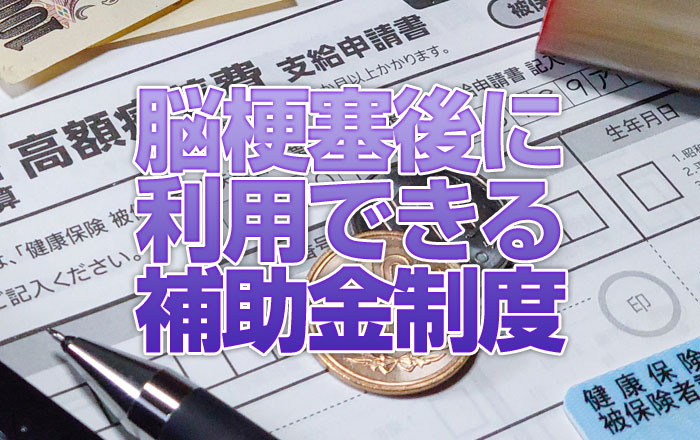













コメント