この記事を読んでわかること
高血圧性脳出血を防ぐための食生活のポイントがわかる。
ストレス管理で脳出血リスクを軽減する方法がわかる。
血圧をコントロールする運動習慣がわかる。
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって起こる認知症の一種です。
本記事では、アルツハイマー型認知症との違いや、脳の損傷部位ごとの症状、感情や注意力、遂行機能への影響についてわかりやすく解説しています。
脳卒中後の認知症に不安を感じている方やご家族は、ぜひ参考にしてみてください。
高血圧性脳出血を防ぐための食生活のポイント

脳出血は、脳の血管が破れる病気のことです。
脳内出血と呼ばれることもあります。
脳梗塞と脳出血、くも膜下出血とともに脳卒中と呼ばれています。
脳出血の原因としては、高血圧や脳アミロイド血管症、脳動静脈奇形などがあります。
その中でも、高血圧は自分自身でも生活に気をつけることでコントロールできる場合があります。
なお、日本では高血圧に起因する脳心血管病死亡者数は年間約10万人と推定されており、脳血管病死亡の要因として歳代とされています。
高血圧をコントロールするためには、食塩の摂取量に気をつけることが大切です。
高血圧の方の治療の一環としての減塩目標は、1日当たり6g未満の食塩摂取が望ましいです。
一方で、日本人は元々食塩を多くとりがちな習慣があります。
それを踏まえ、健康日本21(第三次)では、20歳以上の男女の食塩摂取量の目標値は1日あたり7.0gとされています。
そして、高血圧治療ガイドライン2019年版によると、生活習慣の修正項目の食事については以下のように進められています。
- 食塩制限
- 野菜・果物の積極的摂取
それぞれについて述べていきましょう。
食塩制限
高血圧の方は6g/日以下、それ以外の方は7g以下を目指しましょう。
減塩のためのコツとしては、まずは塩味が薄い食事に慣れることがあります。
そのために、醤油や食塩などの調味料を減らし、素材そのものの味を楽しみましょう。
最初は薄すぎると感じるかもしれませんが、慣れてきます。
そして、食塩が多く含まれる漬物や汁物の量と回数を減らすようにしましょう。
「減塩みそ」や「減塩しょうゆ」などを使うのもよいでしょう。
また、加工食品のパッケージに表示されている「ナトリウム」や「食塩相当量」をチェックする習慣をつけるのもおすすめです。
そばやうどん、ラーメンなどの汁は残しましょう。
ハムやベーコン、ウインナー、かまぼこなどの加工品も塩分が多めのことがありますので注意しましょう。
さらに、レモンやカボスなどの酸味や、胡椒や七味唐辛子などのスパイスも味に広がりを与えてくれます。
野菜・果物の積極的摂取
野菜や果物には、血圧を下げる効果があるカリウムが豊富に含まれています。
野菜は小鉢で1日6杯くらいとれるとよいですね。
果物は、みかんなら2個くらいを目安にとるようにしましょう。
ただし、カリウム制限をしている腎機能が低下している方は、野菜や果物のとりすぎはすすめられません。
また、糖尿病がある方では果物のとりすぎには注意しましょう。
1日80kcalくらいにとどめましょう。
血圧をコントロールする運動習慣とは?
運動は、高血圧の患者さんたちの収縮期血圧(高い方の血圧)を2-5mmHg、拡張期血圧(低い方の血圧)を1-4mmHg下げることが期待できると報告されています。
早歩きやステップ運動、スロージョギング、ランニングのような有酸素持久性動的運動がすすめられています。
運動の強度は、ややきつい程度がよいでしょう。
なお、WHOによるガイドラインによると、成人の場合は有酸素運動を週150〜300分、またはきつい有酸素運動を75〜100分行うことがすすめられています。
ただし、急激な運動や過度な筋トレはかえって血圧を上げてしまうこともあるため、医師と相談しながら始めましょう。
ストレス管理で脳出血リスクを軽減する方法
ストレス管理も、脳出血リスクを下げることに対して重要です。
最近の研究によると、心理的・社会的ストレスによって高血圧発症が2倍以上高まることが報告されています。
また、高血圧の患者さんは、正常な血圧の方に比べて2倍以上のストレスにさらされていたとのことです。
ストレス管理の方法としては、エビデンスは強くはないものの、ヨガや瞑想、バイオフィードバックなどの有効性が示唆されています。
例えば、毎朝5分間の深呼吸や、夜寝る前のストレッチ、散歩など、日常生活に取り入れやすいストレス軽減法もあります。
テレビやSNSから離れる「デジタルデトックス」も効果的な場合があります。
まとめ
高血圧性脳出血を防ぐためには、毎日の生活習慣の見直しが重要です。
特に、減塩・野菜や果物の摂取・適度な運動・ストレス管理を意識することで、血圧をコントロールし、脳出血のリスクを大きく下げることが期待できます。
一方で、すでに脳卒中を経験された方や、神経障害が残っている方には、回復に向けた選択肢として再生医療の取り組みも注目されています。
たとえば、ニューロテック®では「神経障害は治るを当たり前にする」ことを目指し、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療「リニューロ®」を提供しています。
リニューロ®では、骨髄由来間葉系幹細胞と同時刺激(磁気刺激・電気刺激)を組み合わせた治療や、神経再生リハビリ®(川平法®など)を通じて、損傷した神経回路の再構築を促し、神経機能の回復をサポートしています。
この記事をきっかけに、ご自身の予防・改善に向けた一歩を踏み出していただければ幸いです。
よくあるご質問
- 脳梗塞を悪化させないためにはどうしたらいいですか?
- 再発や悪化を防ぐためには、高血圧・高血糖・脂質異常のコントロールが重要です。
減塩や適度な運動、禁煙などの生活習慣の見直しに加え、医師の指示に従って薬を継続することが大切です。 - 脳出血の原因となる生活習慣は?
- もっとも大きな原因は高血圧です。
その背景には塩分の多い食事、運動不足、過度な飲酒、喫煙、ストレスの蓄積などが関係しています。
日頃から生活習慣を整えることが予防につながります。
<参照元>
(1):脳卒中|病気について|循環器病について知る|患者の皆様へ:https://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/knowledge/disease/stroke-2/
(2):高血圧治療ガイドライン 2019(JSH2019)作成委員会:https://www.jpnsh.jp/data/jsh2019/JSH2019_noprint.pdf
(3):健康日本 21(第三次)推進のための説明資料 p30:https://www.mhlw.go.jp/content/001426890.pdf
(4):食事療法について|栄養・食事について|循環器病について知る|患者の皆様へ|国立循環器病研究センター:https://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/knowledge/diet/diet02/
(5):「食事バランスガイド」について 農林水産省:https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/
(6):身体活動および座位行動に関する ガイドライン WHO:https://www.nibn.go.jp/eiken/info/pdf/WHO_undo_guideline2020.pdf
・脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕:https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2023.pdf
あわせて読みたい記事:血管年齢が脳梗塞や心筋梗塞に影響を与える機序
小脳出血を引き起こす原因と背後にある機序は
外部サイトの関連記事:脳出血を予防するための高血圧対策と健康習慣




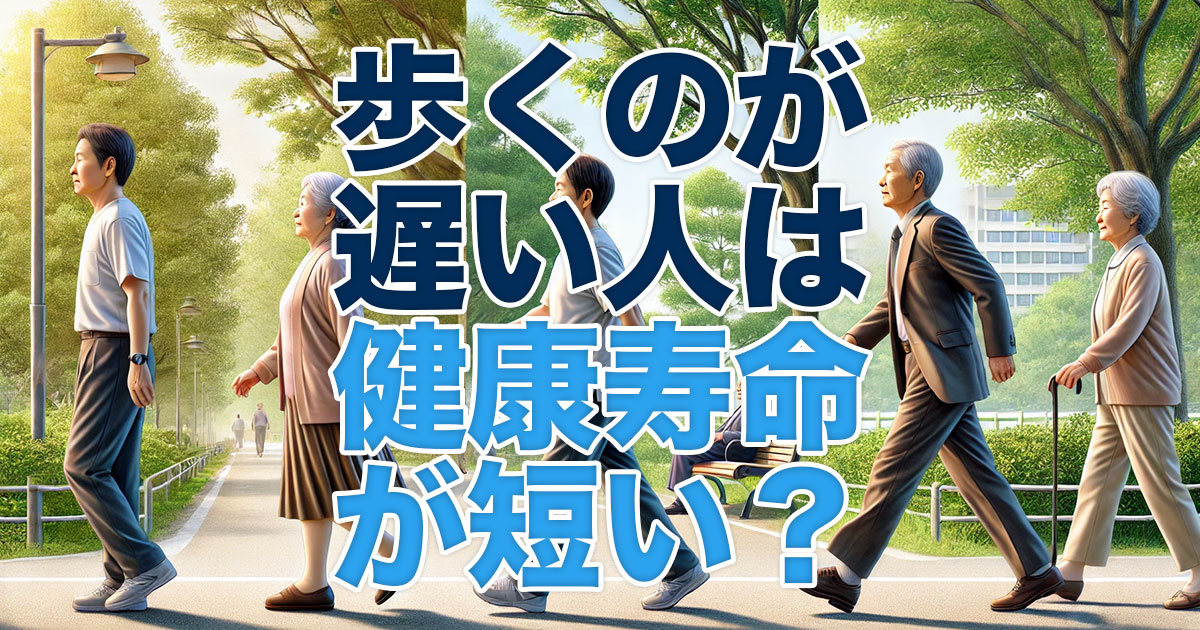












コメント