この記事を読んでわかること
・心筋梗塞の原因や症状がわかる
・脳梗塞の原因や症状がわかる
・心筋梗塞と脳梗塞の共通の予防法がわかる
心筋梗塞と脳梗塞はどちらも血管が閉塞することで臓器の機能が障害される病気であり、どちらも重要な臓器のため、命に関わる危険性もあります。
主な原因はともに動脈硬化であり、普段の生活習慣に注意することでどちらの疾患も同時に予防できます。
そこで、この記事では心筋梗塞と脳梗塞の違いや共通点、予防法について詳しく解説します。
心筋梗塞の原因と症状

心筋梗塞とはその名の通り、心臓を栄養する冠動脈が血栓やプラークで閉塞し、心筋への酸素や栄養の供給が行えなくなることで心筋が壊死する病気です。
主な原因は動脈硬化であり、高血圧や糖尿病、高脂血症などの生活習慣病が長期に渡ることで生じます。
なぜ動脈硬化が起こるのでしょうか??
まず高い血圧に血管が耐えるために、動脈は肥厚して硬くなっていきます。
それによって血管内皮細胞には細かなキズができ、そのキズから血液中を流れるLDL-コレステロールが血管壁内に入り込むことで、血管壁が脆くなって動脈硬化となるメカニズムです。
動脈硬化が進行すれば血管壁内はさらに狭くなり、それは心臓を栄養する血管である冠動脈にも同様の変化をきたします。
心臓は全身に血液を送るポンプのような臓器ですが、心臓から駆出された新鮮な動脈血はまず最初に冠動脈に流入し、心筋を最優先で栄養するようにできています。
そのため、この冠動脈の内腔が狭くなると心筋に十分な酸素や栄養を供給できなくなり、心筋梗塞を発症するわけです。
その他にも、医原性・不整脈・空気塞栓など、さまざまな原因が挙げられます。
発症すれば心筋はすぐに壊死してしまい、ポンプとしての機能を果たせなくなるため、全身への血液供給がままならなくなり、死に至る病です。
実際に、心筋梗塞はがんに次いで日本人の死因第2位であり、病院で治療を受けた方でも5〜10%は救命できない事が報告されています。
心筋梗塞の主な初期症状は下記の通りです。
- 突然の胸を締め付けられるような強い痛み
- 胸部圧迫感・不快感
- 肩や歯への放散痛
- 動悸
- 冷や汗
- 嘔気・嘔吐
- 呼吸困難感
狭心症という病気でも同様の症状をきたしますが、狭心症の場合は冠動脈が閉塞する一歩手前の、冠動脈が狭い状態であるため、安静を保てば心臓での酸素消費量が減って症状も改善します。
一方で、心筋梗塞の場合はすでに物理的に閉塞しているため、安静の有無に関わらず症状が継続します。
脳梗塞の原因と症状
心筋梗塞が冠動脈の閉塞であるのと同様に、脳梗塞とは脳を栄養する血管が閉塞する病気です。
脳も心臓と同じで血液からの酸素供給が途絶えるとすぐに壊死してしまうため、危険な病気です。
梗塞する部位によって出現する症状はさまざまですが、主に麻痺やしびれ・嘔気嘔吐・頭痛・嚥下障害・構音障害などの神経症状が出現し、梗塞範囲が広いと意識障害や呼吸停止などを招きます。
脳梗塞はその原因によって3つに分類できます。
- ラクナ梗塞
- アテローム性血栓性脳梗塞
- 心原性脳梗塞
上記のうち、ラクナ梗塞とアテローム性血栓性脳梗塞の原因は、心筋梗塞と同様、主に動脈硬化です。
動脈硬化によって血管が閉塞し、もともと細い脳深部の動脈が閉塞してしまう脳梗塞をラクナ梗塞と言います。
ラクナ梗塞と違い、血管壁に形成されたアテロームと呼ばれるコブが脳を栄養する比較的太い動脈を閉塞させた場合はアテローム性血栓性脳梗塞となります。
一方で、ラクナ梗塞やアテローム性血栓性脳梗塞とは全く異なる機序で生じる脳梗塞が心原性脳梗塞です。
心原性脳梗塞とは、心房細動などの不整脈などが原因で心臓内に血栓が形成され、その血栓が心拍動とともに脳の血管に拍出されて閉塞させてしまう病気です。
つまり、あくまで原因は脳の血管というよりも心臓にあります。
代表例は心房細動などの不整脈ですが、その他にも人工弁・医原性・重度な心不全などによって血栓形成リスクが上がります。
共通のリスク要因と予防方法
両者に共通しているリスクは下記の2点です。
- ともに非常に酸素需要の高い臓器であり虚血に弱い
- 動脈硬化が主な原因となりうる
先述したように、心筋梗塞・脳梗塞ともに動脈硬化が主な原因です。
また、心臓や脳は起きているときはもちろん、睡眠中でも常に稼働している臓器のため、非常に多くの酸素や栄養を消費する臓器であり、その分酸素不足に弱い臓器とも言えます。
そのため、常に多くの酸素を供給できるよう、動脈硬化の原因となる高血圧や糖尿病・高脂血症などの生活習慣病を予防することが重要です。
規則正しい食生活・睡眠・定期的な運動を日常生活に取り入れるといいでしょう。
まとめ
今回の記事では、 心筋梗塞と脳梗塞の違いと共通点について詳しく解説しました。
心臓と脳はどちらも一度障害されると再生する能力が低い臓器であり、なかなか機能を改善・再生させることは困難です。
そのため予防が重要であり、どちらも発症予防には普段の生活習慣が重要で、食事や運動に気を使う必要があります。
一方で、最近では再生能力の低い心臓や脳に対する再生医療も盛んです。
ニューロテックメディカルでは、「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んで、脊髄や神経の治る力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。
神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「同時刺激×神経再生医療Ⓡ」によって、これまで改善の困難であった脳梗塞後遺症の改善が期待できます。
よくあるご質問
- 心筋梗塞は脳に障害をもたらしますか?
- 心臓は脳をはじめとする全身の臓器に血液を供給する臓器であるため、心筋梗塞によって血液供給が低下すると、脳への血流も低下します。
脳は虚血に弱い臓器のため、脳が障害される可能性も高いです。 - 脳梗塞と心筋梗塞 どっちが多い?
- 日本人の場合、脳梗塞と心筋梗塞では脳梗塞の方が発症者は多いです。
国内で実施されたJPHC Stadyによれば、心筋梗塞と脳卒中の発症率を比べたところ、心筋梗塞に比べて脳卒中の方が、男性で3.7倍、女性では9.6倍も高いという結果でした。
<参照元>
急性心筋梗塞|国立循環器病研究センター
https://www.ncvc.go.jp/coronary2/disease/acute_myocardial/index.html
特集:必要エネルギー量の算出法と投与の実際|J STAGE
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjspen/24/5/24_5_1013/_pdf
心筋梗塞と脳卒中の死亡率と発症率の関連について|がん国立研究センター
https://epi.ncc.go.jp/
あわせて読みたい記事:脳梗塞の性差とその原因
外部サイトの関連記事:脳梗塞発症の年代別ピークと予防策



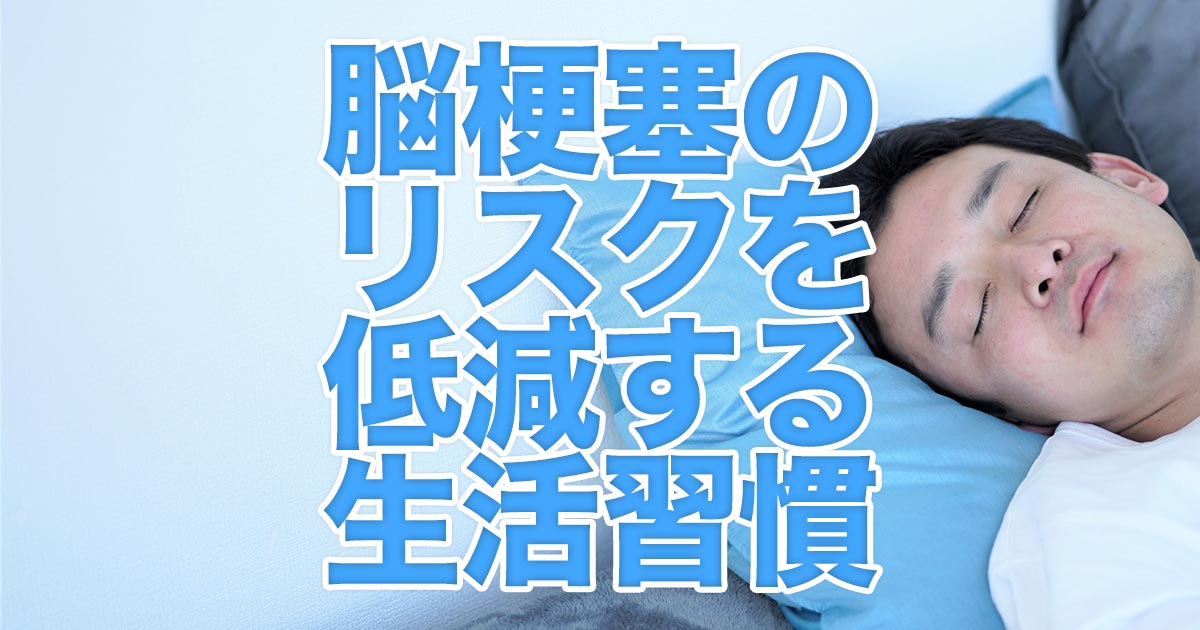
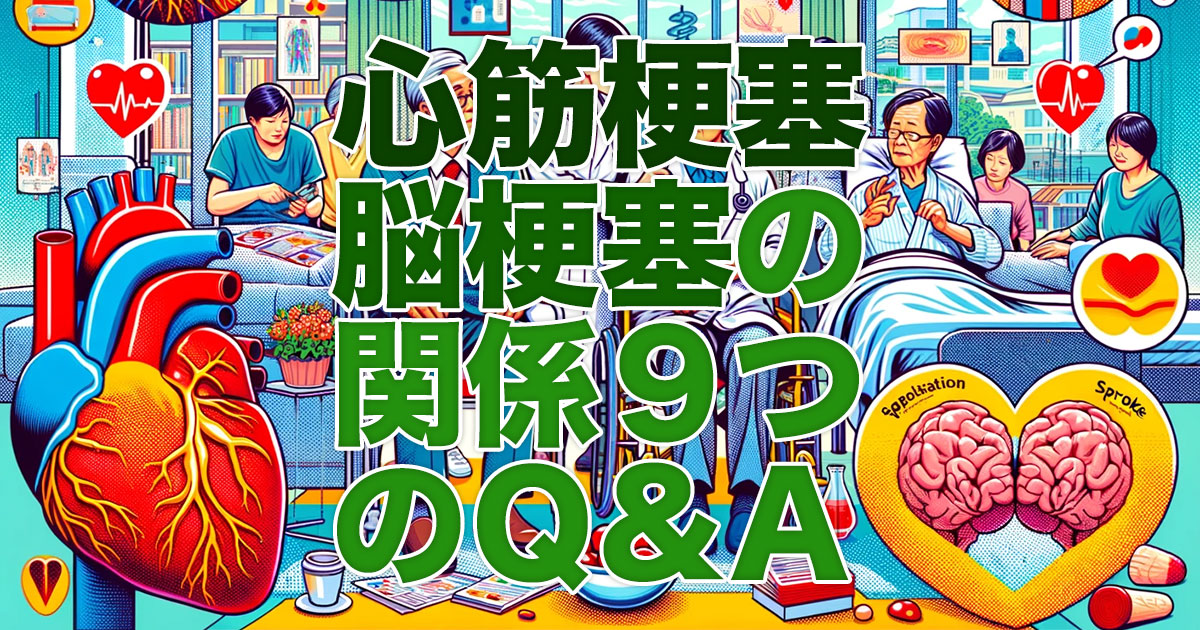
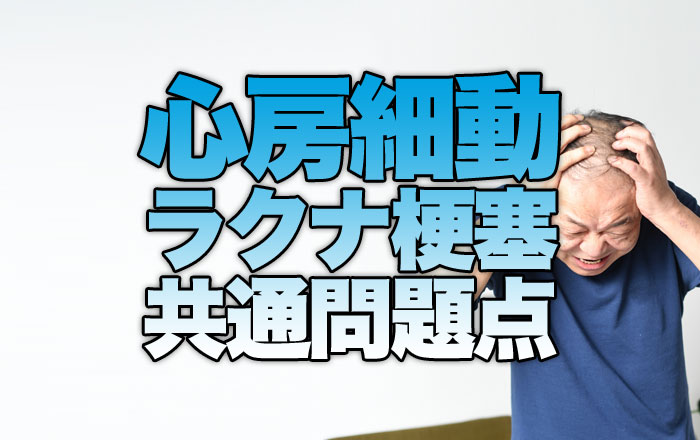












コメント