この記事を読んでわかること
・交通事故などに伴う脳出血のメカニズムがわかる
・ストレスと脳出血の相関関係がわかる
・脳出血のリスクを上げる薬剤についてわかる
脳出血は通常、高血圧や糖尿病によって生じた動脈硬化に伴って発症する病気ですが、実はほかにもさまざまな外的要因で発症リスクが増加します。
特に、交通事故や転倒転落、ストレスや過剰な運動、薬剤性などが外的要因として代表的です。
そこでこの記事では、外的要因が関与する脳出血の原因について詳しく解説します。
頭部外傷が脳内出血を引き起こす仕組み

転倒や転落・交通事故・スポーツによるハードコンタクトなどが原因で頭部に強い衝撃が加わると、脳表層や脳内を走行する血管の一部が破綻し、出血を引き起こしますが、どの部分の血管が損傷するかで、病名や脳に与える影響、予後なども異なります。
例えば、一番イメージしやすいのはたんこぶです。
頭をぶつけた時にできるたんこぶは頭部の皮膚表層の血管の破綻による皮下血腫であり、頭蓋骨に守られた脳には特に影響しないため、実際に重症化することはありません。
同様に、脳の表面を守る硬膜の外側にある血管が破綻した場合は硬膜外血腫と呼び、血腫が蓄積していても硬い硬膜が脳を守るため、脳そのものは障害されにくい傾向にあります。
一方で、硬膜とくも膜の間の血管が破綻する硬膜下血腫や、くも膜のさらに内側で出血するくも膜下出血、脳深部で出血する脳内出血などを引き起こす場合、形成された血腫が直接的に脳を圧迫するため、予後が悪化しやすく注意が必要です。
また興味深いことに、一回の頭部外傷によって不運にも複数箇所から出血することもあります。
例えば、交通事故で激しく右前頭部を打ち付けた場合、右前頭部には脳挫傷とともに脳内出血を引き起こす可能性があります。
またその際の衝撃で脳が揺られ、反対側の頭蓋骨に叩きつけられることで、この場合、左後頭部にも出血を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。
この際、最初に負った右前頭部の外傷を「クー外傷」、二次的に負った左後頭部の外傷を「コントラクー外傷」と呼びます。
(参照サイト:頭部外傷とは|慶應義塾大学病院 医療・健康情報サイト)
このように、実際に事故や転倒・転落に見舞われた際、脳のどの部位の血管が破綻するかで予後や症状も異なり、脳内部の損傷の場合はより早期の対応が求められます。
激しい運動やストレスが血管に与える影響
脳の出血で注意すべきは外傷だけではありません。
実は激しい運動や過剰なストレスも、脳の血管に悪影響を与え、出血するリスクが増加することが知られています。
人は激しい運動を行う時やストレスを感じた時、身体がこれらの状況の変化に追いつけるよう、交感神経を活性化させます。
例えば、激しい運動を行なう時は全身の筋肉にたくさんの酸素を供給する必要があるため、交感神経が活性化することで心拍数や心筋収縮力を増強し、より多くの酸素を供給するわけです。
また、過剰なストレスを感じた時もその場から緊急で逃げ出すために、動物的感覚で交感神経が活性化されます。
その際、交感神経が手のひらのアポクリン汗腺を刺激するため、手に滲むような冷や汗が生じるのです。
では、持続的な交感神経の活性化は血管にどのような影響を与えるのでしょうか?
- 血管平滑筋が収縮して、高血圧に陥る可能性が高まる
- 血糖値の上昇に伴い、糖尿病に陥る可能性が高まる
- LDLコレステロールが増加し、高脂血症に陥る可能性が高まる
これらの反応は全て、脳の血管内皮細胞を損傷し、動脈硬化を進展させる可能性があるため注意が必要です。
動脈硬化が進展すれば血管は従来の弾性を失い、血圧の変動に耐えることができず、破綻する可能性が上がるため、脳出血の発症リスクが増加します。
さらに、損傷した血管内皮細胞からLDLコレステロールが血管壁内に入り込み、蓄積するとアテロームと呼ばれるコブを形成し、脳血管を狭窄させるため、アテローム性血栓性脳梗塞の発症リスクも増加します。
(参照サイト:動脈硬化|厚生労働省)
以上のことより、激しい運動やストレスは血管にさまざまな悪影響を与えるため、適度な負荷の運動やストレス発散を心掛けると良いでしょう。
薬剤使用が脳出血リスクを高めるケース
実は薬剤使用が脳出血リスクを高めるケースもあります。
特に近年では、脳梗塞や心筋梗塞など血管の病気に罹患する方も増え、それに伴い発症や再発予防のために抗凝固薬や抗血小板薬を内服する方も増加しています。
これらの薬は血液をサラサラにして脳梗塞や心筋梗塞の発症を予防する一方、本来であれば自然に止血の得られる微小な出血も止血が得られなくなるため、脳出血リスクを高めることが知られています。
国立循環器病研究センターの研究によれば、抗凝固薬や抗血小板薬の内服で脳出血発症リスクが高まるのはもちろんのこと、特に抗凝固薬の1つであるワルファリン内服者の場合は脳出血発症後の重症化リスクも高まるそうです。
(参照サイト:抗血栓薬内服中の患者が脳出血を発症した場合の重症化リスクを解明|国立循環器病研究センター)
まとめ
今回の記事では、外的要因が関与する脳出血の原因について詳しく解説しました。
脳出血は通常、動脈硬化の進展によって発症する病気ですが、それ以外にも頭部外傷や転倒転落、ストレス、激しい運動、薬剤性など、さまざまな外的要因で発症しうる病気です。
一度発症すれば麻痺やしびれなどの神経学的後遺症を残す可能性があり、また一度後遺症として残ってしまうと、現状ではリハビリテーションが唯一の改善策です。
しかし、後遺症の程度によってはリハビリテーションでも改善することは困難であり、日常生活に大きな支障を与えます。
そこで、近年では新たな治療法として再生医療が大変注目されています。
ニューロテックメディカルでは、「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。
「ニューロテック®」では、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。
また、神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「同時刺激×神経再生医療Ⓡ」によって、これまで改善の困難であった脳出血後の後遺症の改善が期待できます。
よくあるご質問
- 高血圧以外の脳出血の原因は?
- 高血圧以外の脳出血の原因は、抗血小板薬や抗凝固薬などの薬剤性、脳動静脈奇形やもやもや病などの脳血管異常、過度な喫煙や飲酒、交通事故などの高エネルギー外傷など、多岐に渡ります。
- 脳血管疾患の原因は?
- 脳血管疾患の主な原因は動脈硬化です。
高血圧・糖尿病・高脂血症などの生活習慣病や喫煙、肥満などによって生じる動脈硬化によって脳の血管は硬く・脆く変性し、脳梗塞や脳出血を発症しやすくなります。
<参照元>
(1)頭部外傷とは|慶應義塾大学病院 医療・健康情報サイト:
https://kompas.hosp.keio.ac.jp/disease/000276/
(2)動脈硬化|厚生労働省:
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/metabolic/ym-082
(3)抗血栓薬内服中の患者が脳出血を発症した場合の重症化リスクを解明|国立循環器病研究センター:
https://www.ncvc.go.jp/pr/release/pr_44966/
あわせて読みたい記事:脳出血後遺症の程度を知るための基本知識
外部サイトの関連記事:首の後ろの痛みが脳卒中の前兆となる理由



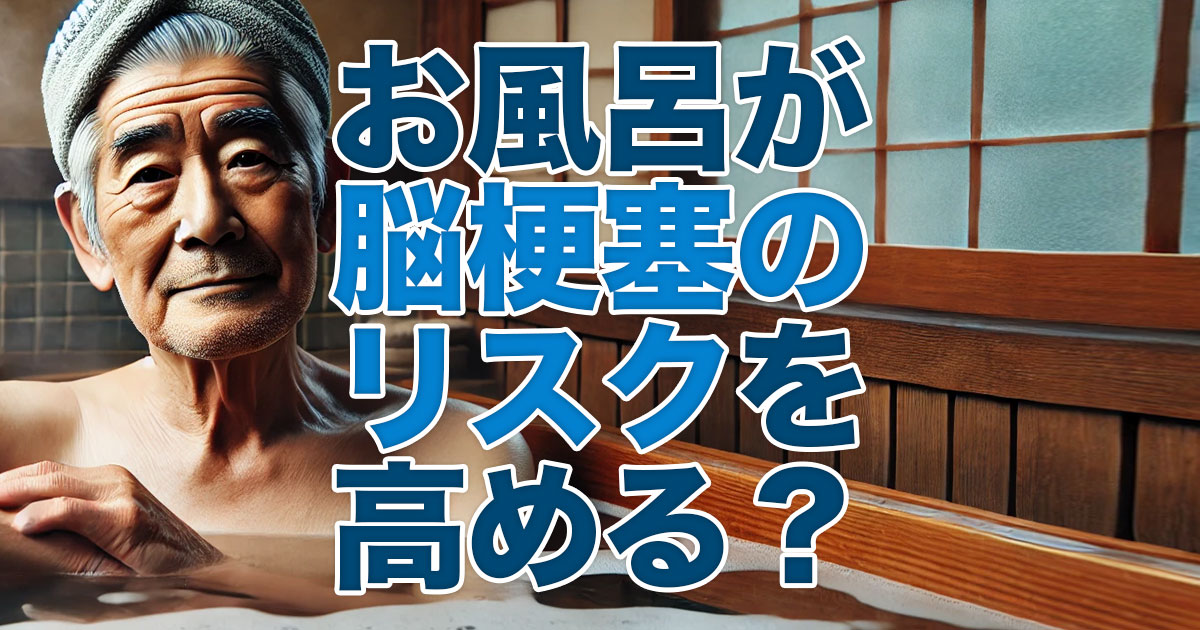
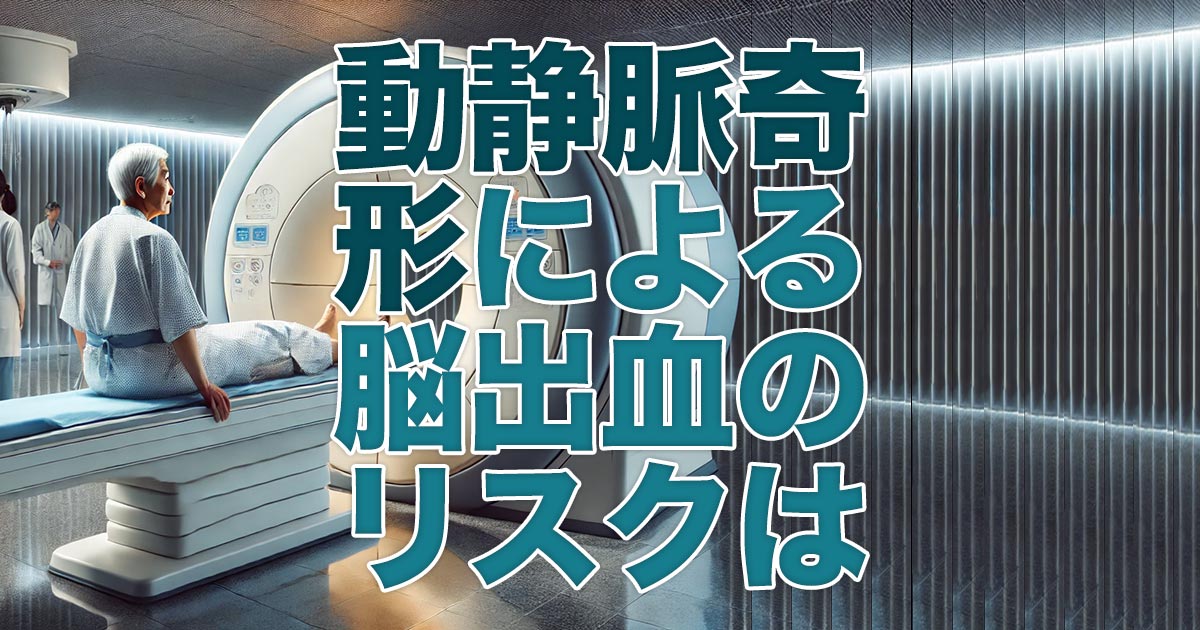












コメント