この記事を読んでわかること
・脊髄が担う情報伝達の仕組みとは?
・脊椎が体全体を支えるための仕組みと負担
・脊髄と脊椎が連携して行う身体の動きの調整
脊髄と脊椎は、体を支える重要な役割があります。
脊髄は脳からの指令を全身に伝えたり、体の感覚を脳に送ったりする神経の通り道で、運動、感覚、自律神経の働きを調整します。
脊椎は、脊髄を守る機能に加えて、体を支えてスムーズな動きを可能にします。
損傷すると、運動や感覚の障害、自律神経不調など、深刻な影響が出る可能性があります。
脊髄が担う情報伝達の仕組みとは?

この記事では脊髄が担う情報伝達の仕組みとは?について解説します。
脊髄は、脳と全身をつなぎ、情報を伝達する働きをしています。
脊髄は中枢神経系の一部で、感覚神経と運動神経を通じて情報をやり取りします。
感覚情報の伝達では、皮膚、筋肉、内臓などからの刺激が感覚神経を通って脊髄に送られ、そこから脳へと伝えられます。
この仕組みにより、痛み、温度などの変化を感じ、脳が適切な反応を指示することができます。
(参照サイト:脊髄後角神経回路による体性感覚の情報処理|生化学2016;88:pp229-232)
一方、運動情報の伝達では、脳からの指令が脊髄を経由して運動神経に伝わり、筋肉を動かします。
これにより、手足を細かくスムーズに動かすことができます。
(参照サイト:皮質脊髄路の基礎知識|脊髄外科2015;29:pp267-278)
また、脊髄には反射機能もあり、脳を介さずに素早く反応する仕組みがあります。
例えば、熱いものに触れた時に反射的に手を引くことができます。
さらに、脊髄は自律神経の調整にも関係しており、内臓の働き、血圧、呼吸などをコントロールしています。
これらの情報伝達が正しく行われることで、体は環境の変化に適応することができます。
脊椎が体全体を支えるための仕組みと負担
この記事では、脊椎が体全体を支えるための仕組みと負担について解説します。
脊椎は、体全体を支えるために、骨・関節・筋肉・椎間板が連携して働いています。
脊椎は、頸椎・胸椎・腰椎・仙椎・尾椎の五つの部位に分かれます。
頸椎は頭を支え、胸椎は肋骨と連携して胸郭を形成します。
腰椎は体を支える重要な部分で、仙椎と尾椎は骨盤とつながり、体の安定を保ちます。
脊椎にかかる体重をうまく分散するために、椎間板はクッションの役割を果たし、衝撃を吸収しています。
また、関節や靭帯が脊椎の動きを調整し、姿勢を安定化します。
さらに、脊柱起立筋や腹筋などの筋肉が脊椎をしっかり支えることで、正しい姿勢を維持し、負担を軽減しています。
しかし、脊椎には日常の動作による負担が常にかかっています。
長時間同じ姿勢を続けたり、無理な動きや急激な動きをしたりすると、椎間板や筋肉に負担がかかり、腰痛や猫背の原因となります。
加齢によって椎間板がすり減ると、衝撃を吸収する力が弱まるため、脊椎への負担が増えます。
さらに、骨粗鬆症などで骨がもろくなると、脊椎が体を支えきれなくなり、圧迫骨折のリスクが高まります。
脊髄と脊椎が連携して行う身体の動きの調整
この記事では脊髄と脊椎が連携して行う身体の動きの調整について解説します。
脊髄と脊椎は連携して、身体の動きがスムーズになるように調整しています。
脊髄は、脳からの指令を筋肉に伝えるとともに、感覚情報を脳へ送る役割を担っています。
一方、脊椎は脊髄を保護することに加えて、体を支え、柔軟な動きができるような骨格の構造となっています。
体を動かす時、まず脳が運動の指令を出し、その信号が脊髄を通じて運動神経に伝わります。
運動神経は筋肉を刺激し、手足や体幹を動かします。
さらに、感覚神経が筋肉や関節の状態を脊髄に伝え、その情報が脳へ送られることで、姿勢の調整や細かい動きのコントロールが可能になります。
また、脊髄には反射機能があり、素早い動きが必要な場合には、脳を経由せずに直接反応します。
(参照サイト:脊髄反射|脳科学辞典)
さらに、脊椎は、脊髄がスムーズに情報を伝達できるように、可動性と安定性を両立した構造になっています。
椎間板がクッションのような役割を果たし、外部からの衝撃を吸収します。
関節や靭帯は、適切な可動域を確保することで、脊髄の働きを支えています。
まとめ
今回の記事では、脊髄と脊椎の役割から見る身体の重要な機能とはについて解説しました。
脊髄は脳と全身をつなぎ、運動、感覚、自律神経の調整を行い、脊椎はその脊髄を保護しながら体を支えています。
そのため、脊髄損傷が起こると、運動機能や感覚が失われ、日常生活に大きな影響を及ぼします。
近年、再生医療の進歩により、脊損による症状回復への期待が高まっています。
『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』を、ニューロテック®と定義しました。
ニューロテック、脳梗塞脊髄損傷クリニックなどでは、脳卒中・脊髄損傷を専門として、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しております。
リニューロ®とは、脳卒中や脊髄損傷、神経障害の患者さんに対する『狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療』と定義しております。
具体的には、同時刺激×神経再生医療Ⓡに加えて、治療効果を高めるために骨髄由来間葉系幹細胞、神経再生リハビリ®を併用し、神経障害の更なる軽減を目指しています。
これらの治療法は、脊髄損傷の後遺症で苦しむ患者さんに対して期待が持てる治療となるでしょう。
よくあるご質問
- 脊髄の主な機能は何ですか?
- 主な機能として、情報の伝達、反射の制御、自律神経の調整の三つがあります。
情報伝達として、脳からの運動指令を筋肉に伝えたり、体の感覚情報を脳に送ったりします。
反射の制御として、反射をコントロールし、刺激にすばやく反応できるようにします。
自律神経の調整として、内臓の働き、血圧、呼吸などを調整します。 - 脊椎の機能は?
- 主な機能は、脊髄の保護と体を支えることです。
まず、脊椎は脳からつながる脊髄を包み込んで、外部からの衝撃を守る働きがあります。
次に、体の中心として骨格を支え、正しい姿勢を保つように体を支える機能があります。
<参照元>
・(1)脊髄後角神経回路による体性感覚の情報処理|生化学2016;88:pp229-232:https://seikagaku.jbsoc.or.jp/10.14952/SEIKAGAKU.2016.880229/data/index.html
・(2)皮質脊髄路の基礎知識|脊髄外科2015;29:pp267-278:https://www.jstage.jst.go.jp/article/spinalsurg/29/3/29_267/_pdf?utm_source=chatgpt.com
・(3)脊髄反射|脳科学辞典:https://bsd.neuroinf.jp/
あわせて読みたい記事:非骨傷性頸髄損傷の病態と回復に向けた治療法
外部サイトの関連記事:首の手術による脊髄損傷の治療と回復プロセス



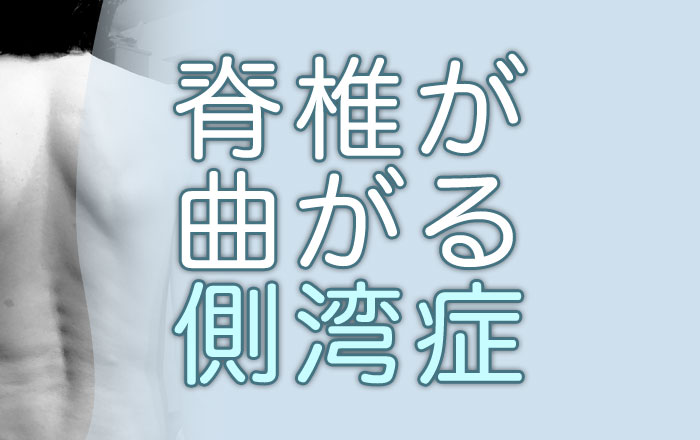
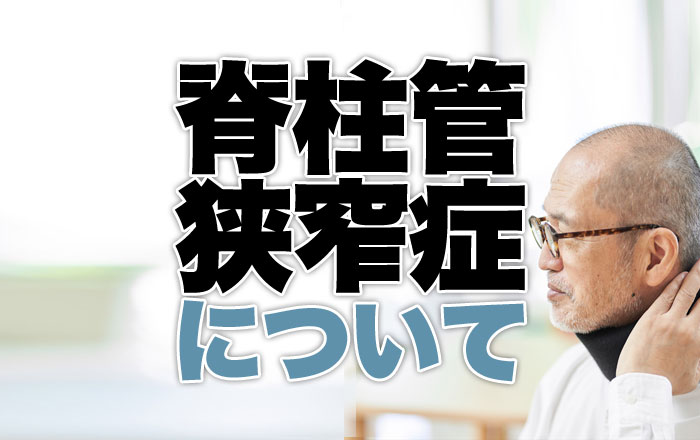












コメント