この記事を読んでわかること
脳血管性認知症の原因と特徴がわかる。
アルツハイマー型認知症と脳血管性認知症との違いがわかる。
脳の損傷部位ごとに、どのような認知機能の障害があるかがわかる。
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって起こる認知症の一種です。
本記事では、アルツハイマー型認知症との違いや、脳の損傷部位ごとの症状、感情や注意力、遂行機能への影響についてわかりやすく解説しています。
脳卒中後の認知症に不安を感じている方やご家族は、ぜひ参考にしてみてください。
脳血管性認知症の原因と特徴:アルツハイマー型との違い

認知症とは、通常、慢性的あるいは進行性の脳疾患によって生じ、記憶や思考、見当識、理解、計算、学習、言語、判断など多くの高次脳機能障害からなる症候群とされています。
つまり、生まれつきの知能レベルの問題ではなく、生まれてきてから徐々に脳の神経細胞の働きが低下し、記憶や判断力といった認知機能が低下することで社会生活に支障がでる状態を指します。
認知症にはさまざまなタイプがあります。
中でも最も多いものが、アルツハイマー型認知症です。
ついで、血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症があります。
過去には、日本では血管性認知症がアルツハイマー型認知症よりも多かったのですが、1990年代後半からアルツハイマー型認知症が増加傾向になりました。
特に80歳以上の方での増加が目立っています。
そして、今後も、アルツハイマー型認知症が増えていくことが予想されています。
ここでは、アルツハイマー型認知症と血管性認知症のそれぞれの特徴とその違いについて簡単に説明します。
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー型認知症は、老人斑(アミロイドβ蛋白がまだらにたまったもの)と、神経原線維変化が多発することが特徴です。
この老人斑は新皮質連合野という大脳の表面の方の部分に現れ、その後密度を増しながら他の部位にも広がっていきます。
老人斑の蓄積などによって、脳の神経細胞が破壊されてしまい、脳が萎縮してしまうというメカニズムが考えられています。
初期の段階では、昔の記憶は保たれるが、最近のことはどんどん忘れて行ってしまいます。
ゆっくりと進行することが多く、やがて時間や場所の感覚を失い、状況に合わせた判断が難しくなります。
血管性認知症
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血といった脳血管障害が原因となる認知症のことです。
血管性認知症にはさまざまなタイプがあります。
中でも、小血管病性認知症が最も多いとされています。
脳の小血管の穿通枝(せんつうし)領域にラクナ梗塞や白質病変、脳出血、わずかな出血などの細い動脈硬化の所見を認めます。
なお、穿通枝は、太い脳動脈から枝分かれし、脳の深い部分まで酸素や栄養を送っている細い血管のことです。
血管性認知症は、脳卒中発作の後に、段階的に、認知機能障害が進行していくことが典型的とされています。
特に、脳卒中の後に認知症を起こすものは脳卒中後認知症と呼ばれています。
脳卒中後認知症の割合では、脳卒中を起こした方の30%であり、脳卒中発症から1年後には7%であったものが25年後には48%に増えるという報告もあります。
ただし、脳卒中後認知症の中にはアルツハイマー型認知症が原因となっている場合もある点には注意が必要です。
危険因子としては、加齢や運動不足、脳卒中の既往、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満、心房細動、喫煙が挙げられます。
血管性認知症とアルツハイマー型認知症との違い
血管性認知症とアルツハイマー型認知症との違いとしては、血管性認知症は脳の損傷を受けている部位に対応するような神経脱落症状がみられるなど、身体の機能障害を伴うことが多い点が挙げられます。
例えば、歩行障害、転倒しやすくなる、排尿障害、人格障害、意欲の低下、うつ、などがあります。
なお、アルツハイマー型認知症と比べ、血管性認知症ではうつを合併する割合も高いと言われています。
脳のどこが損傷すると認知機能が落ちるのか?
大脳は、前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉に分けられています。
その中でも側頭葉は、脳の後方側面を占めている領域であり、視覚や聴覚といった認知機能や記憶の中心となっていることが知られています。
また、側頭葉はもちろん、脳の後ろの方を占める後頭葉や、上の方を占める頭頂葉も認知的な処理を行う重要な部位となります。
脳の損傷部位と認知機能の関係については、以下のようになります。
脳の内側底面
この部位は、解剖学的には舌状回の外側部あるいは紡錘状回の後内側部などが該当します。
これらは、視覚に関する認知的処理が行われている領域です。
損傷すると、色が認識できなくなったり、顔をみても誰かわからない相貌失認、よく知っているはずの建物や風景を見てもわからない街並失認などが起こります。
脳の前部
解剖学的には、海馬とその周辺の皮質が該当します。
脳のこの部位での損傷によって、健忘が起こります。
健忘は、きっかけとなった出来事の数秒前、数日前、さらに前、またはその後に起こった体験や出来事を思い出す能力が部分的または完全に失われる障害です。
脳の上の方の内側面
これは解剖学的には脳梁膨大後域が該当します。
左では健忘、右では道順障害が起こります。
道順障害は、よく知っているはずの地域内で、ある地点から別の地点へ移動する際に、方角を定位する(どちらの方向に進めばよいか)ことが困難になる状態です。
簡単に言えば、道順がわからなくなることで道に迷う状態です。
これらのように、脳の損傷を受ける部位によって、さまざまな認知機能障害が現れます。
感情のコントロール・注意力・遂行機能が障害されやすい理由
血管性認知症では脳血管障害によって特定の脳の部位が損傷を受けます。
そのために、感情のコントロールや注意力、遂行機能が低下しやすいともいえるでしょう。
実際に、遂行機能障害や注意力の問題は、記憶障害や喚語障害が通常優勢であるアルツハイマー病とは異なり、血管性認知症かどうかを見極める上で重要な手がかりとなる可能性があります。
例えば、血管性認知症で、特に前頭葉や前頭基底部の損傷が起こる場合もあります。
前頭葉は、感情の抑制、集中力、計画立案などを司る重要な部位です。
そのため、これらの機能が障害されると、怒りっぽくなったり、物事に集中できなくなったり、段取りよく行動することが難しくなったりします。
これにより、日常生活では感情的なトラブルが増えたり、仕事や家事の効率が大きく落ちることも少なくありません。
まとめ
血管性認知症は、脳梗塞や脳出血といった脳血管障害によって引き起こされる認知症の一種です。
血管性認知症は、高血圧や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病や、喫煙などがリスクとなる場合もあります。
こうした病気や生活習慣をきちんと管理、改善していくことで、血管性認知症を予防できる可能性もあります。
また、脳の損傷部位によって現れる症状が異なるため、早期の診断と適切なリハビリテーションが重要です。
ニューロテック、脳梗塞脊髄損傷クリニックなどでは、脳卒中後の認知機能低下に対して、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療「リニューロ®」や「神経再生リハビリ®」を組み合わせ、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める取り組みを行っています。
早期から専門的な治療とサポートを受けることで、生活の質(QOL)の維持や回復を目指すことが可能です。
よくあるご質問
- 脳血管性認知症の特徴は?
- 脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害が原因となり、認知機能が段階的に低下するのが特徴です。
感情のコントロール、注意力、遂行機能の障害が目立ち、歩行障害や排尿障害を伴うこともあります。 - 脳血管障害の初期症状は?
- 脳血管障害の初期症状には、片側の手足のしびれや脱力、ろれつが回らない、視野が欠ける、急なめまい、意識障害などがみられます。
これらの症状が突然現れることが特徴で、早期の医療機関受診が重要です。
<参照元>
(1):認知症疾患診療ガイドライン2017、1 章 認知症全般:疫学,定義,用語:https://www.neurology-jp.org/guidelinem/nintisyo_2017.html
(2):知っておきたい認知症の基本 | 政府広報オンライン:https://www.gov-online.go.jp/article/202501/entry-7013.html#firstSection
(3):1 4章 血管性認知症 vascular dementia(VaD)の診断基準はど のようなものか:https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_14.pdf
(4)ラクナ梗塞 (らくなこうそく)とは | 済生会:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/lacunar_infarction/
(5)記憶を正しく思い出すための脳の仕組みを解明~側頭葉の信号が皮質層にまたがる神経回路を活性化|東京大学:https://www.jst.go.jp/pr/announce/20150424-2/index.html
(6)認知的処理における「大脳内側面・底面」の役割.神経心理学.2017:33;238-250.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/neuropsychology/33/4/33_17011/_pdf
(7)Vascular Dementia – StatPearls – NCBI Bookshelf.:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430817/
あわせて読みたい記事:アルツハイマー型認知症とは
外部サイトの関連記事:脳血管性認知症に再生医療は有効か?治療とその効果を解説



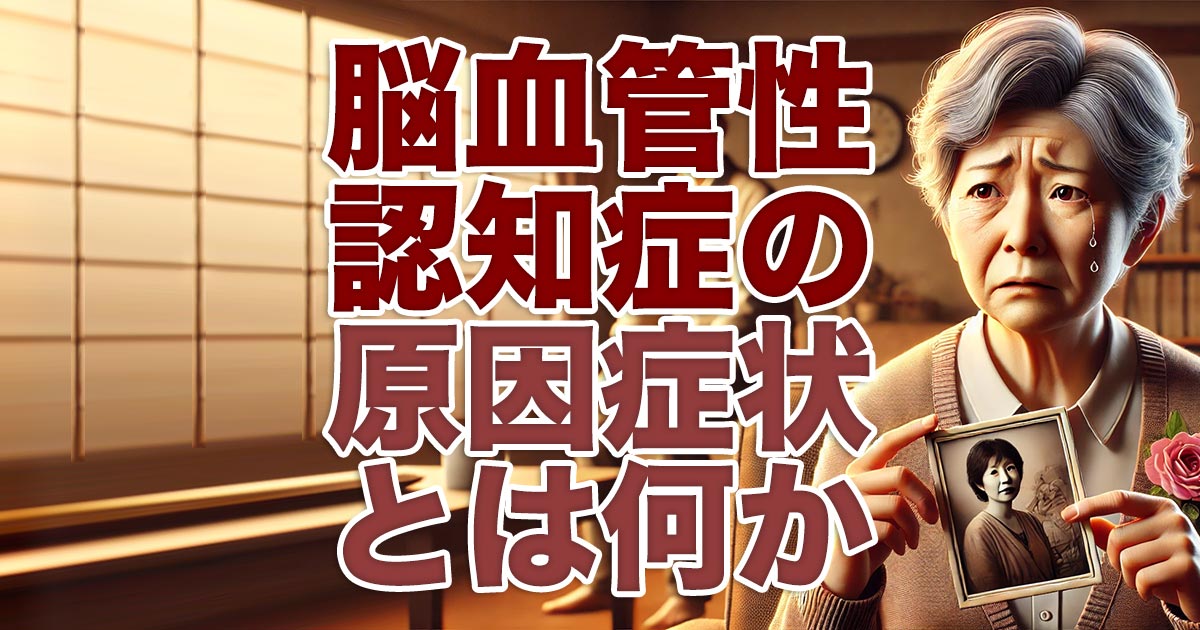
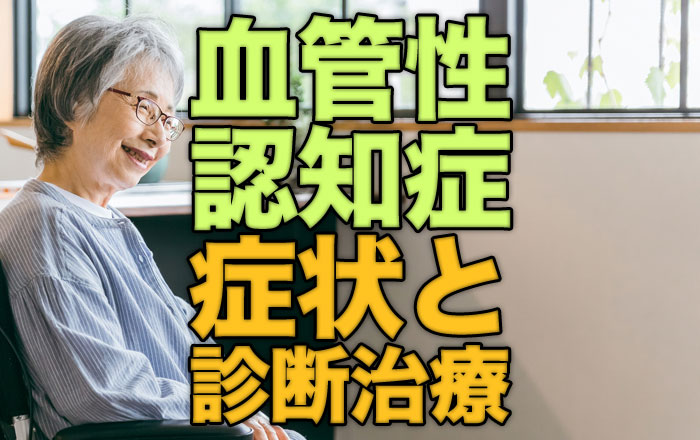












コメント