この記事を読んでわかること
パーキンソン病がどのように進行し、“末期”とはどのような状態を指すのかがわかる。
進行を遅らせるために日常生活でできる運動・食事・休養の工夫がわかる。
医療や介護、再生医療を含む今後の治療の可能性について知ることができる。
パーキンソン病は、神経の働きが少しずつ低下していく進行性の病気です。
しかし、早期からのリハビリや生活習慣の工夫によって、進行をゆるやかにし、長く自分らしく暮らすことが可能です。
この記事では、病気の進行段階や日常生活でのケアのポイント、利用できる医療・介護制度、さらに再生医療の最新研究についても解説します。
“末期”を迎える前に知っておきたいパーキンソン病の進行と特徴

パーキンソン病は、脳の神経細胞が少しずつ減っていくことで、手足が震えたり、動作が遅くなったりする病気です。
しかし、発症の前には、実は前駆期(プレモーターステージ)と呼ばれる段階があります。
この時期には、便秘、嗅覚の低下、夢と連動して体を動かしてしまうレム睡眠行動障害などが、身体の動きがぎこちなくなるといった運動症状より前に起こるサインが見られることがあります。
その後、実際の動作に、手足の震えや筋肉のこわばりなどの症状が現れる時期(いわゆる運動期)に入り、さらに進行すると、歩行や姿勢のバランスを保つことが難しくなる進行期へと移行します。
現在では、治療薬の進歩により、パーキンソン病であっても一般の方とほぼ同等の寿命が期待できるようになりました。
また、進行のスピードは人によって異なり、早めのリハビリや生活習慣の工夫でゆっくり進むケースも多くあります。
最近では、一般の方でも早めに気づけるような検査や診断技術の研究も進められており、早期に治療や運動を始めることで、進行をさらに抑えられる可能性が注目されています。
たとえば、嗅覚検査や記憶・注意力を調べる神経心理学的検査、心臓の画像検査(核医学)など、早期発見を目指す研究も進められています。
一方で、進行すると、歩行が難しくなったり、飲み込みにくさ(嚥下障害)や転倒が増えたりすることがあります。
さらに、末期の段階になると、日常生活の基本動作が難しくなり、寝たきりになります。
また、認知機能の低下や、うつ状態などの身体の動き以外の症状も目立つことがあります。
進行を遅らせるためのケア|運動・食事・生活習慣

ここでは、パーキンソン病の進行をゆっくりにするために大切なポイントを説明します。
運動とリハビリのポイント
体を動かすことは、神経の働きを保つためにとても大切です。
運動療法としては、身体をリラックスさせることがまず挙げられます。
またゆっくりと体幹をねじり、さらにゆっくりと関節を動かすことで、関節が固まるのを防いだり、柔軟性を保ったりする訓練(ROM訓練)などもあります。
また、背中を伸ばしたり骨盤を傾けたりする訓練や、実際にベッドなどから車いすに移乗するなどの移動訓練などもあります。
そのほかにも、ウォーキングや、バランス訓練、エアロビック訓練、筋力訓練、太極拳などもあります。
さらに家でもできるホームエクササイズも筋力を高めるために有効であるとする報告もあります。
無理のない運動を日課にすることで、筋力やバランス感覚を保ちやすくなります。
また、言葉が出にくい方には「声を出す訓練」も有効です。
近年では、音楽療法やダンス療法なども注目されています。
リズムに合わせて体を動かすことで、運動だけでなく心の活性化にもつながることがわかっています。
食事と休養
バランスの取れた食事を意識し、野菜やたんぱく質をしっかりとりましょう。
水分をこまめに摂ることや、誤嚥(ごえん)を防ぐ食べ方の工夫も重要です。
十分な睡眠をとり、体を休めることも進行を遅らせる一助となります。
特にたんぱく質は、L-ドパなどの一部の薬の効きを妨げることがあるため、服薬時間とのバランスに注意しましょう。
栄養士による食事指導を受けるのもおすすめです。
家庭での工夫
転倒しないように床の段差やカーペットを減らし、使いやすい家具配置に整えることがポイントです。
家族や介護者が患者さんと一緒に取り組むことで、心の支えにもなります。
日々の小さな成功体験を共有することが、本人の自信やリハビリ継続のモチベーションにつながります。
介護者も無理をしすぎず、支援を受けることが大切です。
医療・介護体制と再生医療の可能性
パーキンソン病の治療は、薬だけでなく、医療・リハビリ・介護が連携する「チーム医療」が大切です。
医療費助成や介護サービスなど、パーキンソン病の方を支える制度も整備されています。
その一つの医療費については、ホーン・ヤール重症度分類が3度以上、かつ生活機能重症度2度以上の患者さんの場合には、難病医療費助成制度の対象となります。
なお、ホーン・ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の進行度を5段階で評価するものであり、数値が小さいほど軽症を意味します。
また、重症度分類が1,2度の場合でも、医療費が一定額を超えた場合には、高額療養費制度の適応となります。
そのほか、訪問リハビリやデイケアなど、在宅でも支援を受けられる仕組みがあります。
こうした制度によって、治療やリハビリを継続しやすい環境が整いつつあります。
そして、もう一つの希望として注目されているのが、「神経そのものの修復」を目指す再生医療です。
また、近年では、神経の再生を目指す再生医療の研究も進んでおり、iPS細胞を使ってドーパミンを作り出す細胞を移植する臨床研究も行われています。
医療の進歩は、「病気と共に生きる」人々にとって大きな希望となるでしょう。
まとめ
パーキンソン病は、焦らず向き合うことで生活の質を長く保つことが期待できる病気です。
毎日の運動、栄養、睡眠、そして支えてくれる人たちとのつながりが、何よりの治療になります。
リニューロ®(同時刺激×神経再生医療®)のように、神経を再構築する力を引き出す治療も登場しています。
薬だけに頼らず、自分の回復力を引き出す時代へと進化しています。
医療の進歩と再生医療の力を味方につけながら、今できるケアを一歩ずつ積み重ねていきましょう。
病気と共に生きる中で、“自分らしさ”を取り戻すことが最大のリハビリです。
小さな努力の積み重ねが、確実に未来の自分を支える力になります。
<参照元>
(1)Siderowf A, Lang AE. Premotor Parkinson’s disease: concepts and definitions. Mov Disord. 2012 Apr 15;27(5):608-16. doi: 10.1002/mds.24954. PMID: 22508279; PMCID: PMC3335740.:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3335740/
(2)パーキンソン病(指定難病6):https://www.nanbyou.or.jp/entry/169
(3)パーキンソン病診療ガイドライン2018 第 11 章 パーキンソン病のリハビリテーション:https://neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_19.pdf
(4)薬剤師解説 薬物治療の取り組みと留意.日本静脈経腸栄養学会雑誌.2017;32(5):1445-1447.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspen/32/5/32_1445/_pdf
(5)パーキンソン病診療ガイドライン2018 第 12 章 公的制度・費用対効果:https://neurology-jp.org/guidelinem/pdgl/parkinson_2018_20.pdf
(6)世界トップクラスのパーキンソン病iPS細胞バンクを背景に根本的治療薬の開発を目指す! – Juntendo Research:https://www.juntendo.ac.jp/branding/report/152/
あわせて読みたい記事:脳卒中とパーキンソン病の関連性
外部サイトの関連記事:パーキンソン病と線条体黒質変性症の基本的な違い



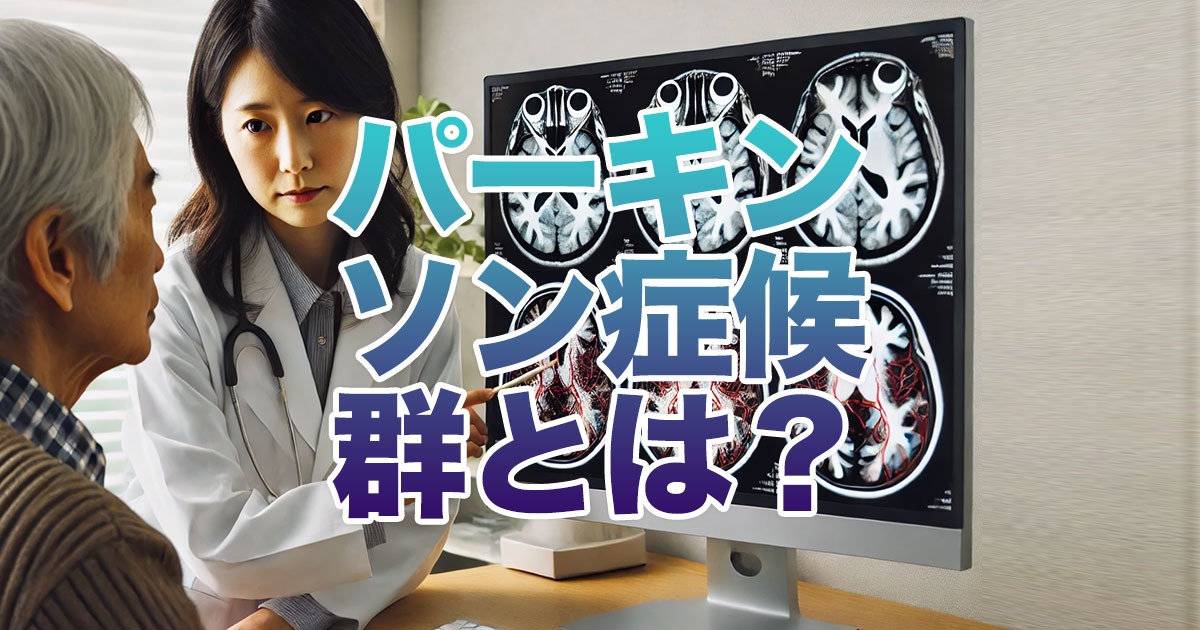
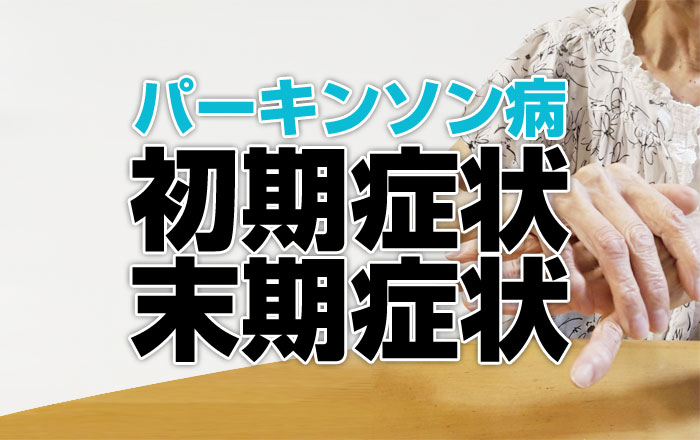












コメント