この記事を読んでわかること
延髄梗塞の内側と外側での症状の違いがわかる
延髄梗塞によって生じるさまざまな後遺症がわかる
延髄梗塞に有効な画像診断がわかる
延髄はとても小さいながらも、呼吸機能や心臓中枢、嚥下機能や構音機能など、非常に重要な機能をいくつも司るとても重要な脳の一部です。
そのため、障害される部位によって出現する症状も異なり、麻痺や感覚障害の出方も梗塞部位によって異なります。
そこでこの記事では、延髄梗塞の内側・外側での症状の違いについて解説します。
延髄内側 vs 外側の障害による麻痺のパターン比較
延髄梗塞とは脳梗塞の1種であり、延髄を栄養する血管で梗塞が生じることで発症します。
また、延髄はさまざまな機能を司る部位であるため、その発症によってさまざまな神経症状をきたします。
延髄自体は実は大人の親指よりも少し大きいくらいの大きさと言われていますが、その中でも司る機能は異なり、梗塞によって障害されるのが延髄の内側・外側かによっても出現する麻痺のパターンは異なります。
まず、延髄内側は前脊髄動脈や左右の椎骨動脈など、豊富な血管によって栄養されているため、梗塞に陥ることは極めて稀であり、報告によれば脳梗塞全体の0.5〜1.5%です。
延髄の内側で梗塞を発症した場合、延髄の内側に位置する下記の3つの部位が障害され、それぞれ出現する症状も下記の通りです。
- 舌下神経核:同側の舌の麻痺や萎縮
- 内側毛帯:対側の深部知覚障害
- 錐体路:対側の麻痺(顔面を除く))
以上のような3つの特徴的な症状を有し、これをDejerineの三徴といいます。
次に、延髄の内側で梗塞を発症した場合、これはいわゆるWallenberg症候群といい、それぞれ障害される部位と出現する症状は下記の通りです。
- 前庭神経核:眼振など
- 三叉神経核:同側の顔面の麻痺
- 小脳との連絡路:同側の小脳失調
- 脊髄視床路:対側の温痛覚障害
- 自律神経:交感神経障害(眼瞼下垂・瞳孔縮小など)
以上のことから、内側の梗塞では対側の上下肢に麻痺が生じ、外側の梗塞では同側の顔面の麻痺が生じることがわかります。
嚥下障害・構音障害・呼吸障害など多様な後遺症

先述の通り、延髄にはさまざまな機能を司る神経回路や神経核が位置しており、延髄梗塞によって多彩な後遺症が出現します。
延髄に存在する神経核は下記の通りです。
- 舌咽神経核:舌の後方1/3の味覚・咽頭部の感覚・咽頭筋の収縮など
- 迷走神経核:心機能の抑制・消化機能促進・嚥下や発声に関わる筋肉の運動など
- 舌下神経核:舌の筋収縮
舌咽神経が障害されると、咽頭部の正常な筋収縮が得られなくなるため、嚥下障害(ものの飲み込みが悪くなる)を生じ、長期的には誤嚥性肺炎の発症リスクを増大させます。
同様に、舌下神経核が障害されると舌を自由に動かすことができなくなり、うまく言語を発せられなくなったり、嚥下機能が低下する可能性があります。
次に、迷走神経は嚥下や発声に関わる筋肉の運動を支配しており、障害されることで嗄声や構音障害・嚥下障害など、さまざまな機能が障害されるため注意が必要です。
さらに、延髄には呼吸中枢や心臓中枢も位置しており、広範に障害されると呼吸能力や循環維持能力が破綻し、生命維持すら困難になる可能性があるため、注意が必要です。
画像診断(MRI)と臨床症状の突き合わせ方
一般的に、医療機関を受診した患者に対してまずは身体診察や問診を行い、患者の問題点や病歴を抽出します。
その際、麻痺の部位や感覚障害の部位、構音障害や嚥下障害の有無などを確認し、病変部位が脳のどの部分なのか、もしくは脳以外の可能性が高いのかを判断します。
その上で、最終的にはCTやMRIなどの画像検査を用いた画像診断を行うことが重要です。
特に、発症急性期の脳梗塞の場合、CTでは検出できない可能性が高く、急性期の診断においてはMRIが重宝されます。
一方で、たとえMRIを用いたとしても延髄は周囲を骨組織や髄液に包まれており、さらには病変部位も大変小さいため、検出感度が低く、偽陰性の可能性が高くなりやすいです。
実際に、山崎らの報告によれば、延髄梗塞の偽陰性率は25.4%であり、他の文献では64.7%とする報告も認めており、報告によってばらつきが大きい結果でした。
そのため、画像検査所見だけに頼らず、あくまで臨床症状から病変部位を疑っていくことが正確な診断の上では重要です。
まとめ
今回の記事では、延髄梗塞の病変部位における症状の違いについて詳しく解説しました。
延髄は小さいながらも非常に重要な機能を司る部位であり、呼吸や循環、運動や感覚など、生きていく上で必要不可欠な機能を司っています。
内側と外側では栄養する血管が異なり、梗塞するとそれぞれ別の症状が出現するため、診断の上では臨床症状が重要です。
また、内側・外側に関わらず、一度発症すると何らかの後遺症が残ってしまう可能性が高く、後遺症を根治するような治療法もないため、発症を予防することが重要です。
一方で、近年では延髄梗塞に対する新たな治療法として、再生医療が非常に注目されています。
また、ニューロテックメディカルでは、「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。
「ニューロテック®」では、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。
また、神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「同時刺激×神経再生医療Ⓡ」によって、これまで改善困難であった延髄梗塞の後遺症の改善が期待できます。
よくあるご質問
- 脳梗塞には何種類あって、それぞれの違いは何ですか?
- 脳梗塞は血管の詰まり方によって、アテローム性血栓性脳梗塞・ラクナ梗塞・心原性脳梗塞の3つに大別されます。
動脈硬化によって太い血管にアテロームができて梗塞するのがアテローム性血栓性脳梗塞、細い血管が狭小化するのがラクナ梗塞です。
また、心臓にできた血栓が飛んで生じる脳梗塞を心原性脳梗塞といいます。
- 延髄梗塞の症状は?
- 延髄梗塞の症状は、麻痺やしびれ、頭痛、嘔気、意識障害、呼吸障害などが挙げられます。
また、延髄に位置する脳神経核が障害されることで、構音障害・嚥下障害なども出現します。
<参照元>
(1):Dejerine症候群の三徴を示さず,診断に難渋した延髄内側梗塞の1例|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics1964/36/12/36_12_899/_pdf
(2):延髄梗塞の臨床的検討|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jstroke/29/4/29_4_502/_pdf/-char/ja
あわせて読みたい記事:ワレンベルグ症候群という脳梗塞の原因と症状
外部サイトの関連記事:延髄梗塞を引き起こす原因とリスクを徹底解説



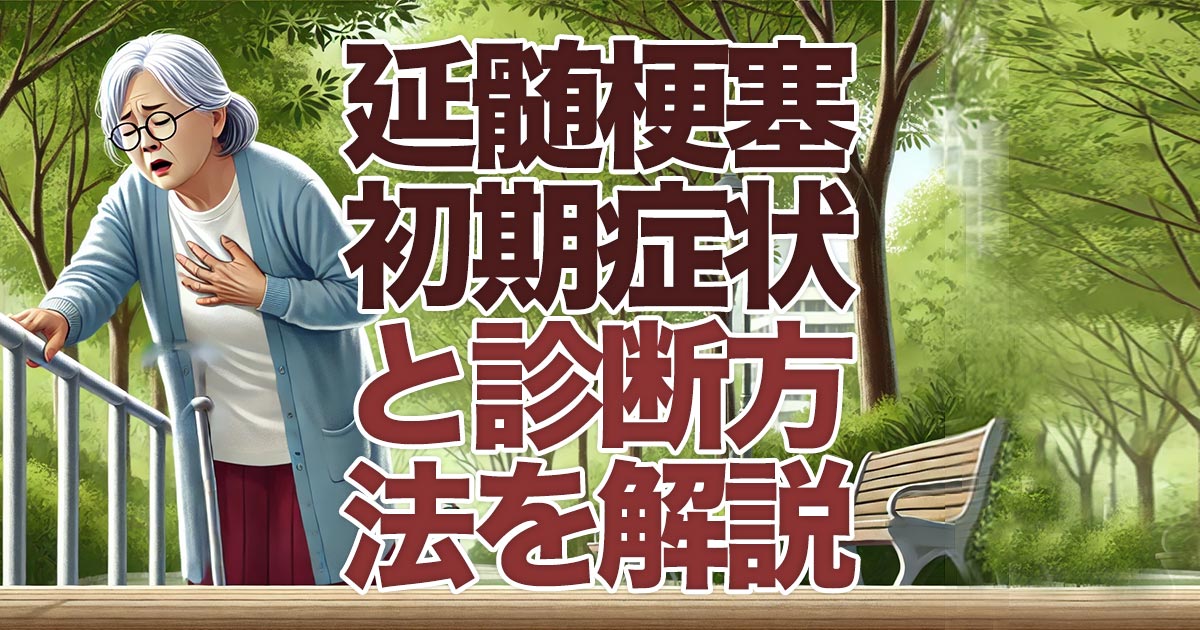
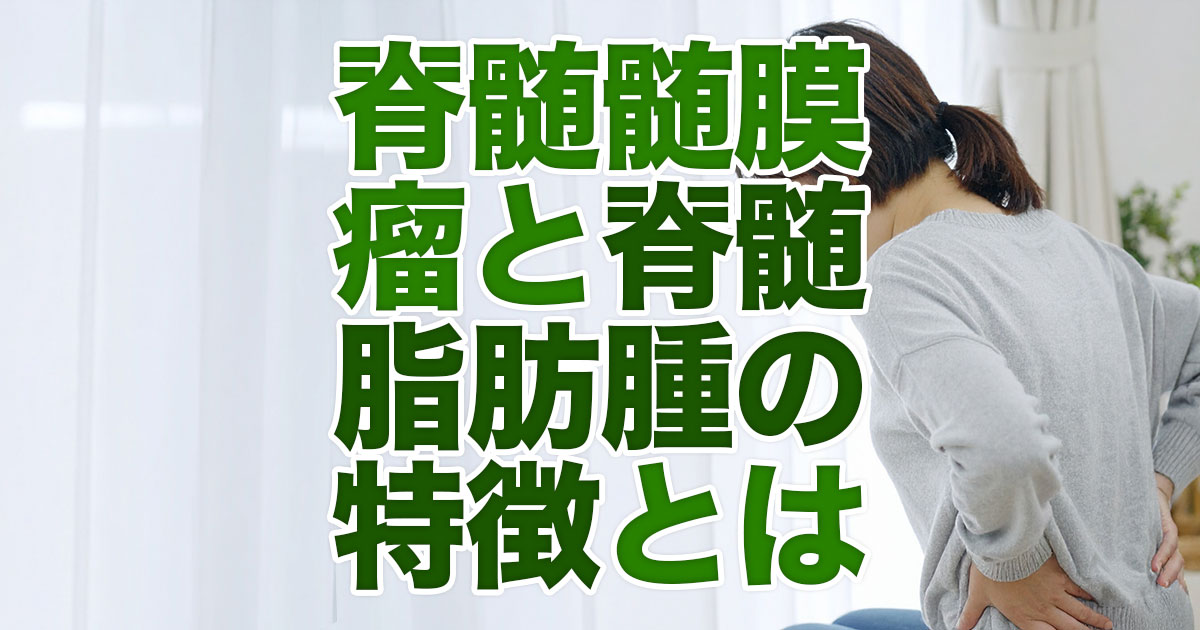












コメント