この記事を読んでわかること
出血性梗塞の特徴
どのような脳梗塞が出血性梗塞を起こしやすいか
出血性梗塞後のリハビリテーション
出血性梗塞とは脳梗塞後に脳出血を起こす疾患です。
後遺症が重症になりやすく、心原性脳塞栓症や脳内の治療後に発症しやすいと言われています。
症状が落ち着いた後、リハビリテーションを行うことが重要です。
この記事では出血性梗塞について、特徴から発症しやすい疾患、リハビリテーションまで解説します。
脳梗塞の後に症状が悪くなる出血性梗塞とは

脳梗塞とは脳の血管に血栓などが詰まることで、詰まった部位よりも先の脳の組織に血液が行き渡らないことで脳が障害を受ける疾患です。
血栓によって詰まってしまった血管は栄養が十分に行き渡らないため、血管の壁が弱くなります。
脳梗塞後では血栓が移動したり、治療によって血栓が溶けたりする場合があり、その結果弱った血管に血液が流れこみます。
弱った血管に血流が急激に戻ることで、血管の壁が破れて脳出血を合併することがあります。
このように、脳梗塞後の血管に血流が戻ることで脳出血を起こす病態を出血性梗塞と言います。
出血性梗塞では、元々の脳梗塞で出現していた症状に加えて、片麻痺・感覚障害・注意障害などの高次脳機能障害が悪化したり、出血量が多いと意識がなくなることがあります。
出血性梗塞は脳梗塞後に起きるため、基本的には入院中に発症します。
発症すると意識がもうろうとしたり、手足の動きが悪くなったり、言葉が出にくくなることがあります。
出血性梗塞は看護師の見回りや療法士がリハビリを行う際などに気付くことが一般的です。
早期での治療は、通常の脳出血と同様に血圧を下げ、出血を止めることが最優先で行われます。
また、出血量が多く、降圧のみでは出血を止めることができない場合は手術を行い、脳にかかる圧迫を軽減させる治療を行います。
出血が落ち着けば、リハビリテーションを行い動作の獲得を目指した治療を行います。
病態によって変わる発症率とリスク要因
脳梗塞はいくつかの種類に分類することができますが、出血性梗塞は種類によって発症率が変わります。
最も出血性梗塞を起こしやすい脳梗塞は心原性脳塞栓症です。
心原性脳塞栓症とは、心房細動などの疾患によって作られた血栓が血流に乗って脳の血管で詰まってしまう脳梗塞です。
他の脳梗塞と違い、心原性脳塞栓症は大きな脳血管に急激に血栓が詰まるため、症状が急激かつ重度の症状が起きやすいことが特徴です。
また、心原性脳塞栓症は血栓が移動したり、溶けたりすることによって90〜95%の方に脳内の血流が戻ると言われています。
そのため、血栓が詰まることによって弱った血管に血流が戻り発症する出血性梗塞が起きやすくなります。
心原性脳塞栓症における出血性梗塞は、軽症例も含むと血流が再開した約40%の方に認められるとの報告もあります。
また、他の脳梗塞でも出血性梗塞は起きることがあります。
特に発症しやすいタイミングは、血栓を溶かす治療や血栓そのものをカテーテルで取り除く治療後です。
このような治療後は出血リスクが高くなっているため、医師や看護師、療法士などは麻痺症状や高次脳機能障害の変化に注意を払います。
もし、出血してしまった場合は速やかに急性期治療を行います。
生活の自立を目指すリハビリテーション

出血性梗塞に対するリハビリテーションは、通常の脳出血後のリハビリと同様に生活の自立を目指して行います。
通常の脳卒中と比較すると、梗塞後に出血しているため症状が重くなりやすいことが出血性梗塞の特徴です。
また、発症後は症状が進行していないかを確認しながら進めることが重要です。
発症後すぐは症状が悪くなっていないことと血圧が上がり過ぎていないかを確認しながら、車椅子への乗り移りの練習から開始します。
状態が安定すれば、歩行練習や生活動作の練習を行います。
嚥下障害や注意障害などの高次脳機能障害がある場合は言葉や飲み込みのリハビリを行う言語療法士による訓練を行い、食事のための嚥下訓練やコミュニケーション手段の確立を目指します。
急性期病院で生活に戻ることができる程度まで症状が改善すれば自宅に退院し、積極的なリハビリを継続した方がよければ回復期リハビリテーション病院へ転院します。
転院後は積極的に歩行練習や生活動作練習に加えて、身体機能を上げるための筋力トレーニングや可動域訓練などを行います。
回復期リハビリテーション病院では集中的にリハビリを行って訓練の量を増やすことができます。
訓練量の増加は歩行などの動作の再獲得に重要とされています。
生活に必要な動作の獲得や退院後の環境調整が整えば退院し、自宅でのリハビリテーションに移行します。
在宅でのリハビリテーションは介護保険を使用したサービスや医療保険を使用した通院リハビリなどがあります。
退院後も継続したリハビリテーションや自主練習を行い、身体機能や動作能力を維持・向上できるようにしましょう。
まとめ
この記事では脳梗塞後に症状が悪化する出血性梗塞について解説しました。
出血性梗塞は脳梗塞後に脳出血を起こす疾患で、重い症状が出やすいことが特徴です。
心原性脳塞栓症が最も起こりやすいですが、その他の脳梗塞でも治療後に注意が必要です。
状態が落ち着いた後はリハビリテーションを行い、身体機能や生活動作の改善を目指します。
出血性梗塞で残存した神経障害の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。
今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。
私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。
当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。
よくあるご質問
- 出血性梗塞と脳出血は別の疾患ですか?
- 出血性梗塞は先に脳梗塞を発症し、その後に弱った血管に血液が流れ込んで脳出血を起こす疾患です。
そのため、病気のきっかけは血管が閉塞したことによる梗塞のため、分類上は脳梗塞になります。
- 出血性梗塞で命に関わることはありますか?
- 出血性梗塞を発症した後の出血の量によって、命に関わるかは変わります。
出血が多く、脳が圧迫されてしまうような状況になれば命に関わることがあります。
しかし、出血量が少ないこともあり、適切な治療によって後遺症を最小限にとどめることもあります。
<参照元>
(1)心原性脳塞栓症の治療と予防の最前線|J-stage :https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/106/3/106_490/_pdf/-char/ja
(2)脳卒中治療ガイドライン2021改定2025:https://www.jsts.gr.jp/img/guideline2021_kaitei2025_kaiteikoumoku.pdf
関連記事
あわせて読みたい記事:脳梗塞後の薬物や治療に関する禁止事項とは?
外部サイトの関連記事:脳梗塞後の日常生活の管理と家族支援



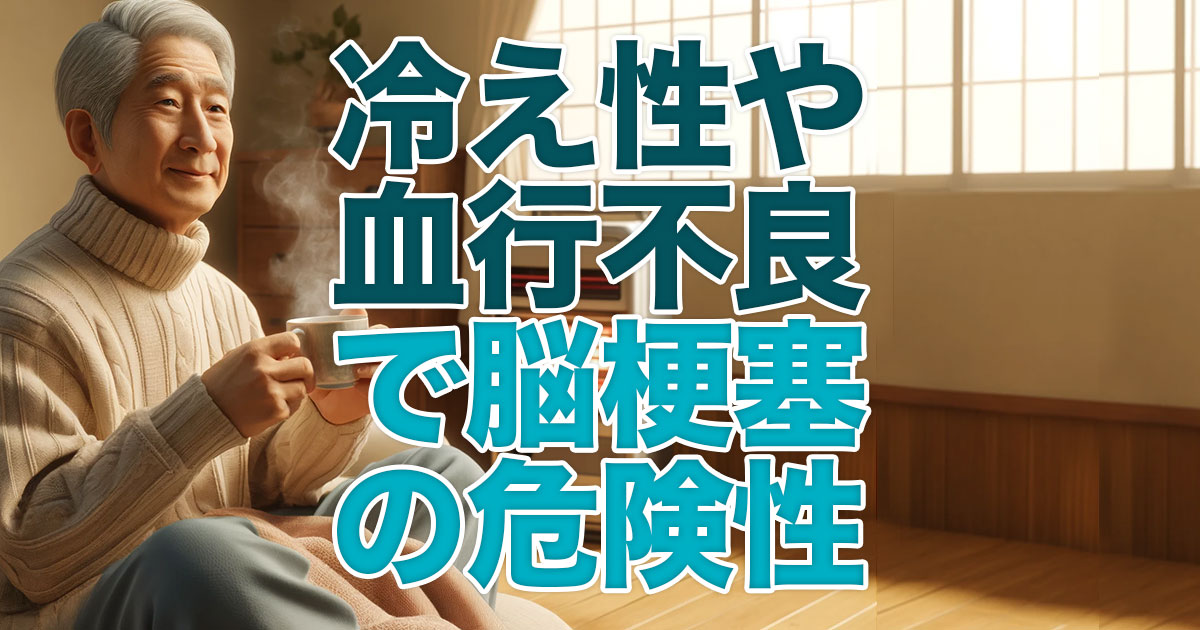
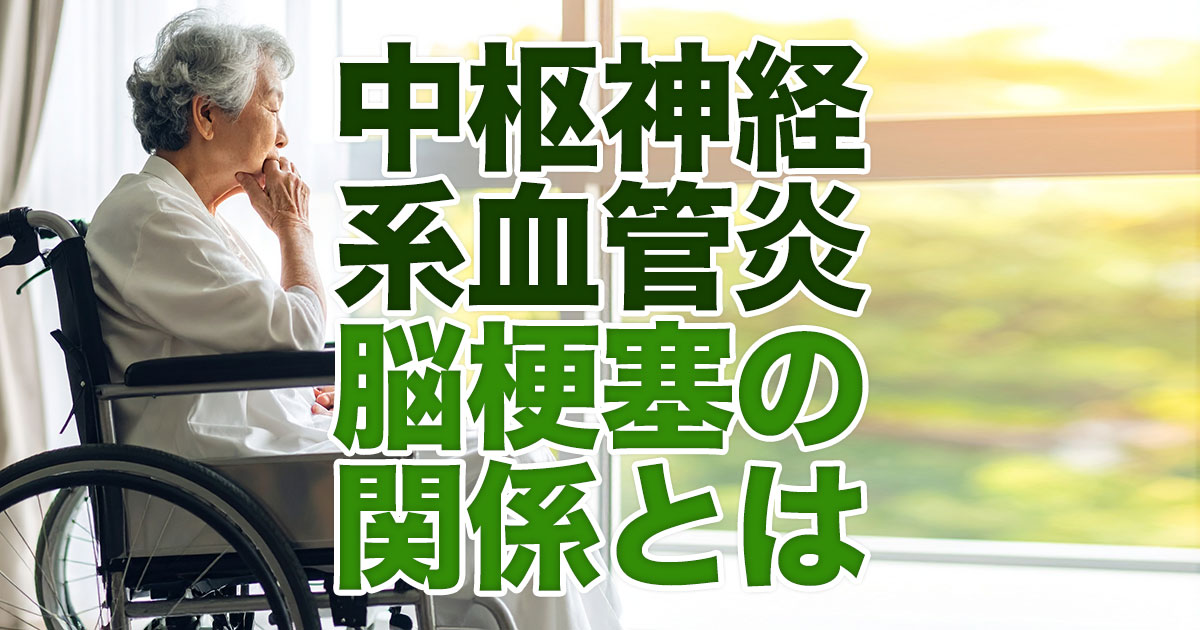












コメント