この記事を読んでわかること
教育歴と脳梗塞の関係性がわかる。
社会的支援の有無と脳梗塞の関係性がわかる。
精神的ストレスを伴いやすいライフイベントと脳梗塞の関係性がわかる。
脳梗塞は一般的に食事や運動などの生活習慣が発症に大きく関わりますが、近年の研究では教育歴やライフイベント、社会的支援の有無などの社会的リスク要因も、脳梗塞の発症に一定関わることがわかってきています。
そこで、この記事では社会的リスク要因が脳梗塞の発症に与える影響や仕組みを詳しく解説します。
脳梗塞の社会的リスク因子:教育歴

多くの方が一般的にイメージする脳梗塞のリスクとは、不健康な食生活や運動不足、肥満などが挙げられるかと思います。
しかし近年、多くの研究で社会的リスク因子が脳梗塞の発症リスクを増大させることが明らかとなっています。
社会的リスク因子とは、個人の健康や行動に悪影響を及ぼす可能性のある、個人を取り巻く社会的・環境的な要因のことであり、身体的、もしくは精神的なリスクとはまた異なるものです。
具体的には、下記のような要因が脳梗塞の社会的リスク因子として挙げられます。
- 教育歴
- 社会的支援
- 精神的ストレスを伴いやすいライフイベント
- 自覚的ストレス
例えば、教育歴と脳梗塞の関係については、これまでの多くの研究でもその関わりが報告されており、特に低学歴、もしくは高学歴であるにも関わらず職業的地位の低い仕事に従事している方は注意が必要です。
実際に、本城らの研究では、脳卒中や心臓病の病歴のない40〜59歳の日本人女性20,543名を対象に、中学校卒業・高校卒業・大学以上の教育を受けた場合で比較しています。
その結果、虚血性脳卒中のリスクを数値で表すと、リスクの低い順に下記のような結果が得られています。
| 高校卒業 | 大学以上 | 中学校卒業 | |
|---|---|---|---|
| リスク | 1 | 1.60 | 1.90 |
この結果において、学歴が低い方の場合は身体活動量が少なく、肥満や高血圧などの特徴が多く見られたため、脳梗塞が多いとされていましたが、逆に高学歴の方でリスクが上がる理由は解明されませんでした。
そこで、国立がん研究センターのJPHC Studyでは職業的地位と教育歴の両方が脳梗塞発症に与える影響を調査しています。
40〜59歳の女性約1万5千人を約20年追跡調査した結果、学歴に見合った職業のポジションにつけている方グループと比べ、学歴に見合った職業のポジションにつけていない方の脳卒中発症リスクは約2倍という結果でした。
以上の結果から、教育歴が高い方でも現在の職業的地位が低い場合、その自分の立ち位置に不満やストレスを感じることで脳卒中発症リスクが増大すると考察されています。
脳梗塞の社会的リスク因子:社会的支援

社会的支援(家族や友人による支援)を受ける機会が少ない方ほど、脳卒中による死亡リスクが上昇する傾向にあるため、注意が必要です。
癌および心血管疾患の既往歴のない40~69歳の日本人男女44,152名を対象とした池田氏(国立研究開発法人国立がん研究センター, がん対策研究所, 外来研究員)らの研究では、社会的支援が最も高いグループと最も低いグループで、脳卒中の死亡率や発症率を比較しています。
その結果、脳卒中死亡率の多変量ハザード比(病気などのイベントが発生するリスク)および95%信頼区間(CI)は、全体で1.45(1.00~2.10)、男性で1.59(1.01~2.51)、女性で1.25(0.63~2.46)であり、特に男性では死亡率が上昇していました。
一方で、社会的支援と脳卒中発症率には関連性は認められず、あくまで社会的支援の有無は予後に関わる要因であると推察される結果でした。
脳梗塞の社会的リスク因子:精神的ストレスを伴いやすいライフイベント
死別や離婚などの精神的ストレスを伴いやすいライフイベントは脳卒中発症率を上昇させる可能性があるため、注意が必要です。
実際に、本城らの研究では既婚から未婚に変化した男女における脳卒中リスクを解析しており、特に脳出血においてリスク増加が認められました。
(加重ハザード比(95%信頼区間[CI])は男性1.26(1.13~1.41)、女性1.26(1.09~1.45))
本研究では、脳出血のリスクが上がる要因として、死別や離婚によって生じる多大な精神的ストレスや生活習慣の乱れなどが影響すると考えられています。
まとめ
脳卒中の発症予防のためには規則正しい食生活や定期的な運動習慣など、日々の生活習慣の改善が重要です。
さらにこの記事で紹介したように、教育歴やライフイベント、社会的支援の有無など、様々な社会的リスク因子も発症率や死亡率に影響します。
脳梗塞は一度発症すれば麻痺やしびれなどの後遺症が残ってしまう可能性もあるため、原因を把握した上で日々の生活に注意し、発症リスクを下げて予防に徹することが重要です。
一方、近年ではこれまで標準治療では改善困難であった神経学的後遺症に対し、再生医療の効果も大変注目されています。
さらに、神経障害が「治る」を当たり前にする取り組みとして注目されている「ニューロテック®」という考え方があります。
これは、脳卒中や脊髄損傷に対して「狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療」再生医療「リニューロ®」を軸とするアプローチで、骨髄由来間葉系幹細胞や神経再生リハビリ®を組み合わせた治療法です。
後遺症によって日々の生活に苦しむ方に対して、今後このような先進的な治療法が希望となる可能性があります。
よくあるご質問
- 脳梗塞の主なリスク要因は?
- 脳梗塞にとって最大のリスクは動脈硬化であり、その動脈硬化の原因としては高血圧・糖尿病・高脂血症などの生活習慣病や、喫煙・肥満などが挙げられます。
また、心房細動などの心疾患が原因で脳梗塞を発症することもあります。 - 脳梗塞を発症することによる問題点は?
- 脳梗塞によって障害される脳の部位によって、麻痺やしびれ、失語や失認などの高次脳機能障害、構音障害や嚥下障害など、さまざまな神経学的後遺症を残す可能性があります。
これらの後遺症によって歩行や排泄、着衣などの日常生活動作に支障をきたす点が問題です。
<参照元>
(1)Honjo K, et al : Education, social roles, and the risk of cardiovascular disease among middle-aged Japanese women : the JPHC Study Cohort I. Stroke 39 : 2886―2890, 2008.:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18658036/
(2)磯博康:わが国の疫学調査から見えてくる脳卒中の現実 : 日本内科学会雑誌106巻9号 : 1851-1857, 2017.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/106/9/106_1851/_pdf
(3)教育歴と職業における社会的地位の不一致と脳卒中発症リスクとの関連について : 国立がん研究センター:https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/3462.html
(4)Ikeda A, et al : Social support and stroke and coronary heart disease : the JPHC study cohorts II. Stroke 39 : 768―775, 2008.:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18239171/
(5)Honjo K, et al : Marital transition and risk of stroke : How living arrangement and employment status modify associations. Stroke 47 : 991―998, 2016.:https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/strokeaha.115.011926
あわせて読みたい記事:脳梗塞による痛みの治療
外部サイトの関連記事:脳出血と脳梗塞で回復しやすいのはどっち?後遺症と改善の比較



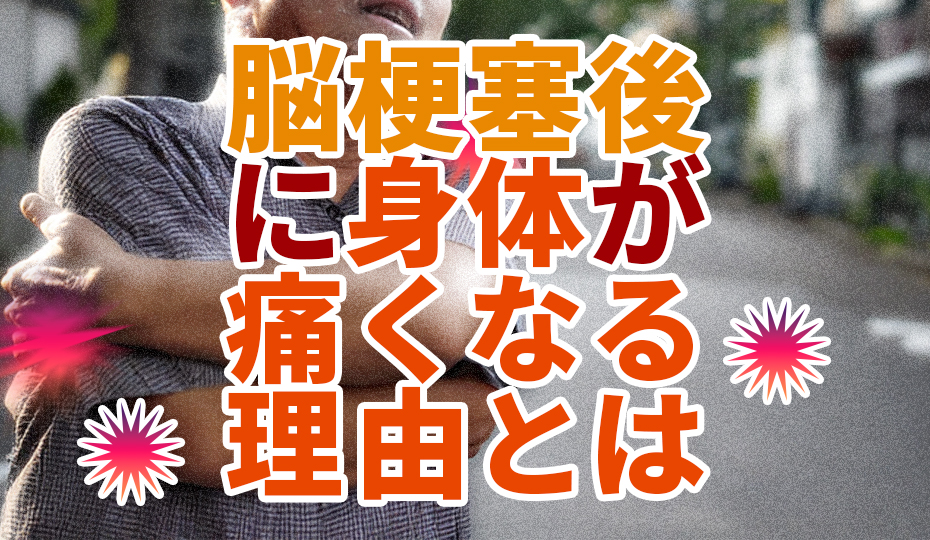
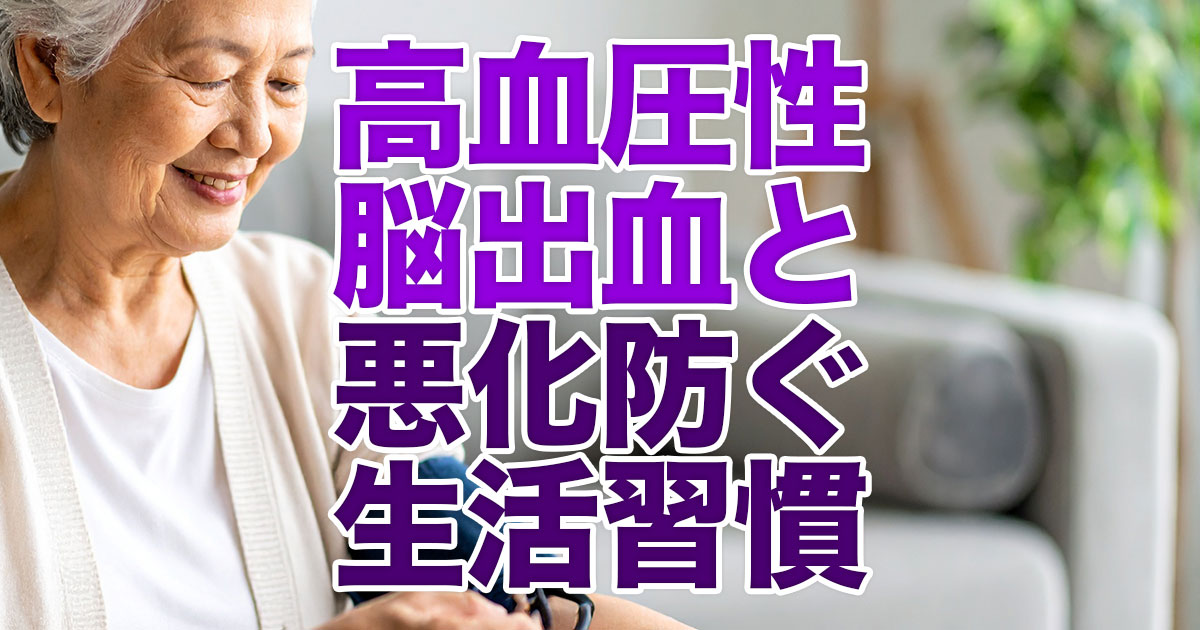












コメント