この記事を読んでわかること
高血圧性脳出血の発症メカニズムとリスクがわかる。
健康診断で高血圧を早期に見つける意義がわかる。
高血圧の見逃されやすい初期症状がわかる。
高血圧性脳出血は、突然発症し命に関わる危険な病気です。
また、後遺症が残ってしまうことも多いです。
症状が出にくい高血圧を早期に発見するためには、定期的な健康診断が重要です。
さらに、減塩や運動など生活習慣を見直すことで、脳出血のリスクを大きく下げることが可能です。
本記事では予防と対策のポイントをわかりやすく解説します。
高血圧性脳出血を防ぐための健康診断の重要性

それではまず、高血圧性脳出血とはどういったものかについて解説します。
高血圧性脳出血の概要
脳梗塞や脳出血、くも膜下出血といった脳血管障害を、脳卒中といいます。
2024年の日本脳卒中データバンク報告書によると、各々の発症の割合は、脳梗塞が約70%、TIA(一過性脳虚血発作)約4%、脳出血が20%、くも膜下出血は5%程度となっています。
脳出血は脳卒中の中では脳梗塞よりも少ない病型ですが、発症後の死亡率は脳梗塞に比べて高く、また中等度から重度の障害を残してしまうことが多いです。
さて、疫学的に、高血圧は脳卒中や、脳卒中を含めた心血管イベントの最大の危険因子とされています。
血圧の値と脳卒中の発症率との関係は深く、血圧が高いほど脳卒中や心筋梗塞などの心血管イベントの発症率が高くなります。
脳出血の原因として、脳動静脈奇形や硬膜動静脈瘻といった血管の異常、さらに脳腫瘍に合併したもの、さらに抗血栓療法に伴う脳出血がありますが、やはり最も多いものは高血圧です。
そのため、血圧を適切な値に保つことは、脳出血を防ぐためにとても大切です。
高血圧を見つけ出すための健康診断の有効性
一方で、高血圧はサイレントキラーとも呼ばれており、かなり高い血圧であっても症状が現れないことも多くみられます。
実際に、健康診断で血圧を測定して、初めて血圧が高いとわかる方も少なくないのです。
健康診断で、高血圧とまではいかないものの、高値血圧という収縮期血圧/拡張期血圧が130−139/80−89mmHgの際には、まずは減塩や食事療法などの生活習慣改善を行います。
そして、3ヶ月後ほどに再評価し、十分に血圧が下がらなければ再び生活を見直します。
しかし、後期高齢者(75歳以上)や、頸動脈の狭窄、脳の主幹動脈の閉塞がある場合、1ヶ月後に血圧を再チェックし、血圧が下がらなければ生活習慣の改善に加え、薬物療法を検討します。
健康診断を受けることで、血圧がやや高めの状態から対応をすることが可能となるのです。
健康診断はおそらく1年に1回から2回受けることが多いかと思われます。
血圧が高めと言われている方は、家庭での血圧も測定しておきましょう。
医療機関での血圧が140/90mmHg以上、家庭での血圧が135/85mmHg以上で、高血圧と診断されます。
こうした血圧を超えてくることが多い場合には、かかりつけ医や内科などで相談をしてみるとよいでしょう。
高血圧の初期症状を見逃さないために知っておくべきこと

高血圧の人のほとんどは、血圧の値が危険なレベルに達しても何の症状も現れません。
しかし、中には以下のような症状がみられることもあります。
- 頭痛
- 息切れ
- 鼻血
また、重症高血圧(通常は、180/120mmHg以上)の際には、このような症状が現れることもあります。
- ひどい頭痛
- 胸痛
- めまい
- 呼吸困難
- 吐き気
- 嘔吐
- 視界のぼやけなどの視覚異常
- 不安
- 混乱
- 耳鳴り
- 不整脈
こうした症状は、高血圧以外にも重大な病気のサインかもしれません。
医療機関を早めに受診しましょう。
脳出血のリスクを減らすための生活改善アドバイス

脳出血の最大のリスクは高血圧です。
高血圧の予防や、高血圧と診断されている場合にも適切に血圧をコントロールすることで、脳出血のリスクを減らすことができると考えられます。
高血圧の予防として、食事、運動などの生活習慣の改善が勧められます。
食事については、以下のようなことを参考にしましょう。
- 1日6g未満の食塩量に減量する
- 低ナトリウム塩を使う
- 果物や野菜を積極的に摂取する
- コレステロールや飽和脂肪酸を控える
- 魚(魚油)の積極的摂取
- 減量(適正体重維持)のための適切なカロリー摂取
- 節酒
取り組みやすいこととして、食事面では「ラーメンやうどんの汁は全て飲み干さないこと」「揚げ物より、蒸す・茹でるといった調理法を多くする」などがあるでしょう。
また、運動習慣が全くない方の場合、まずは1日10分でも多く歩くといったことを意識してみてはいかがでしょうか。
これらのことを意識することで、血圧低下、さらには脳卒中の予防に効果があると示されています。
まとめ
今回の記事では、高血圧性脳出血の予防と、血圧が高くなることで起こりうる症状について解説しました。
高血圧は、それ自体で症状が出ることはほとんどありませんが、まれに重症高血圧の方では症状が現れるケースもあります。
早急に医療機関への受診が推奨される状態です。
一方、高血圧とまでは行かないが、血圧が高めであるといった方は、健康診断で血圧を測定して初めてわかるという場合も多いです。
早めに減塩、体重維持などの生活習慣を改善することにつながりやすくなるといった意味でも、健康診断は重要であるといえます。
万が一脳出血などの脳卒中を発症してしまった場合には、生命を落としてしまうこともあります。
また、生命が救われても、手足の麻痺や言葉の問題など、後遺症が残ってしまう方もみられます。
そうした方にとっては、リハビリテーションが機能回復に大きな意味を持ちます。
なお、万が一脳卒中を発症し、後遺症が残った場合には、早期のリハビリ介入が大切です。
最近では、再生医療を組み合わせた先進的なリハビリ治療も始まっています。
ニューロテック、脳梗塞脊髄損傷クリニックなどでは、脳卒中・脊髄損傷を専門として、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。
リニューロ®では、同時刺激×神経再生医療®、骨髄由来間葉系幹細胞を用いて狙った脳や脊髄の治る力を高めた上で、神経再生リハビリ®を行うことで神経障害の軽減を目指します。
リハビリテーションと再生医療の組み合わせにご興味がある方は、HPをご覧になってみてください。
よくあるご質問
- 脳出血の前兆チェックリストはありますか?
- 脳出血の前兆として、急な片側のしびれや脱力、言葉が出にくい、視界の異常、ふらつき、激しい頭痛などが挙げられます。
これらの症状が突然起こった場合は、早急な受診が必要です。
「いつもと違う感覚」があれば、迷わず医療機関を受診しましょう。
- 脳の血管に良い飲み物は?
- 血圧を安定させ、脳血管の健康を保つには、緑茶やルイボスティー、カカオ含有量の高いココアなどがおすすめです。
いずれも抗酸化作用や血管拡張作用があり、日常的に取り入れやすい飲み物です。
ただし、糖分の多い清涼飲料水や過剰なアルコール摂取には注意しましょう。
<参照元>
(1):日本脳卒中データバンク報告書 2024年:https://strokedatabank.ncvc.go.jp/
(2):脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕:https://www.jstage.jst.go.jp/article/numa/82/6/82_325/_pdf
(3):高血圧治療 ガイドライン2019.日内会誌;109:778-783.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/109/4/109_778/_pdf
(4):High blood pressure (hypertension) – Symptoms & causes – Mayo Clinic:https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410
(5):Hypertension|WHO:https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension
あわせて読みたい記事:脳出血予防に効果的な食生活とミネラル習慣
外部サイトの関連記事:脳出血に関わるセルフチェックとは



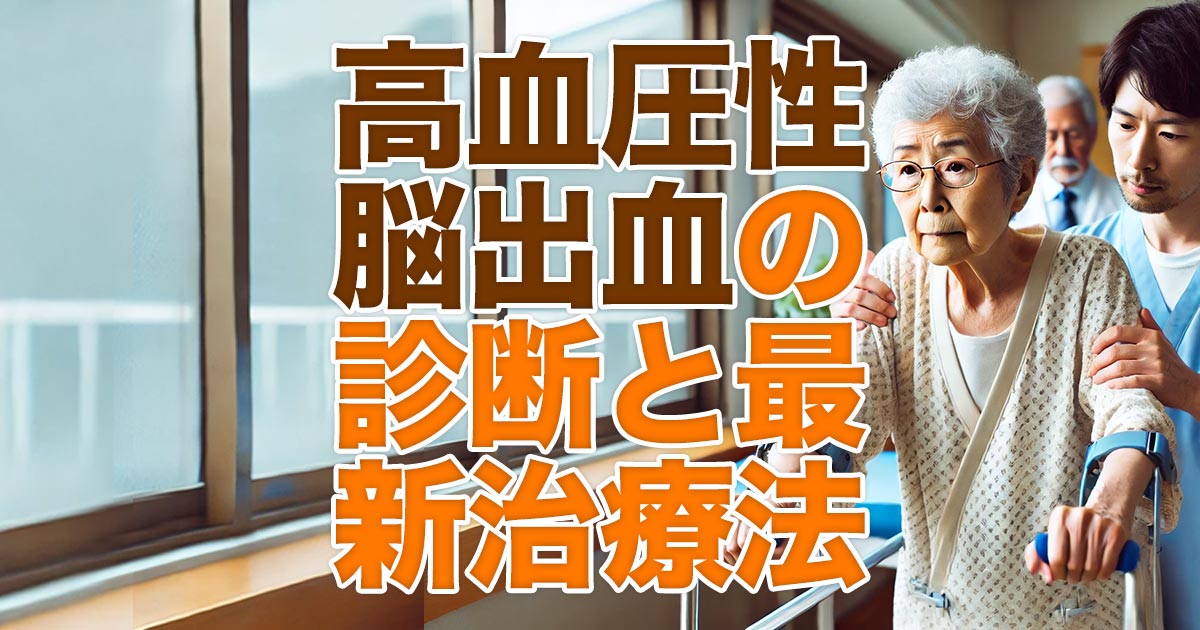
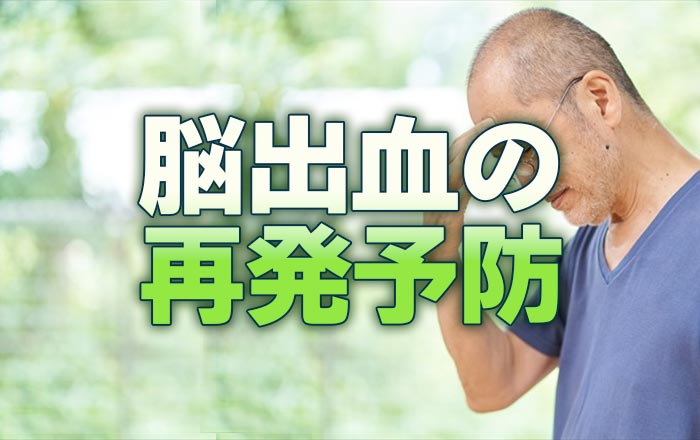












コメント