頸髄損傷原因と初期から見られる症状
四肢麻痺の評価の仕方と予後予測方法
リハビリテーションの開始時期と方法
頸椎損傷とは背骨の中でも首に当たる部分の骨折です。
頸椎を骨折することで背骨の中を通っている脊髄が損傷し四肢に麻痺が出現することがあります。
この状態を頸髄損傷といい、日常生活に戻るためにリハビリテーションを行う必要があります。
この記事では頸椎損傷による四肢麻痺の原因からリハビリテーションまで解説します。
頚椎損傷の原因と初期症状
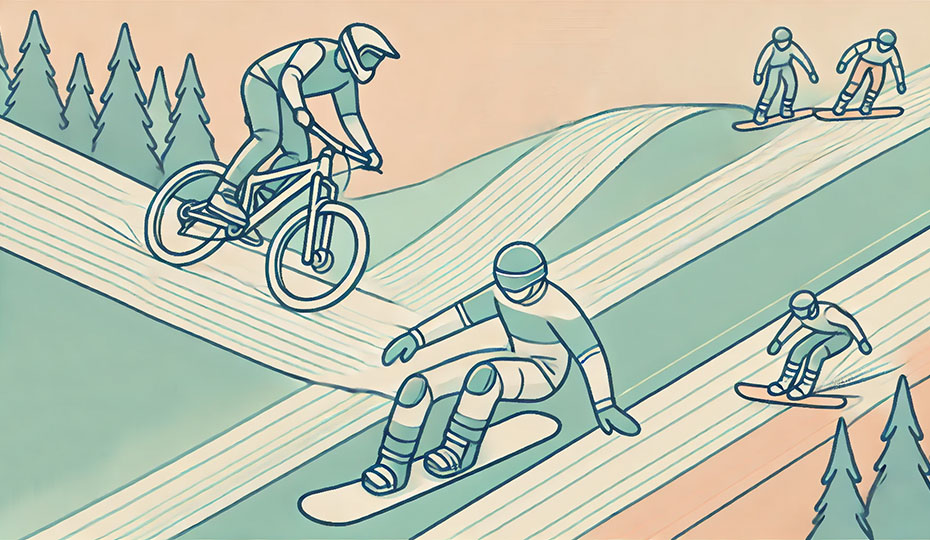
頸椎損傷とは背骨の中の首に当たる部分の骨が損傷、つまり骨折した状態のことです。
頸椎を損傷した際に背骨の中を通っている脊髄神経を同時に損傷することが大きな問題になります。
頸椎を通っている脊髄神経は頸髄と呼ばれ、頸髄損傷は首の部分の神経を損傷した状態で、四肢の運動麻痺や感覚の麻痺、自律神経などの障害が出現する疾患です。
原因は外傷性が最も多く、世代によって原因が変わります。
高齢者では転倒、低所からの転落、交通事故の順に多く、若い世代ではスポーツ、交通事故、高所からの転落が多くなっています。
高齢者は筋力や体力の低下によって、若年者よりも転倒しやすい状況にあり、加えて頸椎に後縦靱帯骨化症などの変性疾患を抱えていることも珍しくありません。
そのため、転倒した際に頸髄がダメージを受けやすく、転倒による頸髄損傷の発症が多いと考えられています。
若年者はそもそもの転倒が少ないことに加え、頸椎の問題を持っている方も少ないため、交通事故やスポーツなどの高いエネルギーが加わる外傷が原因となります。
それぞれの内容では、交通事故は自動車、バイク、自転車の事故の順に多く、スポーツではスキーが最も多く、自転車競技、スノーボードと続きます。
これらの交通事故やスポーツは速いスピードが出ている状況での衝突や転倒が発生しやすいため、頸髄損傷の原因となりやすいことがわかります。
頸椎損傷に伴う頸髄損傷は初期症状として手足のしびれなどの異常感覚や運動麻痺が出現します。
転倒や事故後すぐに症状が現れ、症状が改善しないことが特徴です。
また、頸椎の上から数えて3番目までの高さの神経を損傷した場合は呼吸困難感が出現し、重症例では呼吸が停止してしまうこともあります。
3番目までの頸髄は呼吸を行うための筋肉に指示を出しており、損傷することで呼吸筋に対する命令が止まってしまうために呼吸症状が出現します。
これらの症状が出現した際はできるだけ早く病院を受診することが大切です。
特に呼吸器症状がある場合は必ず救急車を呼び、適切な対応を行う必要があります。
四肢麻痺の程度と予後の見通し
脊髄損傷には障害の重症度をASIA Impairment Scale(AIS)という方法で分類します。
この分類はA〜Eまでの5段階で重症度を分類し、Aが最も障害が重く、Eが最も軽いことを示します。
AISでAの状態は運動機能と感覚機能が完全に機能を失ってしまっている状態です。
Bは感覚機能は少し残存しており、運動機能は失っている状態です。
Cは運動機能が大きく低下した状態、Dは運動機能が低下した状態、Eは運動機能および感覚機能が低下していない状態です。
発症時のAISがAの場合、B〜Dまでの不全麻痺まで改善する割合は約10〜15%とされています。
また、発症時のAISがBでは1年後に1/3がC、1/3がDへ移行するとされており、発症時がCであれば1年後は2/3がDまで改善するとの報告があります。
AISが改善する時期は発症から約3ヶ月までに80%が改善するとされています。
若年者と高齢者を比較した場合は、AISがAなどの重症例であれば高齢者の方が改善しやすく、Cなどの中等度から軽症例に関しては若年者の方が改善しやすいと報告されています。
高齢者の受傷機転が転倒などの衝撃が少ないことが多い点が重症例の改善に関係しているとされており、逆に軽症例に関しては高齢化に伴う筋力低下の影響があるのではないかと考えられています。
このように、頸髄損傷後の運動機能は発症した際のAISのスコア、受傷機転、年齢などによって改善度合いが変わることが多く、個別的なリハビリテーションのアプローチが必要です。
リハビリ開始のタイミングと方法
頸髄損傷におけるリハビリテーションは、できるだけ早期から開始します。
まずはベッド上で呼吸リハビリテーションやポジショニング、関節可動域運動などを行い、肺炎や褥瘡などの合併症を引き起こさないようにします。
頸椎の骨折部が手術やコルセットによって安定すれば、車椅子への移乗練習や下肢の能力が保たれている場合は起立練習や歩行練習を行います。
これらのリハビリを行う前にはAISなどの評価スケールを使用して、状態を把握することが非常に重要です。
現状の状態を把握した上で、今後どのような身体機能・生活能力を上げることができるかを予測しながらリハビリテーションを進めます。
頸髄損傷のリハビリテーションは他の疾患とは違い、特異的な動作方法を習得する必要があります。
そのため、離床が開始になれば、今後車椅子生活をされる方は肩周りのストレッチを重点的に行い、歩行で生活をされる方は下肢の筋力トレーニングや歩行練習を積極的に行います。
残存している部位の筋力や柔軟性を向上させることは非常に重要であり、急性期や回復期病院でしっかりと体力・筋力をつけることが重要です。
退院が近づけば、実際に家で使う動作の練習を重点的に行い、退院に備えます。
退院後は訪問リハやデイケアなどを利用しながら、生活を少しでも楽に行えるようにリハビリを継続します。
頸髄損傷後、自宅や施設での自立した生活を取り戻すためにはリハビリテーションをしっかりと行うことが重要です。
まとめ
この記事では、「頚椎損傷での四肢麻痺による早期対応とリハビリの重要性」について解説しました。
頸椎損傷は事故や転倒によって多く発生し、初期症状としてしびれや感覚障害、運動麻痺が出現します。
四肢麻痺はAISを使用して評価され、AIS使用することで今後の身体機能を予測することができます。
リハビリは早期から開始し、頸髄損傷に特化した日常生活動作の獲得を目指します。
頸髄損傷で神経を損傷してしまった後の脊髄神経の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。
今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。
私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。
当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。
よくあるご質問
- 脊髄損傷後のリハビリの効果とは?
- 脊髄損傷後は四肢が麻痺し、自由に動かすことができなくなります。
そのため、今まで通り歩いたり日常生活を送ることが難しくなります。
リハビリテーションを行うことによって、損傷度合いに応じた日常生活を獲得することができます。 - 脊髄損傷の急性期の症状は?
- 脊髄損傷の初期症状はしびれや感覚障害、運動障害を認めます。
頸髄の高いレベルを損傷した場合は呼吸器症状が出現することがあり、命に関わることがあるため、できる限り早急な対応が求められます。
<参照元>
(1)A nationwide survey on the incidence and characteristics of traumatic spinal cord injury in Japan in 2018:https://www.nature.com/articles/s41393-020-00533-0
(2)脊髄損傷者のリハビリテーション医療における帰結予測|J -stage:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrmc/56/7/56_56.537/_pdf/-char/ja
(3)理学療法ガイドライン第2版:https://cms.jspt.or.jp/upload/jspt/obj/files/guideline/2nd%20edition/p107-129_02.pdf
関連記事
このページと関連のある記事

2024.08.16
頸椎損傷の予後を改善するためのリハビリとは
頸椎損傷のリハビリテーション戦略と幹細胞治療の相乗効果について解説します。頸椎損傷は日常生活に深刻な影響を与えますが、効果的なリハビリテーションによって生活の質を向上させることができます。筋力強化やバランストレーニング、心理的サポートが回復を支え、幹細胞治療との併用でより高い効果が期待されます。...
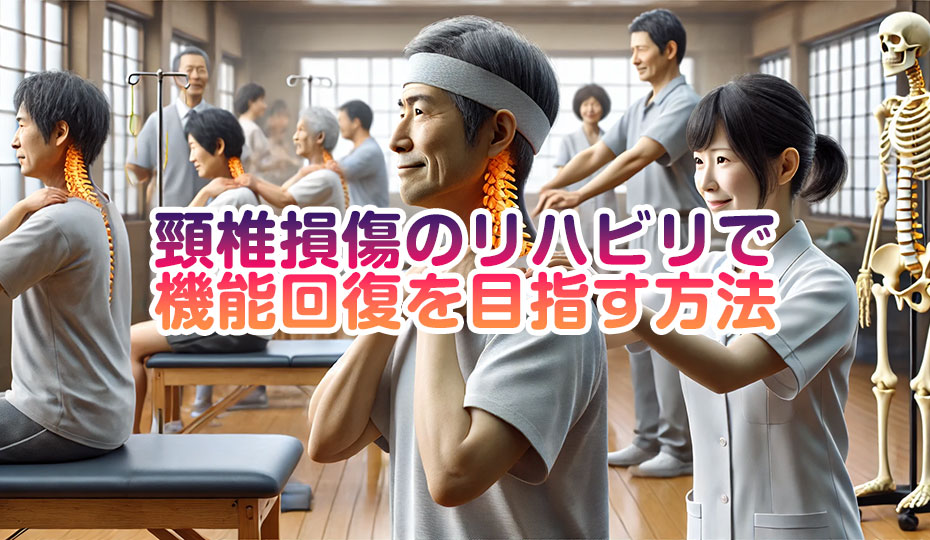
2024.08.02
頸椎損傷のリハビリテーションで機能回復を目指す方法
頸椎損傷のリハビリは機能回復の鍵を握ります。再生医療と動作の反復訓練を組み合わせることで、神経回路の強化・再構築が促され、治療効果の最大化が期待できます。本記事では、頸椎損傷のリハビリの基本から注意点、再生医療の可能性まで詳しく解説し、患者の生活の質向上に向けた最新の治療法について紹介します。...
















コメント