急性期に行うべき早期離床の必要性
関節可動域運動とポジショニングの重要性
廃用症候群を防ぐための方法
脳卒中を発症すると障害部位によって片麻痺が出現します。
一般的に脳卒中後の片麻痺の回復過程は弛緩性から痙性麻痺へ移行し、徐々に改善していきますが、人によって回復過程は異なります。
特に発症早期は弛緩麻痺が発症しやすく早期からの対処が重要です。
この記事では弛緩性麻痺のリハビリ初期と動けない時期の対応法について解説します。
急性期にやるべき“刺激入力”と“寝たきり予防”
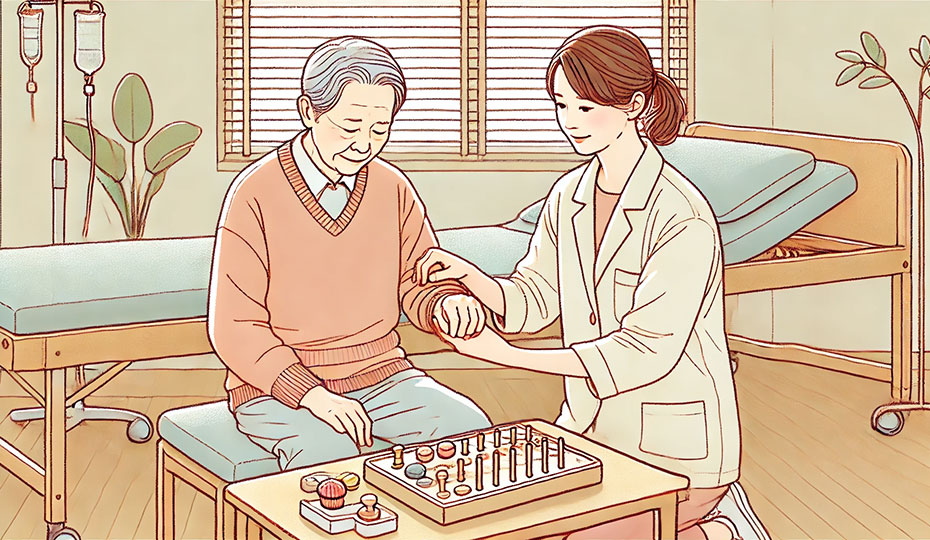
脳卒中を発症し、錐体路と呼ばれる神経の通り道を大きく損傷すると弛緩性麻痺という四肢の力が抜けるような麻痺を発症します。
弛緩性麻痺を発症すると、上下肢への力が入らないため日常生活動作に大きな影響を与えます。
特に発症早期は身体への影響が大きく寝たきりになってしまうことが多くあります。
このような発症早期でのリハビリテーションでは、弛緩性麻痺が起こっている上下肢への感覚刺激の入力と寝たきりを予防するためにできるだけ早くベッドから離れることが重要になります。
上下肢への感覚入力とは、麻痺肢を触ったりするのみではなく、早期から起立などの荷重感覚を入力することが重要とされています。
錐体路を損傷すると、脳からの命令が遮断されてしまい四肢への運動の命令が伝わらないため、弛緩性麻痺を発症します。
しかし、運動は脳からの命令だけで起こるものではなく、感覚刺激の入力によって起きる運動もあります。
例えば、筋肉に対して引き伸ばされるような刺激を入力した場合、感覚繊維が脊髄で運動神経に連絡を行い、脳を介さない反射を使用して運動を行います。
この原理を応用し、荷重感覚を麻痺肢に入力することで感覚刺激を使用して麻痺肢に運動のきっかけを与えることができます。
弛緩性麻痺ではまず筋肉を動かす経験をさせて、少しずつ力が入るようにすることが重要なため、感覚刺激を入力し筋肉の収縮を促すことは非常に重要です。
寝たきりの予防のためにベッドから離床することは脳卒中早期で最初に行うリハビリテーションです。
弛緩性麻痺を発症している脳卒中患者は自分の力で動くことができないため、合併症を発症しやすいとされています。
早期から離床を行うことで代表的で致死的な合併症である深部静脈血栓症と誤嚥性肺炎を予防することができます。
急性期では早期から感覚刺激入力と離床を積極的に行うことが重要です。
可動域訓練とポジショニングの重要性
弛緩性麻痺は関節拘縮を起こしやすく、拘縮を起こさないための工夫を行うことは重要です。
弛緩性麻痺を発症すると自ら関節を動かすことが難しいため、リハビリなどで関節を動かしていないと、少しずつ関節周囲の筋肉や靱帯、脂肪などの軟部組織が変性し関節の拘縮を引き起こします。
特に発症すぐの急性期では自分で動くことが難しい方も多く、関節拘縮を引き起こしやすいとされています。
急性期で拘縮ができてしまうと、回復期でのリハビリの阻害因子になることも多く、拘縮を予防することが重要です。
そのため、リハビリでは急性期の発症早期のベッド上運動から他動的に関節を動かす可動域訓練を行うことが必要です。
また、急性期では拘縮を作らないためにポジショニングを行うことも重要です。
各関節には拘縮を起こしやすい運動方向が決まっています。
例えば、股関節や膝関節であればに拘縮しやすいなどそれぞれの関節によって関節が硬くなりやすい方向があります。
また、同一姿勢を取り続けると骨突出部に褥瘡ができてしまうこともあります。
急性期で自分で寝返りができない時期は関節拘縮や褥瘡ができないように適宜看護師やセラピストなどの医療職によってポジショニングを行います。
クッションやタオルなどを使用してポジショニングを行い、同一体位を取り続けないように気をつけます。
時間は2−3時間に一度、姿勢を変えることが望ましいとされています。
急性期は発症早期から拘縮・褥瘡予防に関節可動域運動とポジショニングを行うことが重要です。
廃用症候群を防ぐための早期介入とは?
脳卒中発症直後は弛緩性麻痺によってベッド上で寝たきりになってしまうことがあります。
1日寝たきりになると筋力は2%程度低下してしまうことが知られていますが、脳卒中では神経が障害されているため、さらに大きく筋力低下を起こします。
これらの動かないことによって生じる身体機能と精神機能の低下を廃用症候群といいます。
廃用症候群はできるだけ早期から離床することで発症を予防することができます。
廃用症候群の予防には発症早期から全身状態に注意しながらできるだけ早く車椅子に乗り、可能であれば荷重練習を行うことが必要です。
弛緩性麻痺に加えて、非麻痺側の筋力低下が起きてしまうと改善まで非常に長い期間がかかります。
筋力は一度低下してしまうと改善まで時間がかかりますが、維持することは離床や起立練習などである程度可能です。
そのため、廃用症候群はできるだけ予防することが重要です。
急性期ではできるだけ早期に離床や荷重練習を行うことで廃用症候群を防ぐためのリハビリテーションを行います。
まとめ
この記事では弛緩性麻痺のリハビリ初期〜動けない時期の対応法について解説しました。
急性期では刺激入力”と寝たきり予防を行うことが重要です。
また、関節の拘縮や褥瘡を発生させないための早期介入や、廃用症候群を予防するための早期からの離床を行う必要があります。
脳卒中で神経を損傷してしまった後の脳の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。
今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。
私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。
当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。
よくあるご質問
- 弛緩性麻痺は回復しますか?
- 脳卒中を発症し片麻痺を認める際に錐体路を障害されると弛緩性麻痺が出現します。
弛緩性麻痺は徐々に筋緊張が上がり、痙性麻痺へ移行することが多いとされています。
しかし、中には弛緩性麻痺のまま経過する方もいます。 - 運動障害の弛緩性麻痺とは?
- 弛緩性麻痺とは神経の通り道の中でも錐体路と呼ばれる部分に重度のダメージを受けた場合に発症する麻痺症状のことをいいます。
症状としては力が入らず、筋緊張の低下している麻痺が出現します。
<参照元>
(1)感覚入力への介入による運動リハビリテーション|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/sicejl/56/3/56_199/_pdf
(2)脳卒中治療ガイドライン:https://www.jsnt.gr.jp/guideline/img/nou2009_07.pdf
関連記事
このページと関連のある記事
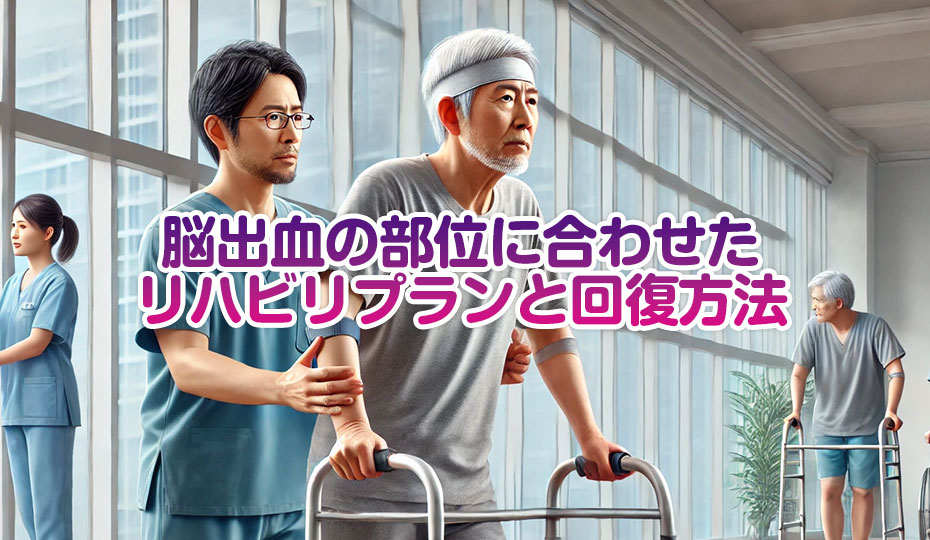
2025.03.01
脳出血の部位に合わせたリハビリプランと回復方法
脳出血では出血した部位によって様々な障害が出現します。出血の好発部位は被殻・小脳・視床が挙げられ、それぞれ出現する症状に違いがあります。被殻では運動機能、小脳では平衡機能、視床では感覚機能が問題になります。この記事では、被殻・小脳・視床の3つの脳出血好発部位それぞれにおける症状とその治療方法について...

2024.02.27
脊髄損傷急性期のリハビリテーション
脊髄損傷は脊柱管の中にある脊髄が、何らかのきっかけで障害を受けてしまう疾患です。後遺症としては手足の麻痺や膀胱直腸障害があり、生活・人生に大きな影響を与えます。脊髄損傷では合併症を防ぎ、回復期へ繋ぐことが重要です。この記事では脊髄損傷急性期のリハビリテーションについて解説します。...
















コメント