・脳梗塞後のリハビリで寝たきりを防げる理由
・リハビリの開始時期が寝たきりのリスクに与える影響
・寝たきりを防ぐリハビリメニュー
脳卒中は要介護の原因2位であり、寝たきりになるリスクは非常に高い疾患です。
脳梗塞後に早期からリハビリを開始することで合併症を防ぎ、活動量を増やすことが寝たきりを防ぐために重要とされています。
この記事では、リハビリを早期から行う理由や寝たきりを防ぐためのリハビリメニューについて解説します。
脳梗塞後のリハビリで寝たきりを防ぐ方法

我が国における要介護になる原因疾患の1位は認知症、2位は脳卒中となっています。
認知症は直接寝たきりになる疾患ではないため、寝たきりになる疾患として最も多い疾患は脳卒中になることが推察されます。
脳梗塞が起きた場合、詰まった脳血管の場所や大きさなどによって起きる障害は様々です。
特に大きな血管が詰まってしまうと身体に重度の麻痺症状が出現し、身体を動かすことが難しくなり寝たきりの原因になります。
重度の障害のある脳梗塞患者が寝たきりを防ぐ鍵はリハビリを行うことが重要になります。
脳梗塞後に片麻痺などの身体障害が出る以外に廃用症候群と呼ばれる身体機能低下が起こることがあります。
廃用症候群とは臥床などによって動く頻度が減少した際に心身に起こる機能低下のことを指します。
脳梗塞を発症した後に今までの生活より活動量が減り、廃用症候群を引き起こすことでより活動量が減るなどの負のスパイラルを起こしてしまうことがあります。
この負のスパイラルに入ると寝たきりになる確率が上がってしまいます。
そのため、脳梗塞になった後はリハビリを行って臥床時間を減らし、活動量を上げながら生活を行うことが寝たきりを防ぐために重要です。
リハビリ開始時期が寝たきりリスクに与える影響とは?
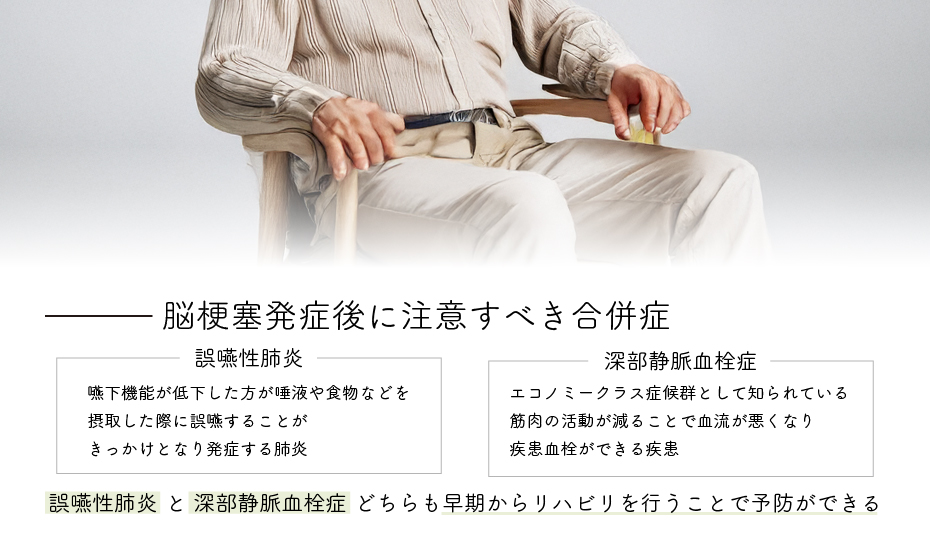
脳梗塞を発症してからリハビリを開始する時期によって、機能回復に差が出ることは過去の研究によって明らかになっています。
そのため、リハビリの開始時期は発症後できるだけ早期にリハビリを始めることが推奨されています。
発症後すぐにリハビリを開始することで身体機能や日常生活動作の回復を促進し、活動量を上げることで寝たきりのリスクを減らすことができます。
また、脳梗塞発症後すぐは様々な合併症を起こしやすいとされています。
特に注意が必要な合併症は誤嚥性肺炎と深部静脈血栓症です。
誤嚥性肺炎とは嚥下機能が低下した方が唾液や食物などを摂取した際に誤嚥することがきっかけとなり発症する肺炎です。
脳卒中を発症した患者のうち2割程度の方が誤嚥性肺炎を発症すると言われており、発症直後のリハビリの障害となります。
深部静脈血栓症とは一般的にエコノミークラス症候群として知られている疾患です。
臥床や麻痺によって筋肉の活動が減ることで血流が悪くなり、血栓ができることがあります。
血栓ができると下肢が浮腫み痛みが出ることもありますが、最も恐ろしいことは血栓が血流に乗ってしまい、肺に達することで発症する肺塞栓症です。
肺塞栓症になると急激な呼吸不全を起こし、時には命に関わることもあります。
また、臥床期間が長くなってしまうため寝たきりになるリスクが上がります。
そのため、深部静脈血栓症は予防が重要とされています。
誤嚥性肺炎と深部静脈血栓症のどちらも早期からリハビリを行うことで予防ができます。
合併症予防を行うことで寝たきりのリスクを下げることもリハビリの重要な点です。
寝たきりを回避するために必要なリハビリメニュー
寝たきりを回避するために必要なリハビリメニューは発症してからの時期によって変わります。
発症直後の急性期ではまず車椅子に乗るなど積極的にベッドから離れることが重要です。
可能な方は歩行練習を行い、ご自身の力で歩けない方は装具なども併用しながら歩行練習を行います。
全身状態が落ち着きリハビリテーション病院へ転院した後は、身体機能と日常生活動作能力を上げるようなメニューを行います。
リハビリで麻痺自体を改善することは難しいと言われていますが、発症から半年までは麻痺の改善を認めやすく、リハビリで積極的に運動を行うことで麻痺の改善の促進を行うことができます。
また、早い時期から日常生活動作の練習を行い、病棟内での活動量を増やすことも重要です。
自宅に退院された後の生活期では、できるだけ生活の自立ができるように日常生活動作の練習を行ったり、環境を整えます。
リハビリテーション病院を退院した後は、理学療法士などのリハビリ専門職と関わる機会が減ってしまうため、自宅であまり動かなくなってしまう方も多数います。
しかし、自宅での活動量が減ってしまうと寝たきりのリスクは上がるため、できるだけご自身で動けるように動作の練習を行い、手すりなどの環境を整えて活動量を確保することが重要です。
脳梗塞後は常に寝たきりのリスクはあるため、どの時期でも活動量を保ち、身体機能や日常生活動作能力を維持・向上できるようにしましょう。
まとめ
この記事では、寝たきりを回避するための脳梗塞リハビリのポイントについて解説しました。
脳梗塞後はできるだけ早くリハビリを開始し、合併症を防ぎながら活動量を向上させることが寝たきりのリスクを減らす重要な手段になります。
脳梗塞で神経を損傷してしまった後の脳の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。
今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。
私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。
当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。
よくあるご質問
- 寝たきりにならないようにするにはどうしたらいいですか?
- 脳梗塞を発症した後できるだけ早期からリハビリを行い、合併症の予防や活動量の確保を行うことが重要です。
また、急性期以降も積極的にリハビリを行い、身体機能や日常生活動作能力を改善することも大切です。 - 脳梗塞のリハビリで回復するのはなぜ?
- 脳梗塞は発症後6ヶ月までの間に神経の機能が改善するとされています。
この期間中にリハビリを行うことで、ダメージを受けた神経細胞の代わりに新しい神経ネットワークが再建されると考えられています。
<参照元>
・リハビリテーション|脳卒中治療ガイドライン:https://www.jsnt.gr.jp/guideline/img/nou2009_07.pdf
・理学療法ガイドライン第2版|日本神経理学療法学会:https://cms.jspt.or.jp/upload/jspt/obj/files/guideline/2nd%20edition/p001-106_01.pdf
関連記事
このページと関連のある記事

2024.10.10
脳出血後の片麻痺を乗り越えるためのリハビリとは
脳出血後の片麻痺を改善するためのリハビリ方法を詳しく解説。片麻痺とは身体の半分が麻痺してしまい動かせなくなってしまう状態のことを言います。右の脳は左半身を、左の脳は右半身を制御しており、脳の片側に障害があるとその反対側の身体に麻痺が生じます。片麻痺と向き合う方々が前向きに取り組むための情報をお伝えし...

2024.09.24
廃用症候群の効果的なリハビリと運動の重要性
廃用症候群の効果的なリハビリや運動の重要性について解説します。廃用症候群は長期の安静で筋肉や骨が萎縮し、心身に悪影響を及ぼす状態です。廃用症候群を放置すれば悪循環に陥り、最悪の場合寝たきりに陥ってしまうため、状態改善のためには早期から適切な食事と、適切な負荷のリハビリが肝要です。...




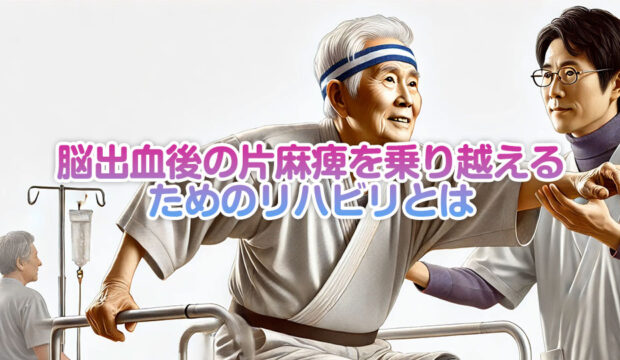











コメント