・絞扼性神経障害の病態
・手根管症候群による正中神経障害の症状と巧緻動作の関係
・手根管症候群の治療方法
絞扼性神経障害とは、身体にあるトンネルを神経が通過するときに圧迫されることでしびれや痛み、手指の脱力などの麻痺症状が出現する神経の障害のことです。
特に手根管症候群によって発症する正中神経障害では手の巧緻動作が障害されることがあります。
この記事では、正中神経障害の病態から治療、リハビリテーションまで解説します。
目次
絞扼性神経障害による手の巧緻性低下の原因とリハビリ治療

絞扼性神経障害とは、脊髄から分かれて出てきた神経が身体の一部にある隙間を通る際に圧迫されて起きる神経の障害のことをいいます。
また、手の巧緻性とは手先や指先を器用に使用する能力のことです。
絞扼性神経障害には様々な種類がありますが、手の巧緻性低下の原因となる疾患では手根管症候群があります。
手根管症候群の治療は手術療法と保存療法がありますが、どちらの治療方法でもリハビリ治療は重要になります。
絞扼性神経障害が引き起こす手の麻痺や巧緻性の低下
絞扼性神経障害では圧迫されている神経の種類によって出現する症状や部位が変わります。
なかでも、手の麻痺や巧緻性の低下を引き起こす疾患として手根管症候群があります。
手根管症候群は手の付け根にある手根管という骨と横手根靱帯で構成されたトンネルが圧迫されることによって生じる正中神経障害のことです。
手根管症候群による正中神経麻痺は最も頻度の高い末梢神経障害であり、有病率は約4%であり女性が男性と比較して3〜10倍発症しやすいとされています。
原因は手根管というトンネルが手を上下に動かした際の物理的な負荷によって圧迫されることや、手根管内の要因(骨折や腫瘍など)、神経脆弱性(糖尿病性神経障害など)、全身性要因(浮腫や妊娠など)があります。
女性が発症しやすい理由は妊娠中や閉経後に発症しやすい点から女性ホルモンとの関係があるのではないかと言われています。
症状は親指〜薬指までのしびれや痛み、手の筋肉の脱力や筋萎縮・麻痺症状を認めます。
手根管症候群によってしびれや痛みが出現すると、手指本来の感覚が障害され手指の細かい動作を要求される巧緻動作が障害されます。
また、運動神経の圧迫によって筋肉の脱力や筋萎縮・麻痺症状が起こると指を思った通りに動かすことができず、手の巧緻性は低下してしまいます。
正中神経麻痺と手の動き:巧緻性に与える影響とは?
正中神経麻痺を発症すると上述のようなしびれ、痛み、脱力、筋萎縮、麻痺などの症状を認めます。
手指の巧緻動作は脳から脊髄神経、末梢神経を通り細かい運動の命令を指先に送ることで行われていますが、逆に指先からは運動した際の感覚やかなり繊細な指の触れた感覚などの情報を末梢神経から脊髄神経に戻し、脳まで送っています。
このように手指の巧緻動作を行うためには脳からの一方的な命令のみでなく指先の感覚が非常に重要です。
しびれや痛みなどの異常感覚があると指先の繊細な感覚は障害され、文字を書くなどの細かい動作は本来の動作を行うことが難しくなってしまいます。
さらに、脳からの命令はかなり細かい指令が出ているため、手指の筋肉の脱力や筋萎縮、麻痺症状などで少しでも正常に動くことが難しくなると、巧緻動作は行えなくなります。
このように手指の巧緻動作はかなり繊細なものであり、少しの感覚障害や運動障害でできなくなってしまいます。
絞扼性神経障害の治療法とリハビリで手の機能を回復させる

絞扼性神経障害の治療方法は主に手術療法と保存療法があります。
手術療法は一般的に「重症例」もしくは「保存的治療で改善が得られない場合」に選択することになります。
重症例もしくは保存療法で改善が得られない場合の例としては、4〜8週の保存療法で効果がない場合、日常生活に影響を与えるような巧緻動作の障害(特につまみ動作)、透析によるタンパク質沈着や腫瘍などの手根管内の病変などが挙げられます。
保存療法では疼痛が強い場合ステロイドの内服や手根管内への注入、疼痛が軽度である場合は手首を安静にし経過を観察します。
手根管症候群による正中神経麻痺は未治療で35%が改善すると言われています。
そのため、重症化しない場合は経過観察で改善することもしばしばあります。
しかし、ステロイド治療や経過観察のみでは十分に症状が改善しないこともよくあります。
その際はスプリントの使用やリハビリテーションを行います。
スプリントとは手首に使用する装具のことで手首の固定を行うことで腱を安静にし、神経の圧迫を取り除く治療です。
夜間だけ使用する方法と一日中使用する方法があります。
リハビリテーションは手術療法と保存療法のどちらを行った場合でも適応があります。
具体的な方法としては、麻痺や筋力低下によって動かしづらくなっている手首や手指のストレッチや関節可動域練習、手指と手首の筋力トレーニングなどを行います。
さらに腱と神経の滑りをよくするための運動や手指の動作練習としてペグなどを使用し巧緻動作練習を行います。
他の治療方法とリハビリテーションを併用して行うことでより高い治療効果を期待することができます。
まとめ
この記事では絞扼性神経障害による手の巧緻性低下の原因とリハビリ治療について解説しました。
絞扼性神経障害の中でも手根管症候群による正中神経障害は手の巧緻性低下を引き起こします。
巧緻性低下の原因はしびれや疼痛、脱力や筋力低下などの症状が作用し合い起こります。
治療方法は手術療法と保存療法がありますが、リハビリテーションを併用するとより効果的です。
手根管症候群は比較的治りやすいと言われている疾患ですが、時には後遺症が残ってしまうことがあります。
後遺症による巧緻性動作の治療方法は現在確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。
今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。
私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。
当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。
よくあるご質問
- 手巧緻運動障害とは?
- 手巧緻運動とは、手指を器用に使用し細かい動作を行うことを指します。
脳や末梢神経の障害によって巧緻動作が上手く行えなくなることを手巧緻動作障害といいます。
手巧緻動作障害が出現すると日常生活で不便を多く感じてしまい、重症化すると介助が必要になってしまいます。 - 絞扼性神経障害の症状は?
- 絞扼性神経障害は身体の様々な部位にあるトンネルを神経が通過する際に圧迫されて起こる障害です。
症状はしびれ、痛み、弛緩性麻痺などがあり、部位によっても変わります。
正中神経障害では、上記の症状が原因となり巧緻動作障害が出現することがあります。
<参照元>
・標準的神経治療:手根管症候群:https://www.jsnt.gr.jp/guideline/img/syukonkan.pdf
・手根管症候群の保存療法における徒手理学療法に関する文献調査―理学療法ガイドライン第 2 版からの検証―:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmpt/23/1/23_59/_pdf/-char/ja
関連記事
このページと関連のある記事

2024.05.21
リハビリテーションで麻痺から復活する可能性
脳出血、脳梗塞により麻痺症状が出現します。発症後、早期よりリハビリテーションを行い、廃用症候群の予防に努め、病状が安定したら積極的にリハビリを実施していきます。退院後も身体機能が落ちないように継続的なリハビリを行えることが望ましいです。この記事では、発症からの時期に応じたリハビリについて紹介していま...

2023.10.23
脊髄損傷後の機能回復とリハビリテーションの関係
脊髄損傷は、従来は回復が難しいとされていました。しかし近年の再生医療の進歩により、幹細胞治療による神経修復が期待されています。幹細胞を体内に再注入することで損傷部位の回復を促し、リハビリと組み合わせることでより高い治療効果を目指します。脊髄損傷に対する幹細胞治療の効果や、リハビリ・感染予防対策につい...

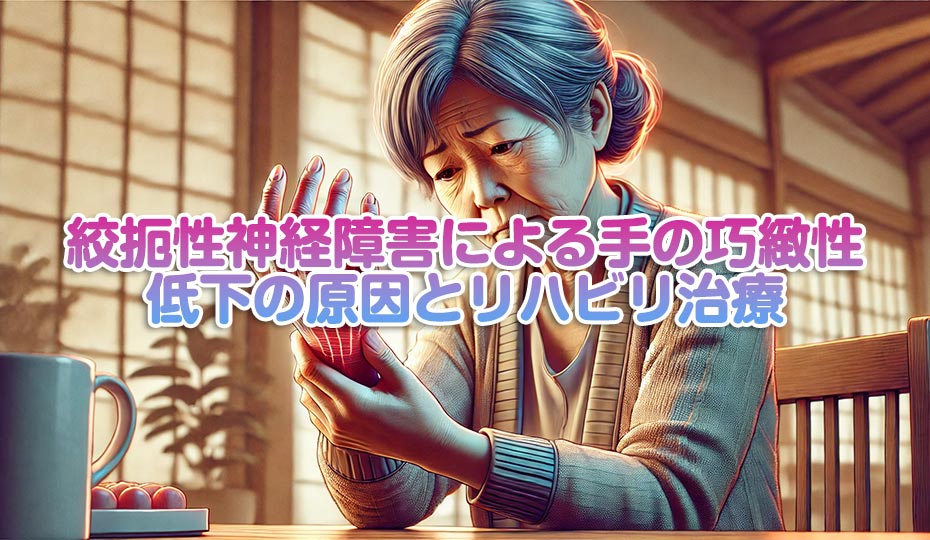

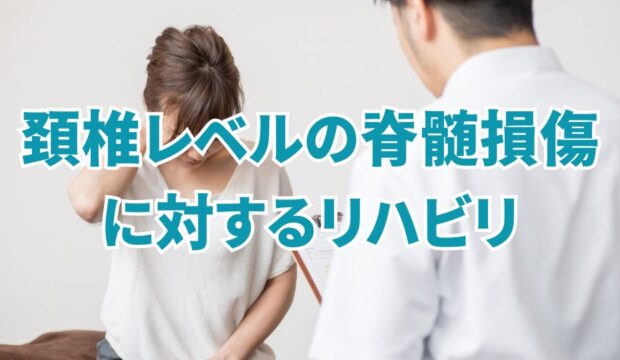












コメント