パーキンソン症候群に対するリハビリの目的
リハビリを行う際のポイント
それぞれの症状に合わせた個別のリハビリ内容
パーキンソン症候群とはパーキンソン病以外で類似の症状を示す疾患群です。
振戦、筋固縮、無動、姿勢反射障害のうちの二つ以上を認めると診断され、進行性核上性麻痺、レビー小体型認知症、大脳皮質基底核変性症など様々な疾患があります。
この記事ではパーキンソン症候群に対するリハビリの基本的な考え方について解説します。
リハビリの目的は「動ける状態」の維持と安全確保

パーキンソン症候群とは、進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症、レビー小体型認知症などのパーキンソン病で見られる臨床上の特徴を持った疾患群のことを指します。
パーキンソン症候群に対するリハビリテーションの目的はできるだけ長い期間「動ける状態」を維持することと、転倒を予防することです。
パーキンソン症候群は進行性の疾患であるため、少しずつ歩行能力が低下し、日常生活動作も障害されます。
そのため、リハビリはパーキンソン症候群の進行度合いによって行う内容が変わります。
初期の段階では活動性の低下を予防し、身体機能をできる限り維持することが重要になります。
パーキンソン症候群における下肢の筋力低下は罹病期間や重症度などよりも加齢による影響が大きいことがわかっています。
加齢に不動が加わってしまうと、筋力の低下が大きく起こります。
診断がついてしまったことでショックを受ける方も多く、転倒の予防のために外出を避ける方もいますが、外出をしないことは活動量の低下に繋がり、結果的に筋力低下が進んでしまう原因になります。
そのため、活動量を維持することは非常に重要です。
また、下肢の筋力を鍛えることで歩行能力の向上や日常生活動作の改善ができることが明らかになっています。
パーキンソン症候群の初期段階ではしっかり活動量を保つようにしましょう。
症状が進んで中等症になった際は、転倒の予防が最重要になります。
パーキンソニズムの症状に姿勢反射障害があります。
この障害はふらついた際に姿勢を保ち、転倒を防ぐための反応が低下してしまう状態を指します。
姿勢反射障害が出現してしまうと転倒のリスクが非常に高くなるため、体幹や股関節の筋力を鍛え、バランス練習を積極的に行うことが重要です。
さらに進行し重症になると褥瘡予防や関節可動域を保つことが目的になります。
この状態まで症状が進むと一人では動くことが困難となり、不動に伴う褥瘡や関節可動域制限などが問題になります。
このようにパーキンソン症候群のリハビリではできるだけ動ける状態を維持して、転倒予防などの安全確保を行うことが非常に重要です。
運動・バランス・生活動作の3本柱を意識する
パーキンソン症候群では姿勢反射障害や歩行障害などの症状が出現します。
そのため、リハビリでは運動機能・バランス動作・生活動作のそれぞれに対するアプローチが重要です。
パーキンソン症候群は高齢者に多く発症する疾患であり、上述の通り加齢による筋力低下の影響が大きいとされています。
そのため、筋力トレーニングを行うことで筋力を維持向上することが必要です。
また、活動量の低下による心肺機能低下に対して有酸素運動を行うことで、心肺機能を向上させることができるとされています。
姿勢反射障害ではふらついた際に手をついたり、体幹を倒れないように保持することが難しくなります。
バランストレーニングはパーキンソン症候群患者の転倒を予防するために必要です。
具体的なバランストレーニングの内容は脚を閉じた状態での立位保持やリーチ動作、片脚立位などがあります。
これらの練習を行うことで体幹の筋力向上だけでなく、動作の学習に繋がり転倒の予防効果が期待できます。
パーキンソン症候群では様々な障害によって生活動作能力が低下します。
特に歩行能力は低下しやすく、リハビリでは歩行練習を積極的に行う必要があります。
歩行障害の特徴として、1歩目が踏み出せない、歩幅が狭くなってしまい小刻み様歩行になってしまうなどがあります。
どちらの障害に対しても、外からの聴覚を使用したリズム刺激や線を跨ぐなどの視覚的な刺激を入力しながら歩行練習を行うと改善効果が期待できます。
これらの動作は日常生活にも応用できるため、自宅でも意識して行うことが重要です。
認知障害や筋緊張に合わせた個別対応が必要
パーキンソン症候群では認知機能の低下や筋緊張の異常が出現することがあり、一人一人に合わせたリハビリの個別メニューを考える必要があります。
中でも、レビー小体型認知症は認知機能低下が出現しやすいパーキンソン症候群です。
レビー小体型認知症は脳の中にレビー小体が出現し、認知機能障害や幻視、パーキンソニズムを特徴とする疾患です。
この認知機能障害は進行性かつ変動が大きく、作業療法や言語療法で認知機能の評価や対策を行うことが重要です。
認知面の低下への対策は環境や周りの関わりなどで周辺症状と呼ばれる二次的な症状を抑えることができます。
パーキンソン症候群では様々な症状がありますが、関節に影響を与える症状として固縮があります。
固縮とは他動的に関節を動かした際に抵抗感を感じる症状のことです。
固縮が原因となり動作が緩慢になったり、関節可動域制限が起きることがあります。
そのため、関節が硬くならないように可動域運動を行う必要があります。
このように認知障害や固縮などの症状に対しては個別のリハビリメニューを行うことが重要です。
まとめ
この記事ではパーキンソン症候群に対するリハビリの基本的な考え方について解説しました。
パーキンソン症候群のリハビリの目的は「動ける状態」の維持と安全確保です。
リハビリでは運動・バランス・生活動作の3本柱を意識することが重要です。
認知障害や筋緊張などの症状に合わせた個別対応が必要です
パーキンソン症候群で錐体外路を損傷してしまった後の脳の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。
今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。
私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。
当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。
よくあるご質問
- パーキンソン症候群のリハビリの禁忌は?
- パーキンソン症候群のリハビリには禁忌とされている治療方法はありません。
しかし、転倒を防ぐための過度な安静は筋力低下や活動性の低下を招いてしまい、日常生活動作能力を低下させてしまうため避ける必要があります。 - パーキンソン病に対するリハビリテーションにはどんなものがありますか?
- パーキンソン病に対するリハビリテーションは理学療法、作業療法、言語療法があります。
それぞれ、身体機能や活動量、認知機能や日常生活動作能力、嚥下機能や高次脳機能を維持することを目的に行います。
<参照元>
(1)パーキンソン症候群の臨床|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/44/5/44_5_564/_pdf
(2)パーキンソン病のリハビリテーション|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrmc/49/10/49_738/_pdf
(3)パーキンソン病のリハビリテーション治療|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrmc/58/3/58_58.303/_pdf/-char/ja
(4)レビー小体型認知症:最近の進歩|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/105/9/105_1820/_pdf
関連記事
このページと関連のある記事

2025.02.14
パーキンソン症候群と進行性核上性麻痺の生活サポート方法
パーキンソン症候群を呈する進行性核上性麻痺の患者様ができる限り快適に日常生活を送るためには運動療法を初めとするリハビリテーションは大切です。適切な運動やリハビリによって転倒リスクの軽減や誤嚥の予防にもなります。この記事ではさらに家族や介護者ができる生活のサポートについても詳しく解説します。...

2025.02.03
不全麻痺の治療とリハビリテーションの選択肢
脊髄損傷では障害を受けた脊髄以下が全く動かなくなる完全損傷と障害部位以下が一部ダメージを受ける不全損傷があります。不全損傷では、初期の治療はもちろん状態が落ち着いた後のリハビリテーションが重要です。この記事では不全損傷に対する初期治療の方法やリハビリテーション、最新のリハビリ機器を使用した治療方法に...




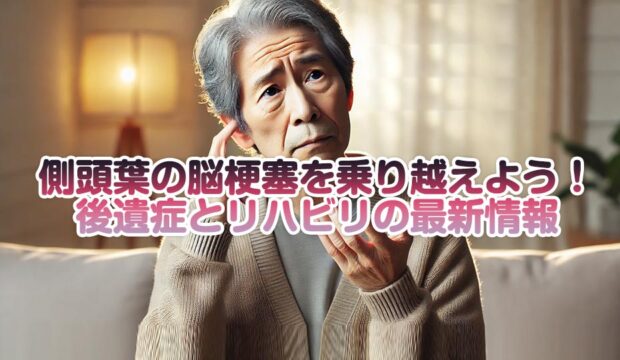











コメント