・脊髄損傷不全麻痺の治療方法
・不全対麻痺に対するリハビリテーション方法
・最新のロボットを使用したリハビリテーションについて
脊髄損傷では障害を受けた脊髄以下が全く動かなくなる完全損傷と障害部位以下が一部ダメージを受ける不全損傷があります。
不全損傷では、初期の治療はもちろん状態が落ち着いた後のリハビリテーションが重要です。
この記事では不全損傷に対する初期治療の方法やリハビリテーション、最新のリハビリ機器を使用した治療方法について解説します。
不全麻痺に対する薬物療法と手術の適応条件

外傷や脊髄を栄養している血管が詰まることによって発症する脊髄損傷には完全麻痺と不全麻痺があります。
完全麻痺とはその名前の通り、障害された脊髄神経のレベル以下の運動機能および感覚機能、自律神経機能が完全に脱失してしまうことを指します。
不全麻痺とは、障害された脊髄神経レベル以下の運動機能や感覚機能などが一部障害された状態を指します。
脊髄損傷の治療を行う際はまず全身の検査を行うことから開始します。
その後、急性期治療として手術療法と保存療法のどちらかを選択します。
手術療法は脊椎の不安定性などがあり、体動などの軽い外力の影響で麻痺が悪化してしまう可能性があったり、できるだけ早期から積極的なリハビリテーションを行いたい場合に適応があります。
具体的な手術内容としては、脊髄が圧迫されている部位の徐圧やインプラントなどを使用した脊椎固定などがあります。
手術療法が適応にならなかった場合は保存療法の適応となります。
保存療法ではコルセットなどを使用した装具療法や損傷後の悪化を防ぐための薬物療法があります。
脊髄損傷を発症すると様々な要因によって、徐々に麻痺が悪化する可能性があります。
その中でも、炎症や酸化ストレスを抑える薬を使用することで麻痺の悪化を少なくできる可能性があると言われています。
残念ながら手術療法と保存療法のどちらでも一度損傷してしまった脊髄神経の完全な回復は困難です。
そのため、リハビリテーションを行い身体機能や日常生活動作を上げることが非常に重要です。
理学療法や作業療法を活用した機能回復プラン
脊髄損傷後のリハビリテーションには理学療法と作業療法があります。
理学療法は基本動作能力と呼ばれる移動能力に関わる動作能力の向上を目指して運動療法や物理療法を行います。
発症後、麻痺症状の悪化がないか確認しながら慎重に検査を行い、全身の運動神経や感覚神経がどの程度ダメージを受けているか確認します。
この際によく使用される評価はASIA Impairment Scaleです。
この評価方法は麻痺の程度を確認するための評価で、不全麻痺の程度を判断することができます。
特に発症すぐの分類がGrade C〜Eの運動機能の障害が重度でない症例に関しては早期から積極的な下肢の機能トレーニングを開始するべきとされています。
具体的なトレーニングとしては基本動作能力を向上させるための起立練習や歩行練習が推奨されています。
自力で体重を支えることが難しいGradeAやBの場合は装具やロボットなどを使用することもあります。
AIS GradeCで年齢が50歳未満の方では歩行を獲得する可能性が80−90%であり、Grade Dの方ではほぼ全ての方が歩行を獲得できると言われています。
また、Gradeが高い方でもリハビリで身体機能が上がった報告もあります。
そのため、理学療法では積極的に歩行の獲得を目指して運動療法を行うことが非常に重要です。
作業療法は日常生活動作能力、つまりセルフケアを含む日常生活動作を行うための動作や下肢動作などができるようになることを目標に日常生活動作練習や巧緻動作練習などを行います。
特に頸髄損傷を発症した方は中心性脊髄障害という障害を認めることがあります。
この障害では下肢よりも上肢に麻痺が強く出ます。
不全麻痺によって上肢の障害が起こると、指先で細かい動作を行う巧緻動作や日常生活動作能力が障害されます。
上肢の麻痺が起こるとトイレ動作や更衣動作なども行いづらくなります。
発症早期からの作業療法はセルフケアの自立を目指して、上肢のトレーニングや環境調整などを行います。
セルフケア方法を確立できれば、徐々にレベルの高い日常生活動作の練習を行います。
理学療法と作業療法は発症早期から回復期、自宅に退院した後の生活期まで行うことで基本動作能力や日常生活動作能力の維持・向上につながるため、継続したリハビリテーションを行うことが重要です。
最新のリハビリ機器を用いた治療事例
最新のリハビリ機器として耳にする機会が多いものとしてロボットスーツHALが挙げられます。
HALとは、下肢に装着するロボット機器であり、人間が身体を動かす際に発生する生体電位信号を読み取って運動のサポートをしてくれる特徴があります。
日本では保険診療として、神経難病などに対して保険適応されています。
過去に様々な研究が行われており、中枢神経損傷後の機能改善の可能性があると言われています。
実際にHALと運動療法を組み合わせることによって、歩行能力やバランス能力が改善した報告もあります。
今後もHALのように様々なロボットが開発され、脊髄損傷不全麻痺の方のリハビリテーションの役に立つことが期待されます。
まとめ
この記事では脊髄損傷における不全麻痺の治療方法やリハビリテーションについて解説しました。
不全麻痺に対する治療は手術療法と保存療法があり、脊椎の不安定性やリハビリテーションをできる限り早期から開始したい場合などに手術が選択されます。
リハビリテーションは主に理学療法と作業療法があり、組み合わせて行うことで日常生活動作能力の向上に繋げることができます。
最新のリハビリ機器としてはロボットスーツHALなどがあり、今後も様々なリハビリテーションロボットの開発が期待されています。
脊髄損傷で神経を損傷してしまった後の脊髄の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。
今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。
私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。
当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。
よくあるご質問
- 不全対麻痺のリハビリにはどんなものがありますか?
- 脊髄損傷不全対麻痺のリハビリは主に理学療法と作業療法があります。
それぞれ、歩行などの基本動作、セルフケアや家事動作などの日常生活動作能力の改善を目的に行います。
どちらも早期から開始することが重要です。 - 不全麻痺にはどんな分類がありますか?
- 脊髄損傷不全麻痺の分類にはASIA Impairment Scal(AIS)があります。
下肢がどの程度実用的に使用可能かを5段階に分けたもので、受傷時のAISがgradeC以上であれば将来的に実用的な歩行を獲得する可能性が高いと言われています。
<参照元>
Who is going to walk? A review of the factors influencing walking recovery after spinal cord injury:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3952432/pdf/fnhum-08-00141.pdf
理学療法ガイドライン第2版:
https://cms.jspt.or.jp/upload/jspt/obj/files/guideline/2nd%20edition/p107-129_02.pdf
脊髄損傷の保存療法 ー薬物療法も含めてー:
https://www.saitama-med.ac.jp/albums/abm.php?d=531&f=abm00003989.pdf&n=28_s_p104_105.pdf
ロボットスーツHALを用いた脊髄損傷不全麻痺者に対する継続的歩行練習の効果|J STAGE:
https://www.jstage.jst.go.jp/article/rika/29/2/29_165/_pdf/-char/ja
関連記事
このページと関連のある記事
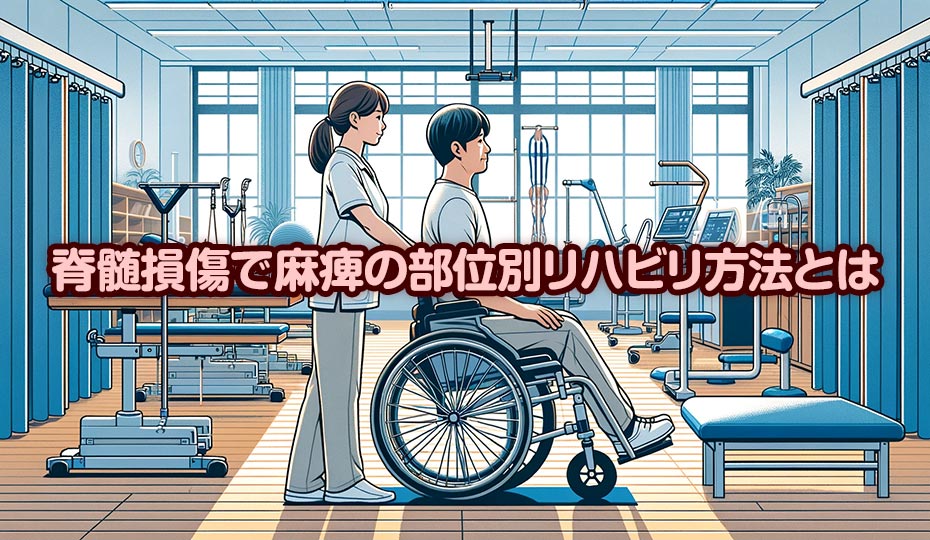
2024.04.24
脊髄損傷で麻痺になる部位別のリハビリ方法とは
脊髄が損傷されると、運動麻痺、感覚障害、自律神経障害、排泄障害などが生じます。脊髄損傷は損傷された髄節レベルによって麻痺の程度が異なり、運動や日常生活レベルも様々です。 この記事では、脊髄損傷の髄節レベル別のリハビリ内容について説明しています。また、予後についても説明していますので、ぜひ最後までご...

2024.08.16
頸椎損傷の予後を改善するためのリハビリとは
頸椎損傷のリハビリテーション戦略と幹細胞治療の相乗効果について解説します。頸椎損傷は日常生活に深刻な影響を与えますが、効果的なリハビリテーションによって生活の質を向上させることができます。筋力強化やバランストレーニング、心理的サポートが回復を支え、幹細胞治療との併用でより高い効果が期待されます。...




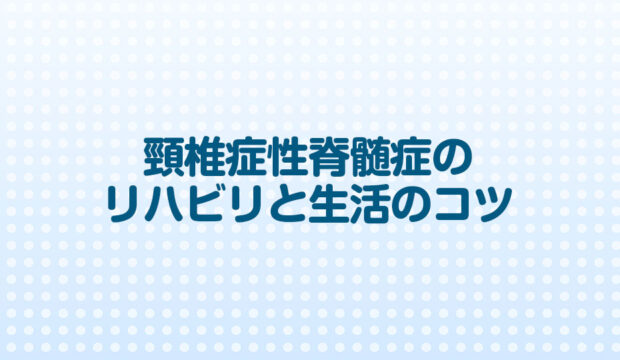











コメント