・言語障害に対するリハビリ方法
・動麻痺を改善するためのリハビリ
・自宅でも行えるリハビリとその効果
脳梗塞を発症すると言語障害や運動麻痺が出現します。
言語障害には言語療法、運動麻痺には理学療法や作業療法をできるだけ早期から開始することが重要です。
また、自宅に退院してからもリハビリを継続することで身体機能や日常生活動作は改善することができます。
この記事では脳梗塞後の言語障害と運動麻痺に対するリハビリ方法を解説します。
言語機能回復を目指した言語療法の実践例

脳梗塞を発症すると言語障害を認める場合があります。
言語障害は大きく2つに分けることができ、それぞれ失語症と構音障害があります。
失語症とは脳の損傷を原因とした言語機能の障害であり、言語の理解や言語の表出などに障害を受けることを指します。
失語症はさらにブローカ失語とウェルニッケ失語に分けることができます。
ブローカ失語は話す際に単語がなかなか出てこず、非流暢に話を行いますが理解は概ね良好な失語症です。
言語療法ではまずコミュニケーション手段の確立から行います。
例として、簡単な言葉やジェスチャーなどでコミュニケーションが行えるように本人と家族と方法を統一します。
次に行うブローカ失語に対する言語療法は、構音の訓練、語彙の回収、構文を作る、書字などを対象となる方の言語能力に合わせて提供します。
練習をしばらく継続して、再度評価を行い少しずつ提供する言語療法のレベルを上げていきます。
ウェルニッケ失語は流暢に話を行えますが、意味のない内容であり単語等の理解ができていないと判断される場合に診断されます。
このタイプの失語症でも、始めにコミュニケーション方法の確立を行います。
その後、ウェルニッケ失語の程度に合わせて、聴覚を使用した認知面のトレーニングや言葉の把持練習、構文の理解や読み練習などを行います。
構音障害は失語症と違い、言葉の認識は可能ですが発声に関わる筋肉が障害を受けることで思ったように話すことができない症状です。
リハビリは発声練習を中心に行います。
失語症や構音障害は発症から長期間にわたって改善するため、継続した訓練を行うことが重要です。
麻痺改善のための運動療法と感覚訓練
脳梗塞では失語症以外にも運動麻痺が出現します。
運動麻痺は発症してから6ヶ月までに改善するとされています。
そのため、発症後すぐの急性期からリハビリを開始し、継ぎ目なく回復期リハビリテーション病院でのリハビリを行うことが重要です。
下肢の運動麻痺に対する運動療法として最も有効と言われているトレーニングは歩行練習です。
麻痺が重度で下肢に体重を乗せることができない場合は、装具などを使用して早期から歩行練習を行うことが推奨されています。
また、歩行練習以外にも起立練習や下肢の筋トレなどを行うことも有効です。
上肢の運動麻痺に対しては早期から洗顔や髭剃りなどのセルフケアの練習から開始します。
回復期では麻痺側上肢のリーチ動作練習やメトロノームを使用した上肢の反復運動などを行います。
適応のための条件がありますが、上肢の麻痺に対してはCI療法という治療方法が有効とされています。
CI療法とは非麻痺側上肢をスリングやミトンなどで動けない状態にし、麻痺側上肢の段階的なトレーニングを行う方法です。
このトレーニング方法はあえて非麻痺側上肢を使えないようにすることによって、麻痺側上肢の活動量を上げることで上肢機能の改善を目指すことができます。
また、運動を行うためには感覚情報も非常に大切です。
そのため、麻痺の改善を目指すには麻痺側に対して運動の量を多くし、感覚入力を増やす必要があります。
感覚情報を増やすためには、できるだけベッド上で寝ている時間を減らし、歩行時間やセルフケアの時間などを確保するようにしましょう。
リハビリ効果を高める家庭でのトレーニング方法

リハビリは病院を退院した後も自宅で継続して行うことが大切です。
退院後、活動量が減ってしまうと筋力や体力が低下し本来行えるはずの日常生活動作が行えなくなることがあります。
このような状況を避けるためにも自宅リハビリを行いましょう。
自宅リハビリで最も行いやすい練習は散歩です。
活動量を確保するために歩数計や、楽しみのためにスマートフォンのアプリなどを使用することなどもおすすめです。
他にも、生活の中のセルフケアや家事動作などを自身で行うこともリハビリになります。
訓練として自宅リハビリを行うのであれば、下肢の運動では起立練習や片脚立ち、上肢の運動では洗濯バサミを使用したピンチ練習や書字練習などの巧緻動作練習が有効です。
自宅に退院した後も筋力や日常生活動作能力は向上させることができます。
ぜひ、自宅に退院した後もリハビリを行いましょう。
まとめ
この記事では、リハビリで目指す言語障害と麻痺の改善について解説しました。
言語障害は長期間改善の可能性があり、言語療法を継続しリハビリを継続することで改善が期待できます。
麻痺は発症早期から6ヶ月間まで改善を認めるため、早期からのリハビリが有効であり、継ぎ目ないリハビリを継続して行うことが重要です。
また、自宅リハビリを行うことで筋力や日常生活動作能力の改善が期待できます。
脳梗塞で神経を損傷してしまった後の脳の治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。
今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。
私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。
当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。
よくあるご質問
- 脳梗塞の片麻痺を改善するにはどうしたらよいですか?
- 脳梗塞の片麻痺は発症早期に大きく改善するため、できるだけ早い時期からのリハビリが重要です。
また、麻痺側への感覚情報の入力も効果的であるため、できるだけ麻痺側を使えるような状況を作ることも必要です。 - 言語療法のリハビリ内容は?
- 言語療法では大きく分けて嚥下訓練と言語訓練があります。
嚥下訓練は食事の際に誤嚥しないように、飲み込みのトレーニングをします。
言語訓練では失語症や構音障害で話すことが困難になった方を対象に、コミュニケーションの練習を行います。
<参照元>
・感覚障害へのリハビリテーション|J STAGE:https://www.jstage.jst.go.jp/article/kochiotjournal/1/0/1_37/_pdf
・左手に強い体性感覚障害のある慢性期脳卒中患者に対する能動的感覚再学習の試み:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jotr/40/4/40_503/_pdf/-char/en
関連記事
このページと関連のある記事

2024.11.05
右片麻痺と言語障害のリハビリ方法
右片麻痺による運動麻痺などの身体的な問題と、言語障害が引き起こすコミュニケーションの困難を改善するための効果的なリハビリ方法について解説しています。運動麻痺においては神経ネットワークの再構築のための運動療法が重要であり、言語療法による発語練習と周囲のサポートが日常生活を豊かにします。...
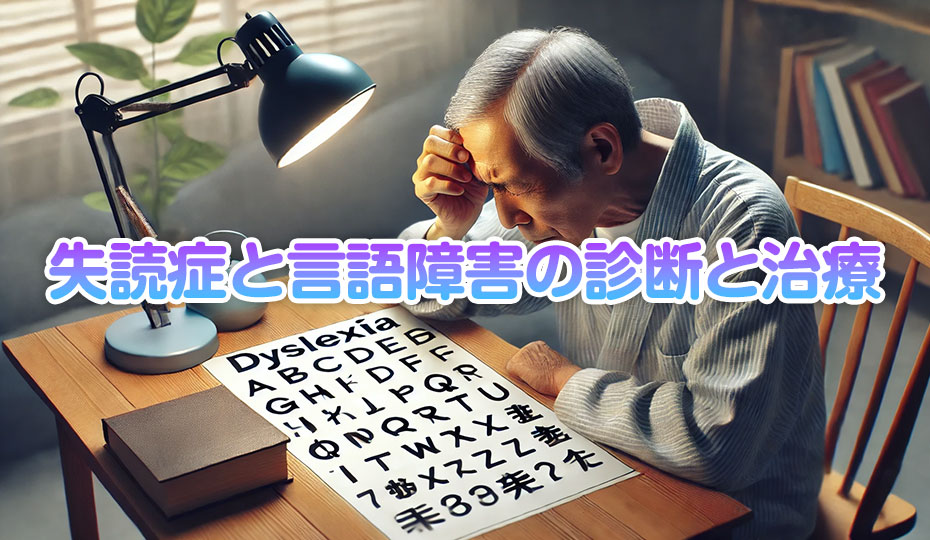
2024.07.18
失読症と言語障害の診断と治療
失読症は、脳梗塞や脳卒中、外傷などで脳の左半球が損傷を受けることで発生し、読み書きに障害をもたらします。本記事では、失読症のタイプや診断プロセス、改善戦略を解説し、リハビリテーションや患者と家族への具体的なサポート方法を紹介します。適切なアプローチを知ることで、失読症の克服と生活の質向上を目指しまし...




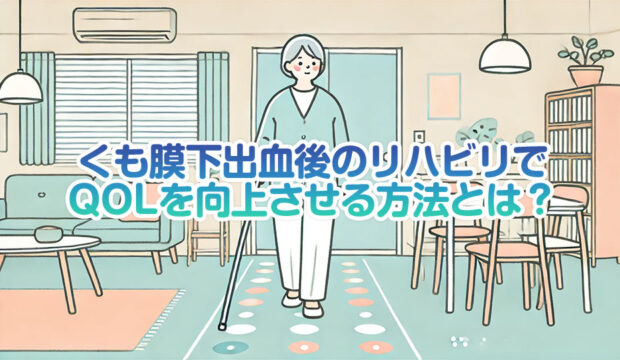











コメント