・脳梗塞でむくむ原因がわかる
・脳梗塞後のむくみを解消できる運動がわかる
・弾性ストッキングやリンパマッサージがむくみに有効な理由がわかる
脳梗塞による麻痺などによって体動が低下すると、特に上肢や下肢の血管への刺激が低下し、血流が悪くなることでむくみが生じます。
そこで、むくみ対策には弾性ストッキングの着用やリンパマッサージ、食事療法や運動療法が行われます。
この記事では、脳梗塞後のむくみ解消方法について、それぞれ詳しく解説します。
目次
むくみを抑えるための効果的なリハビリと運動
脳梗塞や脳出血によって、脳から身体への運動の指令回路(これを錐体路と呼ぶ)が障害されると、脳からの運動の指令が身体に伝わらず、麻痺に陥ります。
本来、血管周辺の筋肉が収縮と弛緩を繰り返しポンプのような役割を果たすことで、血管は外側から圧迫され、血流が増幅されますが、長期的な麻痺に陥ると筋肉の収縮や弛緩が得られなくなり、血管への刺激がなくなることで血流も停滞します。
その結果、特に重力の影響で血液の貯留しやすい下肢では、血管に血液が貯留し、水分が血管外に漏出することでむくみやすいです。
逆に言えば、脳梗塞後のむくみを抑えるためにはある程度上肢や下肢の筋肉を動かす必要があります。
ただし、麻痺がある中であまり積極的な運動を行うと転倒のリスクもあるため、椅子に座った状態や床にマットを敷いた状態で、座位のまま足首を曲げ伸ばしする運動がおすすめです。
足首を曲げたり伸ばすことで、ふくらはぎの筋肉(ヒラメ筋や腓腹筋)が活発に収縮と弛緩を繰り返し、下腿の血管が外部からポンピングされることで、血流改善とそれによる浮腫改善が目指せます。
上肢の場合も同様で、手関節の屈曲と伸展を繰り返すことが浮腫予防にとって肝要です。
リンパドレナージマッサージでむくみを改善

脳梗塞によるむくみには、リンパドレナージマッサージも効果的です。
そもそも「リンパ」とは、リンパ液・リンパ管・リンパ節から構成されるシステムのことで、細胞と細胞の間に蓄積した水分をリンパ液として回収し、リンパ管を通って血液に戻しています。
なんらかの原因でリンパ管が閉塞したり、リンパ管の流れが悪くなると、余分な水分を回収しきれなくなり、むくみが生じます。
逆に言えば、脳梗塞による麻痺によって生じたむくみに対して、リンパドレナージマッサージ、つまりリンパの流れをよくするマッサージを行うことで、むくみが改善されるわけです。
リンパドレナージマッサージの具体的な方法は、強すぎない力で上肢や下肢のリンパ管を、リンパの流れに沿ってマッサージすることです。
耳の後ろや頸部、腋窩、膝窩、鼠径部などにはリンパが豊富であり、そこから心臓の方向にやや力を入れて撫でることで、リンパの流れを改善させる効果が期待できます。
過剰に力を入れると血栓が形成されるリスクが高まるため、程よい力加減でマッサージすることを意識しましょう。
自宅でできるむくみ軽減ケア:マッサージや圧迫療法
リンパドレナージマッサージ以外にも、弾性ストッキングを着用することで自宅で簡単にむくみケアを実践可能です。
弾性ストッキングとは、その名の通り弾性を持つストッキングのことで、これを装着することで下肢の血管を程よく締め上げ、下肢の静脈に血液が貯留しすぎないように予防します。
病態に応じて圧迫圧も調整されており、作りとしては足関節部の圧迫圧が最も高く、上に向かうほど圧力が弱くなる段階的圧迫圧の構造になっています。
この構造によって、より地面に近い血管に血液が貯留しにくくなり、より心臓方向へ血液が灌流しやすくなるわけです。
さらに、弾性ストッキングの着用は運動やエクササイズとも相性が良く、通常の運動時に比較して、弾性ストッキングの着用下での運動は下肢の血流速度が有意に増加することが知られています。
脳梗塞でも自宅で簡単、かつ安全に実施できる、爪先立ちや膝でボールを挟む運動など、弾性ストッキングを着用することでより高い効果が得られるでしょう。
食事療法でむくみを改善!むくみに良い食べ物とNGな食べ物

むくみ対策には摂取する食事内容が大きく関わりますが、中でもむくみにとってNGな食べ物は下記の通りです。
- 塩分の高い食事
- アルコール
兎にも角にも、塩分の高い食事を摂取すると血液中のナトリウム濃度が増加し、ナトリウムには水分を引き込む力があるため、血管内に多量の水分が貯留することでむくみの原因となります。
カップヌードルやレトルト食品、外食、漬物など、塩分が高く設定されている食事は控えるべきです。
また、アルコールには血管拡張作用があり、血管透過性が亢進することで血液中の水分が細胞外に流出しやすくなり、むくみの原因となります。
ついついお酒のお供に、塩分の強い、味の濃いものをつまみにしたくなることも、むくみの原因です。
逆に、体内に貯留したナトリウムを体外に排出するためには、カリウムが必要です。
そこで、カリウムの豊富な緑黄色野菜や果実類、豆類、海藻類、魚介類を摂取すると、効率的に浮腫の原因であるナトリウムを体外に排出できるため、ぜひ摂取してみると良いでしょう。
まとめ
今回の記事では、脳梗塞後のむくみ解消の方法について詳しく解説しました。
脳梗塞によって運動機能が低下すると、血流が停滞することで浮腫が生じやすくなります。
浮腫対策には弾性ストッキングの着用やリンパマッサージ、セルフケアでの運動などが良い対策方法です。
また、近年では脳梗塞後のむくみに対して、再生治療が新たな治療法として非常に注目されています。
再生治療によって麻痺の程度が改善すれば、血流が促進されてむくみも解消される可能性があるためです。
ニューロテックメディカルでは、「ニューロテック®」と呼ばれる『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』も盛んです。
「ニューロテック®」では、狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療『リニューロ®』を提供しています。
また、神経機能の再生を促す再生医療と、デバイスを用いたリハビリによる同時治療「同時刺激×神経再生医療Ⓡ」によって、脳梗塞後のむくみの改善が期待できます。
よくあるご質問
- カリウムが一番多い食べ物は何ですか?
- カリウムが一番多い食べ物は里芋類の葉柄であるずいきです。
他にも、昆布やワカメなどの海藻類にカリウムは豊富であり、高血圧にお悩みの方はナトリウム排泄のためにもおすすめの食材です。 - 脳梗塞のリハビリで注意することは何ですか?
- 脳梗塞のリハビリで注意することは、転倒や転落です。
体幹が不安定な状態で無理にリハビリを行うと、転倒する可能性が高く、外傷を負えばさらにリハビリは遅れてしまうため、必ず危険性を伴うリハビリを行う際は介助者とともに実施しましょう。
<参照元>
歩行時における弾性ストッキングの効果の検証~医療用弾性ストッキング・スポーツ用弾性ストッキング・コントロールの比較~|J STAGE:
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cjpt/2014/0/2014_1600/_pdf/-char/ja
栄養成分表示を使って、あなたも食塩摂取量を減らせる|消費者庁:
https://www.caa.go.jp/
関連記事
このページと関連のある記事
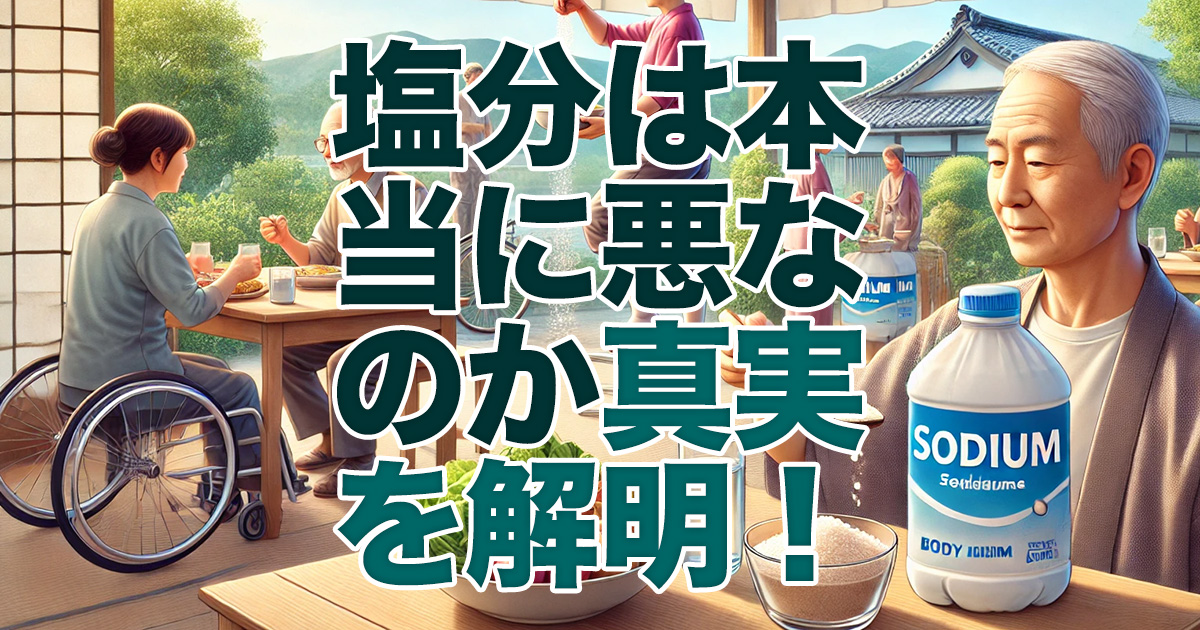
塩分の重要性と適切な摂取量について解説し、過剰摂取が健康に与えるリスクを紹介します。ナトリウムは体液バランスの維持や神経伝達の補助、筋肉の収縮とリラックス、血圧の調整、pHバランスの維持に不可欠です。しかし、過剰な塩分摂取は高血圧や心臓病、脳卒中などの健康リスクを引き起こします。適切な塩分摂取を心がけましょう。

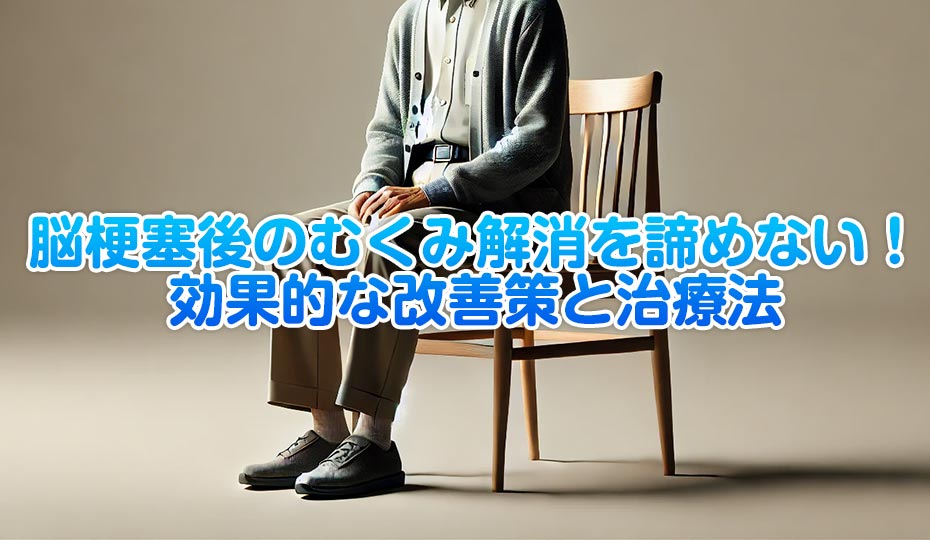
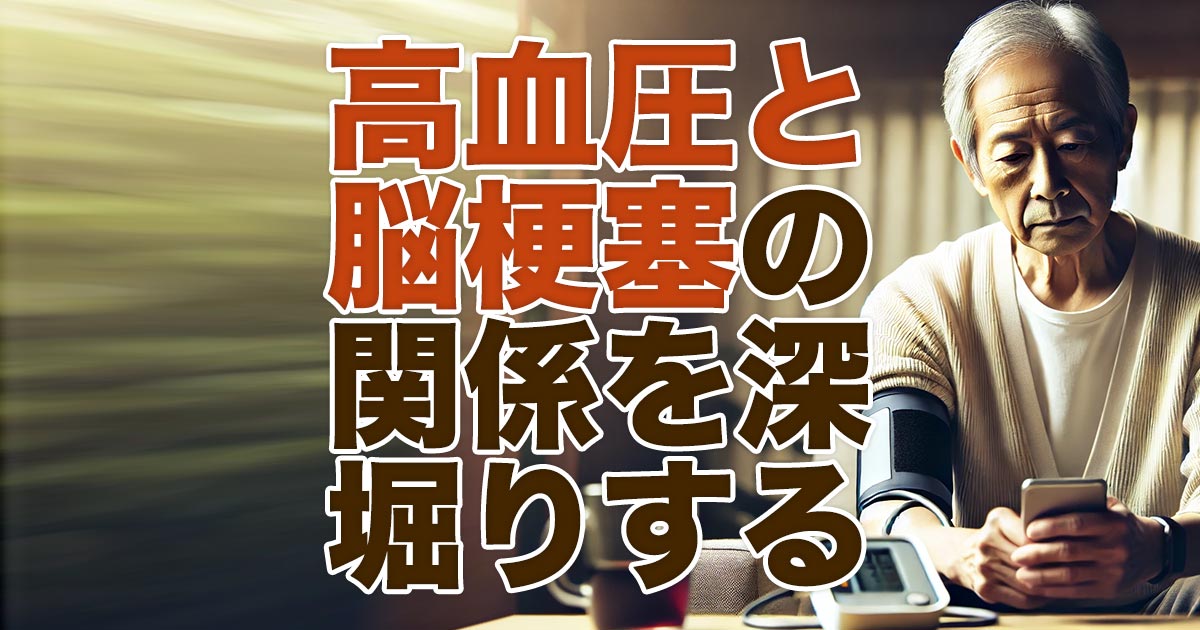














コメント