・麻痺や歩行困難など運動機能障害のリハビリ方法
・失語症の種類と言語障害へのアプローチ方法
・記憶力や判断力の低下に対するリハビリ方法
脳梗塞を発症すると運動機能障害や言語障害、認知機能の低下などが生じる可能性があります。
この記事ではそれぞれ麻痺や歩行困難の症状に対して行われる運動療法、失語症の主な種類とそのアプローチ方法、記憶力や判断力が低下する認知機能の低下に対するリハビリテーションについてご紹介しています。
目次
運動機能障害:麻痺や歩行困難へのリハビリ方法

脳梗塞を発症した際に麻痺が起こることがあります。
脳梗塞後の麻痺は「片麻痺」が多く、身体の半身に麻痺が生じる状態です。
この片麻痺が生じると、半身の運動機能や感覚機能が低下し日常生活動作が困難になるだけでなく、歩行能力にも影響を及ぼします。
ここではこのような片麻痺や歩行が困難になる運動機能障害に対して行うリハビリテーションについて解説していきます。
麻痺に対するリハビリテーション
- 関節可動域訓練(ROMエクササイズ)やストレッチ
麻痺をしている半身は随意的に動かすことが困難となる場合があるため、不動により関節が硬くなり制限が出ないように他動的または自動的に関節の運動を行います。 - 筋力トレーニング
麻痺している側の筋力が低下しないように筋力トレーニングを行います。
特に初期の場合は麻痺をしている半身の筋肉の出力を上げるよう理学療法士や作業療法士がアプローチを行います。
歩行困難に対するリハビリテーション
- バランス訓練
麻痺によってバランス能力も低下するため、立位姿勢や歩行時のバランスを向上させるためのトレーニングを行います。
バランス能力を向上させることで転倒リスクを軽減することに役立ちます。 - 歩行訓練
歩行能力を回復させるためリハビリスタッフと共に実際の歩行訓練を行っていきます。
初期では下肢装具を装着したり平行棒や歩行器、杖などの歩行補助具を用いたりして段階的に歩行訓練を行います。
このような麻痺や歩行困難に対するリハビリテーションは、入院中の専門家とのリハビリだけでなく退院後の自主トレーニングも重要です。
自宅に帰ってもトレーニングが継続できるように日常生活の中で運動する機会を作るよう準備をしておきましょう。
言語障害:失語症の種類と改善アプローチ
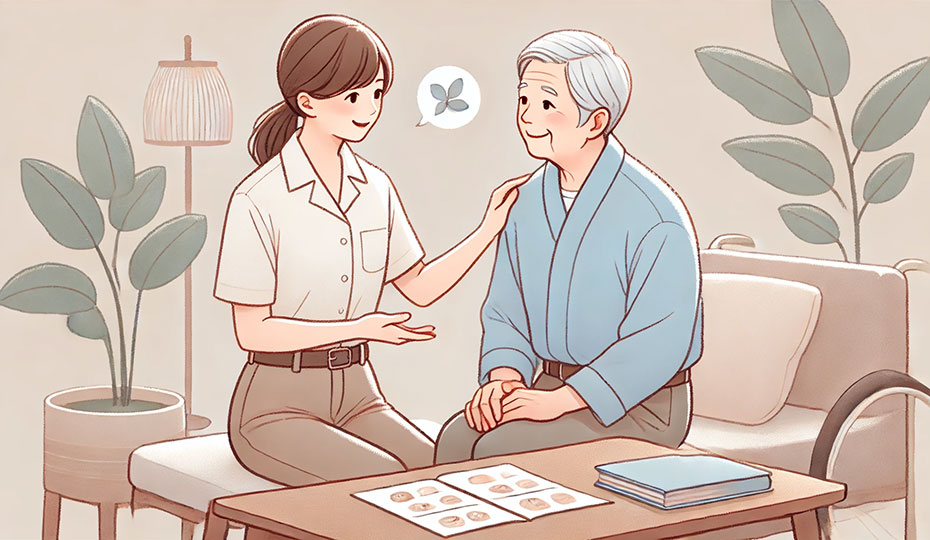
脳梗塞で生じる症状には「話す」「聞く」「書く」「読む」という言葉を使ったコミュニケーションに支障をきたす失語症があります。
この失語症は、舌や口唇などの言葉を発する機能自体は障害されていないのが特徴です。
また失語症にはいくつかの種類がありそれぞれ異なった症状が見られます。
失語症の種類
- 運動性失語(ブローカ失語)
運動性失語は相手の言っている言葉を理解する能力は保たれていますが、自分から話をすることが難しくなります。
また話をする時に音が歪んでしまったり会話量自体が少なくなったりするため、短い単語でのやりとりとなることが多いです。
運動性失語は話を理解することができ、首を振ったり頷いたりというリアクションができるため一見すると失語症と分かりにくいという特徴があります。 - 感覚性失語(ウェルニッケ失語)
滑らかに話すことは可能ですが、相手の話している内容を理解することが難しいです。
そのため会話の量は多いですが、言い間違いが多くなり言葉も支離滅裂になることが多くなります。
また文字を書くことにも支障をきたします。
感覚性失語は理解力が低下したように見えるため認知症を患ったような印象を与えることがあります。 - 全失語
運動性失語と感覚性失語に加え、言語機能のすべてが重度に障害された状態を全失語と言います。
全失語では自分で話すことや相手の話を聞き理解すること、言葉を復唱すること、文字の読み書きなどに支障が生じるため非常にコミュニケーションが難しくなります。
言語障害の改善アプローチ
失語症を始めとする言語障害のリハビリテーションは言語聴覚士が主に担当します。
言語聴覚士は、まずはどのタイプの失語症に当てはまるかスクリーニング検査などを用いて症状の把握を行います。
そしてそれぞれのタイプに合わせて段階的に言語機能の訓練を行っていきます。
例えば簡単な単語の理解・話す・書く・読むなどから短い文、さらに談話へとレベルを上げていきます。
また日常生活の中で必要なコミュニケーションの訓練も行っていきます。
挨拶や簡単な日常会話などから日常生活の中でありそうな場面をイメージし、絵カードやジェスチャーを用いた訓練なども行います。
さらに言語聴覚士はご家族の方にもコミュニケーション方法の指導をし、意思疎通の支援を図ります。
認知機能の低下:記憶力や判断力のリハビリテーション
脳梗塞では記憶障害や注意力・判断力の低下など認知機能面にも影響を与えることがあります。
脳梗塞後に起こる記憶力の低下では、新しいことが覚えられないのが特徴です。
そのため最近の出来事を思い出せなくなったり同じことを何回も繰り返し聞いたりし、日常生活では約束を忘れてしまう様子なども見られます。
また状況を適切に評価し、適切な行動を選択するという判断力なども低下します。
このような記憶力の低下や判断力の低下などは高次脳機能障害の症状にあたり、その他に注意力の低下や言語障害も含まれます。
記憶力や判断力の低下に対するリハビリテーションは、作業療法士や言語聴覚士などが主に担当します。
計算問題やパズル、記憶ゲームなどを用いた認知機能のトレーニングを行ったり、日常生活上でメモやスケジュール管理表を使ったりすることを訓練で行っていきます。
特に作業療法では本人が興味のある、手先を使った趣味活動を用いてアプローチをすることもあります。
まとめ
この記事では脳梗塞後の運動機能障害のリハビリ方法や失語症へのアプローチ方法、認知機能の低下に対するリハビリについてご紹介しました。
脳梗塞の後遺症では歩行が困難となる片麻痺などの運動機能障害が生じますが、筋力トレーニングや歩行訓練など理学療法士や作業療法士と共に実施していきます。
また失語症には様々な種類があり、言語聴覚士によってそれぞれのタイプに合った言語療法が行われます。
さらに記憶力や判断力の低下といった認知機能の低下に対しては作業療法士や言語聴覚士によって記憶力トレーニングや趣味活動なども行います。
今後はこれまでのリハビリテーションに加え、損傷してしまった神経を回復させる再生医療と組み合わせることで新たな進展がみられることでしょう。
よくあるご質問
- 脳梗塞後のリハビリの目的は?
- まずは麻痺や言語障害などの後遺症を改善し、できるだけ元の機能を取り戻すことが挙げられます。
また生活の質(QOL)を上げるため、日常生活動作能力の改善や社会復帰の支援なども行います。 - 脳梗塞後のリハビリはいつから始めますか?
- リハビリの開始は病状が安定したらできるだけ早期から介入することが重要です。
発症直後から約1週間程度の急性期を経て、約6カ月までの回復期、それ以降の維持期とリハビリを継続して行っていきます。
<参照元>
(1)どうするべき?脳卒中による片麻痺の歩行の特徴とリハビリの進め方!|脳神経リハビリセンター大阪:https://noureha-nagoya.jp/osaka
(2)片麻痺による歩行障害の特徴とリハビリテーションの重要性:脳梗塞リハビリセンター|脳梗塞リハビリセンター:https://noureha.com
(3)失語症のリハビリ方法とは?自然な会話を取り戻すポイント|御所南リハビリテーションクリニック:https://goshominami-clinic.jp
(4)失語症とは?言語聴覚士が関わる失語症について|ふっかライブラリー:https://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/fukkalibrary
(5)高次脳機能障害|脳神経リハビリセンター:https://noureha-nagoya.jp/higher-brain-dysfunction-rehabilitation/
(6)脳梗塞による認知症~脳血管性認知症について~|脳梗塞リハビリBOT静岡:https://www.noureha-shizuoka.com/news/1519/
関連記事
このページと関連のある記事

2025.03.14
外傷性くも膜下出血の治療法とリハビリの重要性
この記事では、外傷性くも膜下出血の治療法として手術と保存療法の選択肢について詳しく解説します。また、リハビリの重要性や長期的な視点での取り組みの必要性についても解説します。外傷性くも膜下出血の治療とリハビリに関する基本的な情報を知りたい方、回復を目指す方やその家族に向けて役立つ内容をまとめています。...

2025.03.07
脳幹梗塞の後遺症と余命を支えるリハビリとケアの重要性
脳幹梗塞は生命維持に関わる脳幹に発生し、重篤な後遺症を伴う疾患です。この記事では脳幹梗塞後のリハビリテーションや生活支援の重要性、運動機能回復のためのリハビリの進め方、嚥下障害や呼吸障害に対するケア、家族や介護者が理解しておくべき支援制度について詳しく解説します。脳幹梗塞の後遺症と向きある方々に役立...
















コメント