脊髄損傷後に生じる心理的な影響や絶望感の具体例とその背景がわかる。
ピアサポートやカウンセリングなど、心の回復を支える支援方法がわかる。
前向きなマインドセットを築くための実践的な考え方やセルフケアの重要性がわかる。
脊髄損傷を負った直後の深い絶望感や心理的ショックは、大きな負担となります。
この記事では、そうした心の揺れへの向き合い方や、回復へと進むためのステップを紹介します。
ピアサポートやカウンセリングの役割、セルフケアによる前向きなマインドの育て方まで、実例と最新の研究をもとに、希望を取り戻すための道筋をわかりやすく解説します。
脊髄損傷後に感じる絶望感とその心理的影響
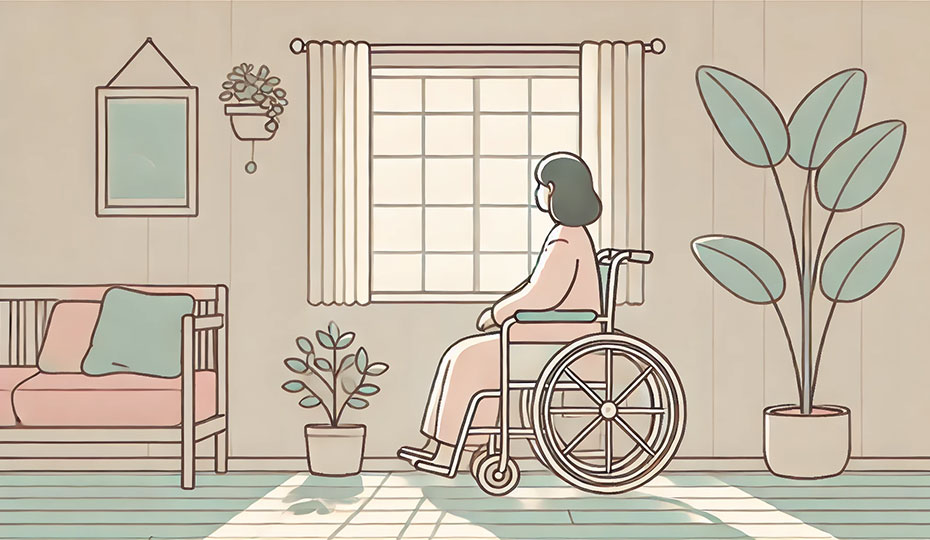
日本では、現在脊髄損傷の患者さんは18歳以上の方では約8万人と推定されています。
脊髄の損傷によって、手足の麻痺や感覚障害、自律神経失調症状などが起こります。
そのため、損傷を受けた脊髄のレベルによっては、自分の意思による体の運動が困難になります。
加えて、受傷直後からの急性期には、外傷性ショックや脊髄ショックという状態に陥ってしまい、生命の危険に晒されることもあります。
そのような急性期の患者さんの心理状態としては、以下のようなものがあると言われています。
- 突然の受傷による不安や混乱の状態
- 自分の置かれた状況に向き合うことを避けたり現実逃避したりすること
- 障害者にみられるということに対する嫌悪感
- 周囲が支えてくれることに対する嬉しさ
- 自分の存在や生命への否定感、絶望感
- 状況や他社への怒り
- 治療や回復への期待
- 自分の行動に対する後悔
また、脊髄損傷を受けてから1ヶ月後程経過すると、脊髄損傷患者さんは以下のような相反する気持ちを体験していきます。
- 将来に自信を持つことと将来への不確かさ
- 冷静と不安
こうした気持ちを持ちながら、その一方で回復や改善を期待する、といった希望を持つこともあります。
カウンセリングやサポートグループの活用方法

脊髄損傷患者さんは、受傷した後のショックが大きく、自分の状況を受け入れるのにはかなりの時間を要します。
また、自分の機能回復への期待も大きく、回復期に医師から機能回復の目安を伝えられても、それを納得することはとても難しい場合があります。
回復期には、患者さんの回復レベルに見合ったリハビリテーション治療プログラムが求められます。
さらに、回復期のリハビリテーション治療のモチベーションを向上させる方法として、ピアサポートを含む心理的サポートがあげられます。
例えば、「公益社団法人 全国脊髄損傷者連合会」では、交通事故などによる脊髄損傷を受けた方たちに対し、同じ障害を持った方たちがサポートするピアサポート、脊髄損傷に関するニュース、制度などの情報提供、スポーツ振興などを行っています。
こうしたピアサポートは、家族や友人からのサポートと同じくらい大切ですが、特に後者からのサポートが不十分な方の場合にはその影響はより強くなると考えられています。
ピアメンターは、同じような経験を経て、他者をサポートするように訓練されている人のことです。
こうしたメンターは、家族や友人とは異なる方法で、人の状況を理解し共感することができます。
ピアサポートを受けることによって、人生への感謝の気持ちが増したり、刺激を受けることができたり、自己アイデンティティが向上したり、あるいは不安や未知への恐怖が軽減するといった、数多くの良い効果が報告されています。
いうまでもなく、脊髄損傷患者さんは、受傷してから障害を受け入れ、社会参加に至るまで、多くの問題に対するアプローチが必要です。
治療の他、カウンセリング、リハビリテーションなど、さまざまな分野の方の包括的な支援が大切です。
前向きに生きるためのマインドセットと実践例
脊髄損傷後に、適切なセルフケアを学び、障害に対処する方法を身につけることは、二次的な健康障害を予防するためにもとても大切です。
二次的な健康障害とは、具体的には褥瘡(じょくそう)や体温調整がうまくできないことによるうつ熱、貧血、生活習慣病などがあります。
また、在宅脊髄損傷患者さんは、慢性的にうつ状態になるリスクが高いことが知られており、特に四肢麻痺の方に多くみられる傾向があります。
そこで、こうした障害を予防し、前向きに生きるためには、セルフケアを身につけることで自分の状態を管理するスキルと自信を身につけることが重要です。
脊髄損傷患者さんは、受傷直後は自分の体が動かなかったり感覚が失われたりすることで、今後回復がみられないのではないか、などといった絶望を味わうことも多いでしょう。
今後生きていく気力が失われることもあります。
しかし、そういった絶望から抜け出すために、家族など身近な人のために生き続けようとする気持ちが大切になる場合もあります。
実際に、不慮の事故によって頸髄損傷を負ってしまった5名の研究では、受傷直後5名中4名が死を考えていたことが明らかになっています。
しかし、徐々に受傷前の生活に近づいたり、視界が広がったり、自分でできることが増えていったり、また、家族や看護師からの本人の生きようとしてほしいという思いを感じることで、生きようとする力を高めていったと結論付けられています。
脊髄損傷を負ってしまっても、残された機能を十分に活かすことでできることは広がります。
また、不全麻痺の場合には、ゆっくりではありますが脊髄損傷の症状改善も期待できます。
一方で、前向きに生きることが難しい時には、家族や友人、ピアサポートなどの助けを借りることも大切です。
まとめ
今回の記事では、脊髄損傷を受けた後の絶望感に対する心のケアと希望の持ち方について解説しました。
脊髄損傷後には、適切なリハビリテーションも必要となります。
そこで、『神経障害は治るを当たり前にする取り組み』を、ニューロテック®と定義しました。
また、脳卒中や脊髄損傷、神経障害の患者さんに対する『狙った脳・脊髄の治る力を高める治療』を、リニューロ®と定義しました。
リニューロ®は、同時刺激×神経再生医療®によって『狙った脳・脊髄の治る力を高める治療』です。
また、その治療効果を高めるために骨髄由来間葉系幹細胞、神経再生リハビリ®の併用をお勧めしています。
再生医療による脊髄損傷治療にご興味がある方は、ぜひ公式HPをご確認ください。
よくあるご質問
- 脊髄損傷のリハビリの目的は?
- 脊髄損傷のリハビリの目的は、残された機能を最大限に活かし、日常生活の自立度を高めることです。
筋力の維持や関節拘縮の予防に加えて、精神的な回復や社会復帰を支えることも大切な目標となります。 - 脊髄損傷のショック期とは?
- ショック期とは、受傷直後に起こる一時的な神経機能の停止状態で、反射や運動、感覚がすべて失われます。
これは「脊髄ショック」と呼ばれ、時間の経過とともに回復の兆しが現れることもありますが、予後の見極めが難しい時期です。
<参照元>
(1)脊髄損傷患者の急性期における体験.日本看護研究学会雑誌.2007;30(2):77- 85.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsnr/30/2/30_20070125006/_pdf
(2)3 脊髄損傷患者.Jpn J Rehabil Med.2022;59;265-270.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrmc/59/3/59_59.265/_pdf
(3)全国脊髄損傷者連合会:https://zensekiren.jp/
(4)McLeod J, Davis CG. Community peer support among individuals living with spinal cord injury. J Health Psychol. 2023 Sep;28(10):943-955. doi: 10.1177/13591053231159483. Epub 2023 Mar 16. PMID: 36924431; PMCID: PMC10467001.:https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10467001/
(5)在宅脊髄損傷者の食生活と食行動・食態度の指標との関連についての検討.栄養学雑誌. 2010;68(3):183-192.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/eiyogakuzashi/68/3/68_3_183/_pdf
(6)脊髄損傷アスリートにおける二次傷害 (脊損者における褥瘡,うつ熱,貧血).日本臨床スポーツ医学会誌.2017;25(3):293-295.:https://www.rinspo.jp/journal/2010/files/25-3/293-295.pdf
(7)在宅脊髄損傷者における軽症慢性うつ状態とその関連要因の検討.The Japanese Journal of Psychology.2000;71(3):205-210.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpsy1926/71/3/71_3_205/_pdf
(8)van Diemen, T., van Nes, I.J.W., van Laake-Geelen, C.C.M. et al. Learning self-care skills after spinal cord injury: a qualitative study. BMC Psychol 9, 155 (2021).:https://bmcpsychology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-021-00659-7
(9)急性期の頸髄損傷患者の体験と生きようとする力に影響を及ぼす看護ケア.Journal of Japan Academy of Critical Care Nursing. 2010; 6(3):46-54.:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaccn/6/3/6_46/_pdf
関連記事
このページと関連のある記事

2025.02.06
脊髄損傷の後遺症と回復に向けた治療とリハビリ
脊髄損傷の後遺症は運動機能障害だけでなく、様々な障害が起こります。特に日常生活に影響を与えることが大きい障害は、運動機能障害、排尿・排便に関わる膀胱直腸障害、触覚や位置覚などの感覚障害と痛みなどが挙げられます。この記事では、脊髄損傷の後遺症の回復に向けた治療方法とリハビリテーションについて解説します...

2025.02.03
不全麻痺の治療とリハビリテーションの選択肢
脊髄損傷では障害を受けた脊髄以下が全く動かなくなる完全損傷と障害部位以下が一部ダメージを受ける不全損傷があります。不全損傷では、初期の治療はもちろん状態が落ち着いた後のリハビリテーションが重要です。この記事では不全損傷に対する初期治療の方法やリハビリテーション、最新のリハビリ機器を使用した治療方法に...

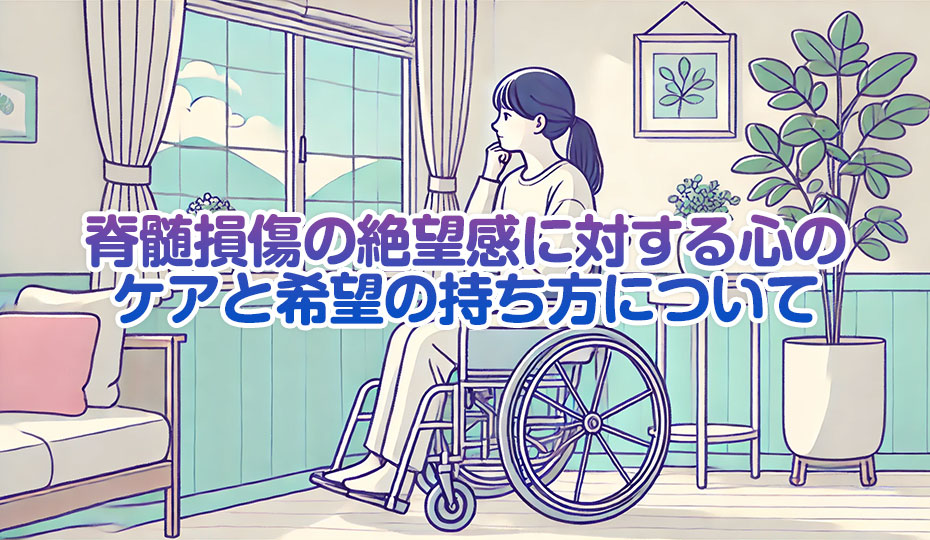



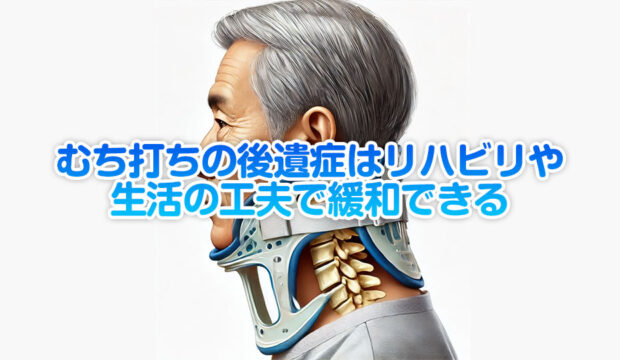










コメント