・左片麻痺患者に出現する症状
・脳出血に対するリハビリテーション
・リハビリテーションを継続することで期待できる効果
脳出血で脳の右半球を損傷すると左片麻痺症状や高次脳機能障害が出現します。
リハビリは早期から開始し、自宅退院後も機能の維持や改善を目標に継続します。
自宅に退院後もさらなる身体機能や動作の改善目的にリハビリを継続することが重要です。
この記事では脳出血後の左片麻痺に向き合うためのリハビリについて解説します。
目次
左片麻痺の後遺症とリハビリの重要性

脳出血で右の脳がダメージを受けた時の障害は左片麻痺や高次脳機能障害などがあります。
高次脳機能障害とは人間の思考、記憶、判断などの高度な機能が障害されることを指します。
左片麻痺患者における高次脳機能障害では、半側空間無視や身体失認などの症状が出現しやすいとされています。
症状の改善にかかる期間は、片麻痺は発症後1ヶ月で急激な改善を認め、6ヶ月まで緩徐に改善し、高次脳機能障害は発症1ヶ月以内で急激な改善を認めるケースもありますが、それ以降の改善はゆっくり進むと言われています。
発症早期よりリハビリテーションを行うことで脳出血後の機能回復や日常生活動作の改善を促すことができます。
しかし、発症後ベッド上で寝たきりになってしまうと本来であれば改善できた機能を取り戻すことができなくなってしまうことがあります。
そのため、脳出血後では早期からの継続したリハビリテーションを行っていくことが非常に重要です。
日常生活に戻るためのリハビリテーションは主に理学療法と作業療法があります。
それぞれについて解説します。
理学療法の役割:運動能力を取り戻す方法
理学療法とは、病気などが原因で運動機能が低下した方に対して、運動機能の維持・改善を目的に運動や物理療法など手段を用いて行われる治療です。
脳出血後の早期ではできるだけ早くベッドから車椅子へ移ったり、可能な方は歩行練習を行います。
全身状態が安定したら、リハビリ病院へ転院し運動の量を増やして日常生活に必要な移動動作の獲得を目指します。
リハビリ病院では、関節可動域運動や筋力トレーニングなどの身体機能を改善するためのトレーニングと歩行や階段などの実際の動作練習を並行して行います。
近年では自立して歩くことが難しい方に対して装具やロボットなどを使用するリハビリテーション病院も増えてきています。
リハビリ病院を退院した後も残存している機能は伸ばすことができるため、身体機能を維持・向上するために訪問や通所などのサービスを利用して、理学療法を続けることができます。
作業療法の実践:日常生活をスムーズにする訓練
作業療法とは、病気などによって日常生活動作が自立できていない方に対して日常生活動作の自立を目指して、作業活動を提供する治療方法です。
急性期では早期から上肢の機能向上を目指した作業活動や高次脳機能障害の評価、トイレ動作や入浴動作などが行えるように日常生活動作の練習を行います。
リハビリ病院へ転院後もこれらの作業療法は継続して行います。
特に、リハビリ病院は日常生活動作の自立を目標に入院される方が非常に多いため、作業療法は非常に重要な役割を持っています。
病棟生活での動作を向上していくことが日常生活動作能力を上げることに直結するため、作業療法士は日常動作練習を行い、動作能力が向上すれば病棟と相談して少しずつ動作を変えていきます。
身体機能だけでなく、高次脳機能障害を持っている方にとって、同じ動作の反復練習を行うことが重要とされており、病棟生活ではできるだけ自宅での動作に近い環境での練習を行います。
退院の前には理学療法士や社会福祉士などと一緒に患者の自宅に訪問し、自宅内の動作確認を行うこともあります。
自宅に退院されてからも行いたい動作は少しずつ変わっていくことも多く、リハビリ病院を退院後、訪問や通所などで作業療法を継続して日常生活動作の練習を継続することができます。
リハビリの継続がもたらす回復の可能性
脳出血後の機能回復は基本的には6ヶ月までとされています。
しかし、上記の期間が過ぎても残されている身体機能はリハビリで改善を目指すことができます。
例えば、麻痺は残存してしまっても起立練習などで下肢の筋力を鍛えることで歩行を再獲得したり、上肢に麻痺があっても反復練習で箸でご飯が食べられるようになるなどです。
これらのようにリハビリを行うことで達成できるようになる動作は多くあります。
現在の我が国の制度では、介護保険や医療保険を利用した訪問リハや通所リハなどのサービスが多くあります。
また、自費診療でのリハビリテーションができる施設も増加しています。
もちろん、リハビリに過度の期待をすることは難しいですが、努力と様々な工夫で日常生活動作が送りやすくなることが多くあり、リハビリテーションを継続することは非常に重要です。
まとめ
この記事では左片麻痺の症状やリハビリ、リハビリ継続の効果について解説しました。
脳出血では発症後早期からリハビリを開始し、継続してリハビリテーションを行うことが非常に重要です。
脳出血で神経を損傷してしまった後の片麻痺や高次脳機能に対する直接的な治療は確立されていませんが、再生医療にはその可能性があります。
今後、神経再生医療×リハビリテーションの治療の研究は進んでいきます。
私たちのグループは神経障害は治るを当たり前にする取り組みを『ニューロテック®』と定義しました。
当院では、リハビリテーションによる同時刺激×神経再生医療を行う『リニューロ®』という狙った脳・脊髄損傷部の治癒力を高める治療を行なっていますので、ご興味のある方はぜひ一度ご連絡をお願いします。
よくあるご質問
- 片麻痺の回復方法はありますか?
- 片麻痺は発症1ヶ月で急激に改善し、6ヶ月まで緩徐に改善すると言われています。
発症直後からリハビリを行うことで片麻痺の回復を促進することができます。
その後の麻痺自体の改善は難しいと言われていますが、残存機能を改善することは可能です。 - リハビリの終了は誰が決めるのですか?
- リハビリの終了は対象者が満足するまでです。
しかし、医療保険におけるリハビリ病院に入院できる期間は期限が決まっています。
自宅に退院後は医療保険だけでなく、介護保険なども併用しながらリハビリを継続することができます。
<参照元>
・厚生労働省 障害者手帳について:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
・厚生労働省 介護保険の概要:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html
関連記事
このページと関連のある記事

2024.10.10
脳出血後の片麻痺を乗り越えるためのリハビリとは
脳出血後の片麻痺を改善するためのリハビリ方法を詳しく解説。片麻痺とは身体の半分が麻痺してしまい動かせなくなってしまう状態のことを言います。右の脳は左半身を、左の脳は右半身を制御しており、脳の片側に障害があるとその反対側の身体に麻痺が生じます。片麻痺と向き合う方々が前向きに取り組むための情報をお伝えし...

2024.05.31
片麻痺の部位別での後遺症改善度合い
片麻痺の後遺症改善は脳損傷後の初期数ヶ月が鍵となり、特に早期リハビリが機能改善に大きく影響します。脳出血や脳梗塞による片麻痺の後遺症は個人差があるものの、理学療法や作業療法、言語療法を組み合わせたリハビリが有効です。本記事では、片麻痺の後遺症改善の可能性やリハビリの具体的な方法と効果について詳しく解...

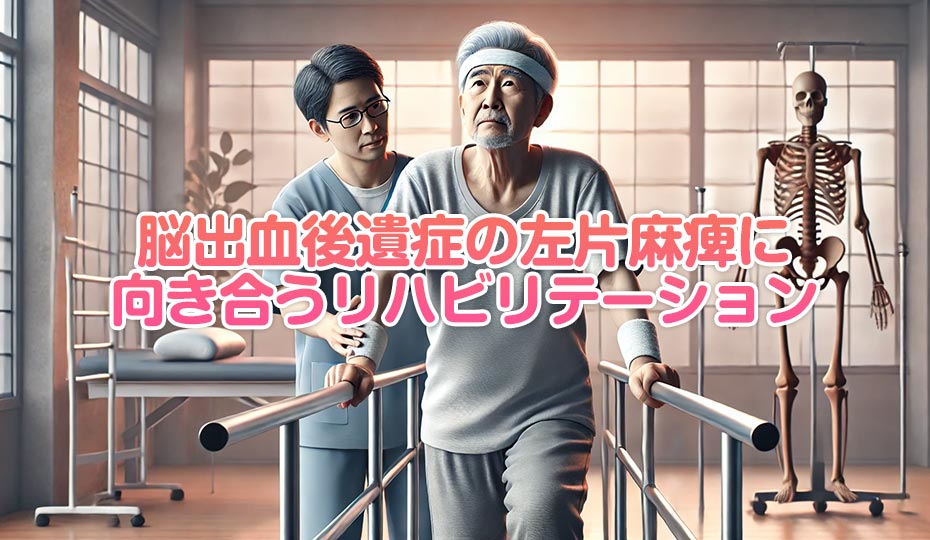














コメント